- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事戦略
- 人事労務
無形固定資産と有形固定資産とは? 例や減価償却について紹介
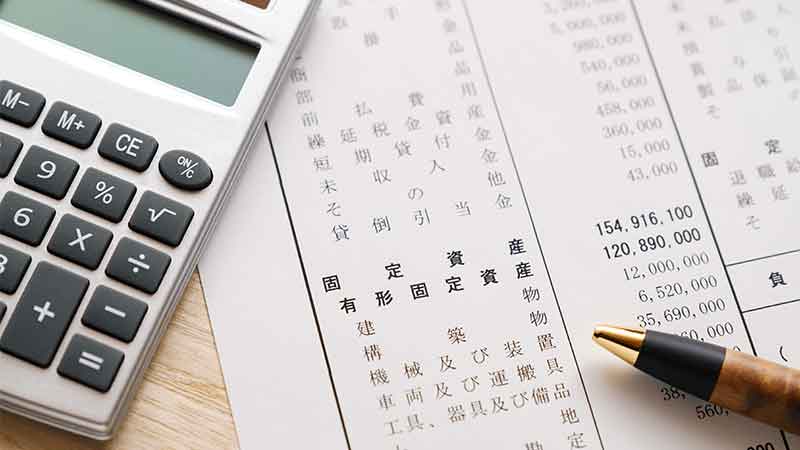
関連資料を無料でご利用いただけます
無形固定資産や有形固定資産など、言葉としては耳にしたことがある方も少なくないでしょう。
しかし「無形固定資産の例や有形固定資産の例としてどのようなものが該当するのかわからない」「固定資産に関する細かい違いや減価償却についてわからない」と感じているケースもあるかもしれません。
そこで本記事では、無形固定資産や有形固定資産について解説しながら、それぞれの具体的な例や違いがわかるようにご紹介します。
目次(タップして開閉)
無形固定資産とは?
無形固定資産とは、目に見えない形のない資産を指します。たとえば、特許権や借地権など法律上の権利は物理的な形態ではありませんが、長期的に利用され、売り上げをつくるための重要な資産といえます。
このように、形にはならない資産を無形固定資産と呼びます。
無形固定資産に該当するもの
無形固定資産に該当するものの例は、以下の通りです。
| ・特許権 ・商標権 ・ソフトウェア ・のれん(M&Aの営業権) ・人的資本 |
物理的ではないものの、法律上の権利やソフトウェアなど、会社の利益を生み出すために使用されるモノが該当します。
| 無形固定資産に関連する記事 知的資産経営とは? 意義とメリット、企業の取り組み事例 人的資本経営とは? なぜ重要? |
有形固定資産とは
無形固定資産が形のない資産であるのに対して、目に見えて形として残る資産を「有形固定資産」といいます。有形資産は長期的に使用し、物理的な形態で所有する資産を指します。
たとえば、土地(オフィスや店舗)や建物、設備などが挙げられます。このように、形として残る資産を「有形固定資産」と呼びます。
有形固定資産に該当するもの
有形固定資産に該当するものの例は以下の通りです。
| ・土地 ・建物および付属設備 ・構築物 ・機械および装置 ・車両および陸上運搬具 ・船舶および水上運搬具 |
有形固定資産は物理的なものであり、会社運営をするにあたって利益を生み出すために必要とされるモノが該当します。
固定資産の減価償却
無形固定資産も有形固定資産も、取得費用を耐用年数に応じて経費に換算する減価償却を行います。減価償却とは会計処理の一種で、時間が経つにつれて資産価値は減少するという考えに基づいて行われます。
減価償却の対象となるのは、次の要件を満たした資産です。
| ・耐用年数が1年以上 ・取得価額が10万円以上 |
減価償却の目的は、年数が経つに連れて資産価値を減少させ、売り上げに対して経費を適正に配分することです。有形固定資産のうち、土地については経年劣化しないものと判断され、減価償却の対象にはなりません。
無形固定資産と有形固定資産の減価償却の違い
無形固定資産と有形固定資産は、減価償却の方法に違いがあります。
一般的な減価償却の方法には
| 定額法 | 取得価額に一定の割合(耐用年数における償却率)をかけて減価償却を計算する |
|---|---|
| 定率法 | 経年にともない、一定の割合を掛けて減価償却費が求める |
があり、個人事業主は定額法を利用する場合が多いです。
無形固定資産は、定額法を使って計算します。無形資産の種類によって耐用年数は異なりますが、定められていないものもあります。
有形固定資産は、定額法や定率法を使って減価償却を行います。原則として、建物や建物付属設備、構築物などは定額法、それ以外は定率法を使います。
ただし、定率法のものは税務署へ届け出を出すと定額法に変更できます。
減価償却の方法による計算式は、以下の表の通りです。償却率は国税庁が定めたものを確認しましょう。
| 減価償却方法 | 計算式 |
|---|---|
| 定額法 | 取得価額×定額法の償却率 |
| 定率法 | 未償却残高×定率法の償却率 |
固定資産の耐用年数
無形固定資産や有形固定資産は、減価償却する際、耐用年数によって計算式も異なります。そこで代表的な固定資産の耐用年数について、ご紹介します。
無形固定資産の耐用年数
| 無形固定資産種類 | 耐用年数 |
|---|---|
| 特許権 | 8年 |
| 商標権 | 10年 |
| 実用新案権 | 5年 |
| 意匠権 | 7年 |
| 借地権 | 非償却 |
| 鉱業権 | 納税地が認定した年数 |
| ソフトウェア | 3~5年 |
| のれん | 5年 |
| 電話加入権 | 非償却 |
参照:『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』法令検索e-GOV
有形固定資産の耐用年数
有形固定資産は、1つの資産でも複数の種類に該当し、それぞれ定められている耐用年数も異なります。
たとえば、建物の国税庁が定める耐用年数は5つに分類され、さらに32以上の細目に分けられており、耐用年数は11~50年と大きな開きがあります。
自社が保有する有形固定資産の耐用年数を確認したいという場合には、国税庁の『主な減価償却資産の耐用年数表』や地域ごとの主税局が公表する耐用年数資料などを確認してみましょう。
参照:『主な減価償却資産の耐用年数表』国税庁
参照:『償却資産の評価に用いる耐用年数』東京都主税局
無形固定資産の例
無形固定資産は、形として目に見えるものではないため、わかりにくいと感じる方もいるかもしれません。そこで、代表的な無形固定資産の例をご紹介します。
特許権
無形固定資産例の1つめは、特許権です。特許権は、工業所有権の一つで、特許法に基づいて登録された発明を独占的・排他的に行使できる権利です。
商標権
無形固定資産例の2つめは、商標権です。商標権は、工業所有権の一つで、商標法に基づいて登録された商標を独占的・排他的に行使できる権利です。
実用新案権
無形固定資産例の3つめは、実用新案権です。
実用新案権は、工業所有権の一つで、実用新案法に基づいて登録された産業上の物品の形状や構造、組み合わせの考案を独占的・排他的に行使できる権利です。
意匠権
無形固定資産例の4つめは、意匠権です。意匠権は、工業所有権の一つで、意匠法に基づいて登録された意匠を独占的・排他的に行使できる権利です。
借地権
無形固定資産例の5つめは、借地権です。借地権は、建物を建てるために地代を払って他者から土地を借りる権利です。借地権には、賃借権と地上権があります。
| 借地権種類 | 特徴 |
|---|---|
| 賃借権 | 建物を売却する際に地主の承諾がいる |
| 地上権 | 建物を売却・転貸する際、自由に行える |
鉱業権
無形固定資産例の6つめは、鉱業権です。鉱業権は、鉱業法に基づいて、一定の区域で鉱物のある地層から鉱物を採掘し、取得できる権利です。
鉱業権はすぐに権利行使できるものではなく、鉱業原簿(台帳)に登録されたうえで、権利として使えるようになる点が特徴です。
また、土地の所有権があっても、鉱物を採掘して取得するには、基本的には鉱業権が必要とされます。
ソフトウェア
無形固定資産例の7つめは、ソフトウェアです。ソフトウェアは、コンピュータを働かせるためのプログラムのことです。
プログラムはさまざまなものが対象になり、将来の収益獲得や費用削減が確実であるという点が認められたものが無形固定資産の対象とされています。
ソフトウェアの取得価額や耐用年数は国税庁で定められており、購入した場合や自社製作の場合によっても異なるため注意しましょう。
のれん
無形固定資産例の8つめは、のれんです。のれんは、企業が買収や合併による費用の中で、買い取り先企業の純資産を上回った差額を指します。
たとえば、3,000万の価値を持つ資産を有する企業が、6,000万円で買収された場合、のれんは3,000万円で計上されます。買収先のブランド力や信用力などを含め、3,000万円の価値があると判断されます。
電話加入権
無形固定資産例の9つめは、電話加入権です。電話加入権は、固定電話(アナログ電話)の回線を利用できる権利です。
ただし電話加入権は、無形固定資産に該当するものの、経年劣化するものではないため、減価償却資産には該当せず、経費に計上できません。
特別な事情によって価値が下落した場合は評価損を計上できる可能性もありますが、電話加入権自体の価値が下落することはないため、評価損の計上も難しいと認識しておきましょう。
人的資本
忘れてはならない無形固定資産の一つとして、人的資本も挙げられるでしょう。
近年では、企業における非財務情報の中でも特に人的資本への注目や重要度が高まっています。株主や投資家などのステークホルダーが、企業価値や企業の将来性を判断する際には、人的資本がより大切な無形固定資産として捉えられているのでしょう。
人的資本とは、従業員が持つスキルや知識、ノウハウなどのことです。人的資本もほかの無形固定資産と同様に経年劣化すると考えられています。
高齢による病気や技術の衰えがその理由ですが、反対に教育の効果や経験によって年齢を重ねると価値が高まる側面もあるため、減価償却の適用が難しく、現在のところ定まった方法がないようです。
参照:『人的資本の測定に関する指針 (仮訳) 』国 際 連 合 (2016年)
有形固定資産の例
有形固定資産は物理的な形態を持つものですが、どこからどこまでが資産として該当するのかわかりにくいと感じる方もいるかもしれません。代表的な有形固定資産の例をご紹介します。
土地
有形固定資産の例の1つめは、土地です。
土地には、オフィスや店舗、駐車場、社宅敷地などが該当します。企業が保有する土地の中でも販売する不動産などは販売目的であるため、有形固定資産には該当しません。
事業用ではなく、あくまでも会社が長期で保有し、当面現金化する予定のない土地を指します。
建物および付属設備
有形固定資産例の2つめは、建物および付属設備です。
事務所用や店舗用の建物が含まれます。付属設備は、電気やガス、冷暖房設備などが該当します。有形固定資産の中で、建物および付属設備は「定額法」で計上する点が特徴です。
構築物
有形固定資産例の3つめは、構築物です。
構築物とは、トンネルや用水池、防波堤や上下水道などが該当します。建物と同様に、有形固定資産の中でも「定額法」で計上します。
機械および装置
有形固定資産例の4つめは、機械および装置です。
機械および装置は、製品などを製造するための工場などに設置される機械設備が該当します。また、機械式駐車場設備も含まれます。
車両および陸上運搬具
有形固定資産例の5つめは、車両および陸上運搬具です。自動車やオートバイ、台車やゴミ収集車などが該当します。
会社の資産は3種類

会社の資産は、会計学上の定義によって定められており、以下のように3つに分類されています。
| 固定資産 | 会社が長期保有を目的としたものや1年以内に現金化しない資産 |
|---|---|
| 流動資産 | 1年以内に現金化できる資産 |
| 繰延資産 (くりのべしさん) | 効果が将来にわたり効果が及ぶとして、税法上・会計上資産として計上すべき資産 |
固定資産
固定資産とは、会社が長期保有を目的とし、1年以内に現金化しない資産を指します。
固定資産は、形があるかないかによって、有形固定資産と無形固定資産に分類されます。経年劣化することで資産価値が減少する固定資産は減価償却が費用です。
流動資産
流動資産とは、通常1年以内に現金化できる資産を指します。流動資産は、次の3通りに分類されています。
| ・現金や預金などの当座資産 ・販売することで現金化できる商品や材料などの棚卸資産 ・短期貸付金や前払い金などのその他資産 |
増えたり減ったりするため、変動が大きい資産という特徴があります。
繰延資産
繰延資産とは、本来は費用として計上するものを資産として計上し、将来にわたって効果が及ぶことを見越して一時的に経費計上する資産を指します。
会社設立にかかる創立費や開業にかかる開業費、社債発行にかかる社債発行費や技術開発、市場開拓にかかる開発費用などが該当します。
会計学上における会社の資産は固定資産だけではありません。それぞれの分類もあわせて確認しておくことで、より理解が深まるでしょう。
固定資産の管理を行うポイント
固定資産の管理では、税務上の専門的な知識が必要になったり、ミスも発生しがちです。固定資産の管理を行ううえで押さえておきたいポイントをご紹介します。
経理から各現場へルールを周知する
固定資産や税務業務を行うのは、経理部門です。
しかし、固定資産を購入したり利用したりするのは企業の各部門の現場に分散されます。各現場から固定資産に関する連絡や報告がなければ実態を把握できないため、経理と現場の連携が重要なポイントです。
そこで、固定資産に関するルールを策定し、現場に理解してもらうことが大切です。
固定資産を購入したり廃棄したりした場合は、必ずすみやかに申請するなどのルールをつくり、現場へ抜け漏れのない周知を行いましょう。
システムを活用する
固定資産は、さまざまな情報を扱うため、手動で行うことでミスや抜け漏れなどのトラブルが発生してしまう可能性が少なくありません。
そこで、固定資産の管理はシステム上で行うのがよいでしょう。
固定資産管理システムは、企業が保有する固定資産の情報を正確に管理するためのシステムです。固定資産情報の管理や仕訳業務、申告業務などを効率化でき、管理の精度や生産性向上も期待できます。
膨大な業務を抱える経理担当者の負担を減らし、より正確でミスのない会計処理をスムーズに行うためにもシステム活用を検討してみましょう。
まとめ
無形固定資産は形としては認識できない資産であり、有形固定資産は形として認識できる資産です。
また、1年を超えて利用される資産であることが共通の定義です。無形固定資産も有形固定資産も、会社の売り上げをつくるために必要な重要な資産の一つといえるでしょう。
経費計上を適正に分配するためにも、固定資産の種類や減価償却方法、計算式、耐用年数などに関して理解しておかなければなりません。
本記事でご紹介した内容も参考にしながら、適切な処理や経費計上が行えるようにしましょう。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!












