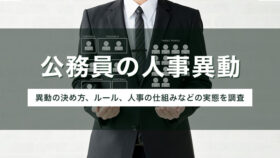- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
業務委託契約書とは? 記載内容や収入印紙の必要性ついても解説!
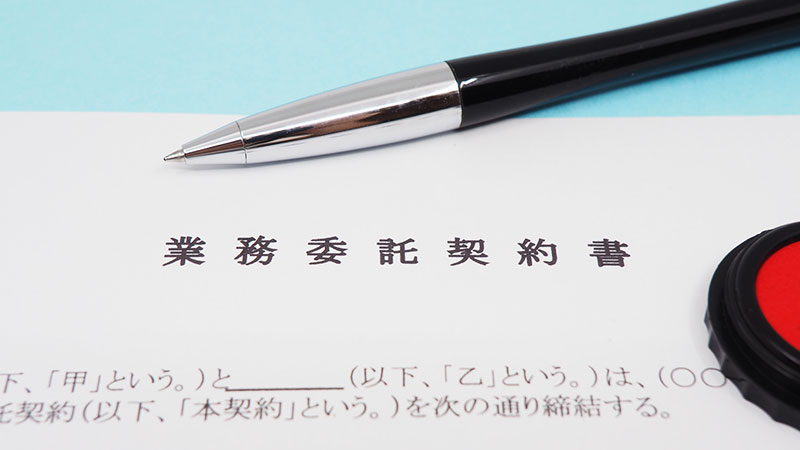
関連資料を無料でご利用いただけます
業務委託契約書とは、業務の一部を委託したり請け負う契約を締結する際に用いる契約書です。ビジネスを円滑に進めるために、企業や個人と業務委託契約を締結している企業は多いでしょう。
しかし、業務委託契約書には、契約の締結について報酬や契約内容など重要な内容が記載されるため、適切に作成されないとトラブルにつながりかねません。業務委託契約書の正しい作り方や記載項目が理解できていないという場合もあるでしょう。
そこで本記事は、業務委託契約書の基礎知識を解説しながら、記載項目や注意点もわかりやすくご紹介します。良好な業務委託契約を締結するためにも、適切で正しい業務委託契約書の書き方の理解にお役立てください。
※本記事記事の内容は作成日または更新日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。
目次(タップして開閉)
業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、業務委託契約を締結する際に、必要条件などを記載したものをいいます。書類作成後に委託者と受託者の双方が署名と捺印を行い、1部ずつ保管する流れが一般的です。
業務委託契約書の目的
業務委託契約書の目的は、業務や報酬の支払いに関する約束に関して証拠を残し、トラブルを避けるためです。業務委託契約自体は、委託者と受託者による合意があれば契約書がなくても成立します。
しかし、報酬や条件など重要な点について認識に相違があると、のちにトラブルに発展するケースもあるでしょう。そのため、契約内容を証拠として書面に残しておき、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
| 関連記事 人事労務のお役立ち情報 |
業務委託契約とは
そもそも業務委託契約とは、特定の業務や業務の一部を外部に委託することを指します。
業務委託契約という言葉自体は、法律上の用語ではありません。委託する業務の性質によって「請負契約型」「委任契約(準委任契約)型」「請負・準委任混合型」という類型に分類されます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
請負契約とは
業務委託における請負契約とは、受託者が「依頼された業務を完成させる」ことを約束し、委託者は「提出された成果物に対して報酬を支払うこと」を約束する契約です。
双方にとって、適切な成果物や報酬の支払いについて認識に違いがないよう、業務委託契約書の中で詳しい内容を決める必要があるでしょう。
委任契約(準委任契約)とは
業務委託における委任契約では、受託者は依頼された業務を遂行し、委託者は遂行された業務に対して報酬を支払います。
委任契約では、業務の進め方などについて、受託者の裁量に任されるのが一般的です。
また、委任契約と準委任契約の違いは、弁護士や司法書士などが行う「法律行為に関する業務」を委任契約とするのに対し「それ以外の事務処理業務」を準委任契約とします。
請負・準委任混合型とは
請負・準委任混合型とは、業務委託契約で請負契約と準委任契約が混在しているものを指します。
| 関連記事 労務管理の目的や仕事内容とは |
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約の違いとしては、契約を結ぶ双方に主従関係があるかどうか、労働関係の法律が適用されるかどうかの違いです。
業務委託契約では、双方に主従関係はなく、独立した対等の立場にあるといえます。そのため、労働関係の法律も適用されません。
一方の雇用契約は、雇用する側と労働する側として主従関係が成り立ちます。そのため、労働関係の法律が適用されます。
業務委託契約か雇用契約かを見極めるポイント
業務委託契約か雇用契約かを見極めるポイントとしては以下のような点が挙げられます。
| ・仕事の依頼や業務命令に対する拒否権の有無 ・業務内容や遂行方法に対して指揮命令の有無 ・労働時間や作業場所などに関する拘束の有無 ・通常業務以外の業務をする可能性の有無など |
業務委託契約は、委託者と受託者が対等な立場にあるため、命令を受けたり、拘束されることはありません。一方で雇用契約では、さまざまなシーンにおいて指揮命令を受けたり、拘束を受ける場合があるといえるでしょう。
業務委託契約の種類
業務委託契約の種類は多数ありますが、報酬の支払い方に注目しながら捉えると、よりわかりやすいでしょう。業務委託契約の一般的な種類についてピックアップしてご紹介します。
毎月定額の報酬を支払うもの【月額固定報酬型】
月額固定報酬型とは、業務の委託者が受託者に対して、毎月定額の報酬を支払う契約種類です。
継続的に業務を委託するものが多いといえるでしょう。このような業務委託契約の例としては、コンサルティング業務や保守点検業務、企業顧問などが挙げられます。
業務の成果により報酬が決まるもの【成果報酬・出来高払い型】
成果報酬・出来高払い型とは、受託者による業務の成果によって報酬が変動する契約種類です。
成果物の完成度や成果物の量によって支払う報酬額が決まります。このような業務委託契約の例としては、営業代行業務や店舗運営業務などが挙げられるでしょう。
しかし、あらかじめ規定した定義や計算方法によって報酬額が算出されることになるため、あいまいな表現ではなく、明確で納得感のある定義や計算方法を明記する必要があります。
単発の業務を委託するもの【単発・スポット報酬型】
単発・スポット報酬型とは、1回きりの業務を委託する場合に、あらかじめ報酬の支払い額を決めておく契約種類です。
このような業務委託契約の例としては、デザイン作成業務や社内研修業務、確定申告業務(税理士)などが挙げられるでしょう。
業務委託契約書の主な記載事項【作り方】
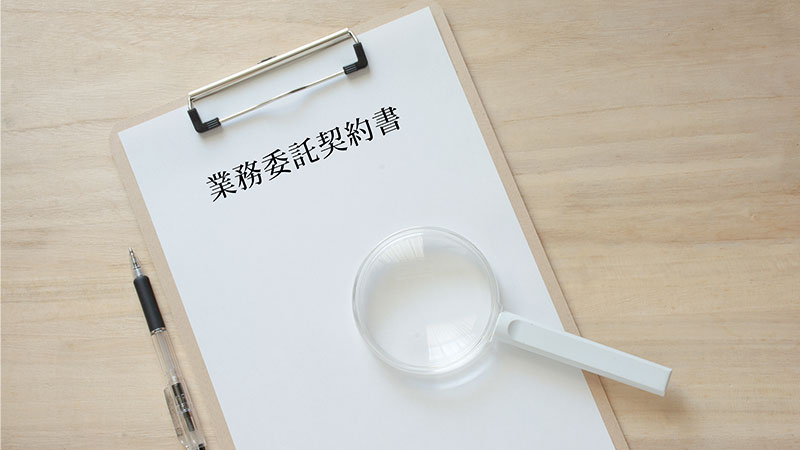
業務委託契約書において記載しておくべき一般的な事項をご紹介します。契約後にトラブルにならないためにも記載しておくべき点を確認しましょう。
業務委託契約の目的
業務委託契約について「受託者に業務の遂行を委託するための契約」という点を記載しておきましょう。
委託業務の内容
業務委託契約で委託する業務内容について記載します。委託する業務内容の詳細を具体的かつ明確に記載して、受託者が注意すべき点やルールなどがある場合にも記載しましょう。
報酬
業務委託契約で支払う報酬金額や支払い時期、支払い方法を明確にして記載します。どのように報酬が支払われるかという報酬の算定方法などの流れも明確にしておきましょう。
特に成果報酬型や出来高制の場合は、認識相違によるトラブルを防止するためにも双方が理解しやすいように定義や計算方法を記載することが重要です。
さらに、報酬がいつどのような形式で支払われるかを明記する必要があります。基本的にはあと払いが原則となりやすいですが、業務遂行上の必要性や事情によっては「前払い」にすることも可能です。
報酬の支払いを「前払い」にする場合は、業務委託契約書の報酬について明記する箇所などにあわせて記載しましょう。
参照:『民法第633条および第648条の2』e-GOV 法令検索
契約期間
業務委託契約の期間や契約期間満了にともなう更新について、記載します。
成果物の権利
業務委託契約の中で発生した著作権などの知的財産権が、委託者と受託者どちらに帰属するかを明確にして記載します。著作権を含めた知的財産権の帰属をあいまいにするとトラブルにつながることもあるため、必ず明記しましょう。
再委託
業務委託契約の中で、再委託が可能かどうかを記載しておきましょう。再委託とは、受託者自身ではなく第三者に委託することを指します。
業務委託契約において、実際の業務を行うのが受託者本人のみなのか、第三者でも問題ないのかなどを記載しておきましょう。
秘密保持
委託する業務について、情報の秘密保持が必要な場合に記載します。
特に個人情報や機密情報などを共有するような場合には、必ず明記しておきましょう。場合によっては、業務委託契約書だけでなく秘密保持契約書を作成する場合もあります。
反社会的勢力の排除
業務委託契約において、委託者と受託者のどちらかが反社会勢力に属する場合は、相手方が契約解除することが可能という点を明記しましょう。
禁止事項
業務委託契約の中で、受託者に対して禁止すべき内容がある場合は明確に記載しておきましょう。
契約解除
業務委託契約では、契約解除の詳細についても必要です。
契約違反や契約履行できないような場合など、一方的に契約解除を行う際の条件を記載しておきましょう。契約解除は損害賠償にもかかわり、大きなトラブルにつながりやすいため、明確に記載します。
損害賠償
業務委託契約の中で、委託者や受託者それぞれに契約違反が起こった場合の損害賠償責任や金額を明記しておきましょう。
著作者人格権の不行使
業務委託契約の中でも、著作物の作成を委託する場合、著作権とは別に「著作者人格権」についても記載しておくべき事項です。著作者人格権とは、著作者だけが持っている権利です。
委託者は、納品された著作物を受託者の了承がなくても修正するために、著作者人格権の行使をしない旨を記載しておきましょう。
管轄裁判所
業務委託契約において何かしらのトラブルで裁判に発展した場合、どこの裁判所で審理するのかを記載しておきましょう。
源泉徴収の取り扱い
業務委託契約書では、源泉徴収に関する記載もしておくと不要なトラブルを回避できます。
フリーランスで働く個人の場合、源泉徴収や税に関する知識が乏しいケースもあります。あらかじめ業務委託契約書にて明記し、いつでも確認可能な状態にしておくと安心です。
業務委託契約書で収入印紙は必要?
業務委託契約を作成する際は、契約内容によって収入印紙の要否が異なります。代表的な契約内容と収入印紙について確認してみましょう。
請負に関する契約書の場合
業務委託契約において、請負に関する契約書(2号文書)の場合は金額によって収入印紙代が異なります。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
継続的取引の基本となる契約書の場合
業務委託契約書が継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の場合、収入印紙は一律で4,000円です。契約期間が3か月を超え、かつ更新について定めがある場合に限ります。
参照:『No.7104 継続的取引の基本となる契約書』国税庁
請負契約にも継続的取引にも該当しない場合
業務委託契約が請負契約にも継続的取引にも該当しない委任契約の場合、収入印紙は不要です。
また、委任契約や請負契約、継続的取引にも該当しないような場合は国税庁のホームページなどで確認してみましょう。
参照:『No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断』国税庁
収入印紙はどちらが負担するのか?
収入印紙の負担について、印紙税法上では課税文書を作成した人に対して印紙税の納税義務が定められています。
業務委託契約では、双方の当事者2人以上が作成する文書であるため、このような場合は連帯して収入印紙の費用を負担します。そのため、保管する業務委託契約書の印紙をそれぞれ負担するのが一般的です。
ただし、契約において原本が1通のみで、コピーを用いて保管する場合には、原本を保管する側が収入印紙を負担する場合もあるかもしれません。
収入印紙についてのトラブルを避けるためにも、どのように負担するのかなどを事前に確認しておくとよいでしょう。
電子契約書の場合は収入印紙は不要
電子契約書を用いた契約書の場合、収入印紙は不要です。電子契約は、紙の印刷や物理的な書類の管理も不要であるため、電子契約書を活用している企業も多いでしょう。
ビジネスシーン全般において、電子化を進める企業が多くなっています。
書面での契約書を用いている場合は、印刷代や収入印紙代などのコスト削減にもなるため、電子契約書の導入を検討してみるのもよいでしょう。
業務委託契約と源泉徴収
業務委託契約を締結する場合、源泉徴収の仕組みを理解しておく必要があります。
源泉徴収税額に関するルールについては、国税庁のホームページで紹介されています。正しい情報を確認したうえで、理解を深めましょう。
参照:『税目別情報』国税庁
源泉徴収制度とは
源泉徴収制度とは、特定の所得について、給与や報酬を支払う際に所得税および復興特別所得税を差し引いて、給与や報酬を受け取る者に代わって納税する制度です。
| 源泉徴収の例と流れ | |
|---|---|
| 1 | A社がBさんの報酬に対して、本来Bさんが収めるべき所得税を差し引いた金額で支払う |
| 2 | A社は、本来Bさんが払うべき所得税(1で差し引いた所得税分の金額)をBさんの代わりに国へ納税する |
給与や報酬の支払いを行う者は「源泉徴収義務者」とされ、毎月給与や報酬を支払った月の翌月10日までに所得税を納税しなければならないとされています。
源泉徴収になる対象
企業が業務委託契約を個人と締結する場合、源泉徴収対象は以下のとおりです。
| 源泉徴収対象 | |
|---|---|
| 1 | 原稿料や講演料など |
| 2 | 弁護士や公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 |
| 3 | 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
| 4 | プロ野球選手やプロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金 |
| 5 | 映画や演劇、そのほか芸能(音楽や舞踊、漫才など)、テレビジョン放送などへの出演などの報酬・料金、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 |
| 6 | ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて、客に対して接待などを行うことを業務とする、いわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 |
| 7 | プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより、一時に支払う契約金 |
| 8 | 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 |
また、法人との業務委託契約の場合は、馬主である法人に対して競馬の賞金を支払う場合にのみ源泉徴収が適用されます。
源泉徴収税額の計算方法と消費税
源泉徴収税額を算出する際は、以下の方法で行います。
| 給与や報酬の支払い額 | 計算式と詳細 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 源泉徴収税額=支払い金額×10.21% (10.21%のうち、10%は所得税額、0.21%は復興特別所得税額) |
| 100万円を超える場合 | 源泉徴収税額=(支払い金額−100万円)×20.42%+102,100円 (20.42%のうち、20%は所得税額、0.42%は復興特別所得税額) |
また、消費税については原則として消費税込みの金額をもとにして計算します。
ただし業務委託契約を結んだ相手からの請求書などにおいて、報酬額と消費税額が明確に区分して記載されている場合は、消費税を含まずに報酬額のみを対象として税額を計算することもできます。
たとえば報酬額が30万円の場合、消費税は3万円です。
この場合、原則として33万円が源泉徴収税額の対象ですが、請求書に「報酬額」と「消費税額」を区別して記載すれば、報酬の30万円のみを源泉徴収税額の対象にできるということです。
業務委託契約書における押印
業務委託契約書では、印鑑を押す必要があります。契約書の内容などによって印を押す場所などが異なるため、注意が必要です。
| 種類 | 状況 |
|---|---|
| 捺印と押印 | 契約書の内容に同意する意思を示す |
| 消印 | 印紙税を納税したことを証明する |
| 契印 | 契約書が2ページ以上になる |
| 割印 | 控えを含み2部以上になる |
| 訂正印 | 訂正箇所がある |
| 捨印 | 将来の契約書の訂正対策を示す |
| 止印 | 文書の終わりを示す |
すべての契約書で必須ではないものの、場合によって押印の必要があるケースについ手も含めて押印の種類をご紹介します。
捺印と押印
契約書の内容に同意したことを証明する印を押す必要があります。
契約する本人の名前を書いたあと、末尾にあたる場所に押印します。直筆署名のあとに印を押すのが「署名捺印」、直筆署名以外の方法で記された名前のあとに印を押すのを「記名押印」といいます。
業務委託契約書の場合、甲乙双方が捺印、押印を行います。
消印
また、文書の種類によっては印紙税を収める必要がある場合もあります。印紙税を納める必要がある文書では、収入印紙を用います。
収入印紙は、文書に貼付したうえで、収入印紙と文書それぞれにまたがって印を押します。これを「消印」といいます。収入印紙に消印が押されていないと、印紙税を納付したと見なされないため、注意しなければなりません。
消印の種類はどのようなものでも問題ありませんが、契約の当事者(1人)が押印すること、2通以上になる場合はそれぞれ収入印紙を添付する必要があるという点を理解しておきましょう。
契印
契印は、契約書が2ページ以上になる場合に押す印です。署名捺印と見開きの場所に、契約者全員の印鑑を見開き部分(すべて)にまたがるように押印します。
契印について、情報が多い契約書の場合、すべての見開き部分に全員の契印を押すのは大変であるため「製本」したうえで契印すると効率的です。
製本する場合は契約書全体をホチキスでまとめ、その上からテープで袋閉じを行います。テープ部分と契約書の紙面のまたがる部分に、当事者双方の契印を押せば「契印」として認められます。
割印
割印は、控えを含み2部以上になる場合に押す印です。契約書を重ね、またがるように契約者全員が押印(契約書上部に押印)するのが一般的とされています。
訂正印
訂正印は、書面の中で訂正したい箇所がある場合に押す印です。
箇所を二重線で消し加筆修正、契約者全員が押印します。契約書欄外(書類右上など)に訂正箇所と文字数を記載する必要があります。
捨印
捨印とは、契約書において将来訂正をスムーズに行うために押す印です。
契約書上部の余白に、あらかじめ予備の印として全員が押印します。捨印は、書類を訂正する際に使用でき、重要な内容が変えられるリスクもあるため注意しましょう。
止印
止印とは、契約書の文書の終わりを示すために押す印です。
文書の終わり部分の余白が大きいと、文書に勝手に加筆されるかもしれません。そのような改ざんを防ぐために、契約書の文末に押印します。
ただし、押印でなく「(以下、余白)」という記載でも対応できます。
契約書で使う印鑑の種類
印鑑にはさまざまな種類があり、状況に応じて押すべき印鑑の種類も異なります。契約締結で用いられる主な印鑑の種類は以下の通りです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 実印 | 印鑑登録されている印鑑 |
| 認印 | 印鑑登録されていない印鑑 |
| 銀行印 | 銀行に届け出をしている印鑑 |
| 社印(角印) | 法人名のみの印鑑 |
| 代表者印 | 法人名+代表取締役印などが彫られている印鑑 |
実印
実印とは、印鑑登録されている印鑑のことを指します。
実印は、公的に認められた印鑑であり信頼性が高い印鑑として用いられます。そのため、高額な金銭のやり取りが行われるような契約書などで使用されます。
認印
認印とは、印鑑登録されていない印鑑のことを指します。
実印が公的に認められた印鑑として重要な契約書などに用いられる一方で、一般的な契約書においては認印を用いるケースが多いでしょう。
銀行印
銀行印とは、銀行に届け出を行った印鑑のことを指します。
銀行口座を開設するためには、この届出印が必要なため、銀行口座を持つすべての人や法人が銀行印を保有しているということです。
銀行印自体は、実印でも認印でもどちらを登録することもできます。
社印(角印)
社印とは、印鑑登録されていない法人の印鑑のことを指します。
社印は印鑑が四角いため、角印とも呼ばれます。社印は一般的な認印と同様で、見積書や請求書など、契約書以外の書面などに用いられることが多いでしょう。
代表社印
代表社員とは、法人名だけでなく「代表取締役印」などと彫られている法人代表者の印鑑のことを指します。代表社員は、法人の代表者が同意していることを示す印鑑であるため、重要な契約書を締結する際などに用いられます。
業務委託で外国人と契約する場合
業務委託契約では、外国人と契約するケースもあるでしょう。外国と業務委託契約を締結する場合、就労ビザについて疑問を抱く場合も少なくありません。
そこで、外国人との業務委託契約を締結する場合に理解しておくべきポイントを解説します。
業務委託契約でも就労ビザの申請が必要
外国人が働けるのは就労ビザ(就労系の在留資格)の範囲内であり、就労ビザの取得には一定の審査基準があり、自由に取得できるわけではありません。
外国人と企業が業務委託契約を締結する場合も、通常の社員を雇用するのと同様に就労ビザの申請が必要です。
また、就労ビザの申請は、契約を締結する企業の中でもっとも高い報酬を支払う企業が代表して申請手続きを行う必要があります。
そのため、契約する外国人が複数の企業と業務委託契約を結んでいるのかを確認したうえで、契約状況もあわせて確認しましょう。
就労ビザの注意点
就労ビザを申請するうえで注意すべき点は、
| ・契約内容が労働法を遵守している ・長期的な契約内容である ・税金や年金、社会保険は委託先(外国人本人)に行ってもらう |
です。
就労ビザの申請では、業務委託契約書の添付が必要であり、ここで業務委託契約の内容に問題がある場合、就労ビザの許可がもらえない場合があります。
契約書に記載すべき内容を確認して抜け漏れがないかどうかを確認しましょう。
契約期間について、短期間の業務委託契約では契約期間が終了した途端に無職になってしまう可能性もあります。短期間で無職になる可能性がある場合、就労ビザの許可は下りにくくなってしまいます。
そのため、外国人と業務委託契約を締結したい場合は長期的な契約として締結するとよいでしょう。
しかし、短期間の契約であっても、大きな問題がない場合は基本的に更新されるということがわかる内容であれば、許可が下りる可能性もあります。
また、外国人と業務委託契約を締結する場合でも、確定申告や社会保険などの支払いは、本人が行わなければなりません。
業務委託契約を締結する際に、相手方に納税や確定申告は自分で行う必要があるという点を明確にして説明するようにしましょう。
業務委託契約書に関するQ&A
業務委託契約書に関してよくあるQ&Aをご紹介します。
業務委託契約書をつくる目的は何ですか?
業務委託契約を結ぶにあたり、トラブルを防止するためです。
契約内容に認識相違があったり契約違反に該当する場合なども、業務委託契約書を根拠にすればトラブルを防止できるでしょう。
業務委託契約書は書面じゃないとだめですか?
業務委託契約書の作成は、書面に限らず電子データによる作成でも問題ありません。
印紙税も不要になり、保管コストや書面管理も効率化できるためおすすめです。ただし、契約を結ぶ双方の合意が必要なので、相手方に確認してみましょう。
業務委託契約書に割印は必要ですか?
業務委託契約書について、割印は契約書の改ざん防止に有効です。
契約書の効力としては影響しませんが、契約書が複数ある際は書面の差し替えを防ぐ効果があります。ただし割印を押す場合は、委託者と受託者双方の押印が必要になる点を理解しておきましょう。
まとめ
業務委託契約書を作成する場合は、一般的に記載すべき項目を理解したうえで内容を踏まえて不足のない契約書になるように作成したいところです。
業務委託契約書への記載が不足していたり、あいまいな表現になっていることで、契約後のトラブルにつながることもゼロではありません。委託者側も受託者側も双方がしっかり確認したうえで、不明点や認識相違がない状態で署名を行うようにしましょう。
また、業務委託契約書は、書面の契約書だけでなく電子契約書を用いる企業も多くなっています。
電子契約書を用いることでコスト削減や管理業務の効率化にもつながるため、書面での契約書を運用している場合は、ぜひ検討してみましょう。
| 無料でお役立ち資料をダウンロード 【人事のお役立ち資料】明日からの業務のヒントに! |

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!