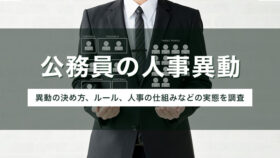- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
労働災害(労災)とは? 種類別の認定条件と事例、発生状況を紹介

労働災害とは、業務や通勤が原因で労働者がケガをしたり病気にかかったりすること。労働災害の防止に努めることは企業の義務であり、法律にも明記されています。
業務上の事故だけでなく、ハラスメントや過重労働による心身の不調も労働災害と見なされる可能性があるため、より一層注意が必要です。
しかし、どのような案件が労働災害と判断されるのか、またその後の対応について、不安を抱える企業も多いかもしれません。
そこで本記事は、労働災害の種類や認定基準、事例、実態を解説します。労働災害が起きてしまった場合の適切な対応方法もご紹介するので、企業の担当者はぜひ参考にしてみてください。
目次(タップして開閉)
労働災害とは|基礎を解説
労働災害とは、業務に起因して従業員が負う病気やケガ、死亡事故のことを指します。業務中に起こるケガだけでなく、通勤中の交通事故や長時間労働が原因とされる過労死、業務上のパワハラが原因とされる精神疾患なども労働災害に含まれます。
労働災害の対象となるのは、原則として企業が雇用するすべての従業員です。雇用形態や国籍は問われません。正社員や契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイム労働者が該当します。
労働災害が多い月
厚生労働省が発表した令和3年の発生状況によると、死亡災害は7月が94件でもっとも多く、11月が59件でもっとも少ないです。
死傷災害においては、1月が16,043件でもっとも多く、11月が10,621件で年間でもっとも少なく報告されています。年間を通して、発生件数に大きな差はないことがわかります。
労働災害の【種類別】認定基準
労働災害の認定基準にはどのようなものがあるのでしょうか。労働災害と認められる基準を種類別に解説します。
業務災害の認定基準
労働災害のうち業務災害と判断されるには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性
業務遂行性とは、事故が業務中に起こったか否かという認定基準です。事業場で従業員がけがなどを負った場合や、事業主の支配下において業務を行っていた場合に認められる可能性があります。
業務起因性
業務起因性とは、従業員が負ったけがや病気などの原因が、仕事にあるか否かという認定基準です。
就業中に発生した事故だけでなく、就業前後や休憩中に起きた労働災害でも業務に関連していたり、社内設備の不備によって発生したりする災害において、認められる可能性があります。
| 業務災害が認められる例 |
|---|
| ・月100時間労働によるうつ病の発症 ・作業中の爆発事故 ・社内の椅子が壊れたことによる負傷 |
通勤災害の認定基準
労働災害のうち通勤災害は、就業にかかわる移動中に発生し、業務との関連性が認められる場合に該当します。
「就業にかかわる移動中」とは、従業員の住居と職場との往復だけでなく、就業場所から別の就業場所への移動や、単身赴任先から帰省先への往復も含まれます。
| 通勤災害が認められる例 |
|---|
| ・通勤中に駅の階段から転落してけがを負った ・職場から取引先に出張に出かけた際に事故に遭った ・通勤中に業務に必要なものを自宅に忘れたことに気づき、取りに帰っている途中に事故に遭った |
第三者行為災害の認定基準
第三者行為災害とは、モノではなく人が原因で業務災害や通勤災害が引き起こされた場合を指します。
たとえば、通勤中に車にはねられたり、同僚の操作ミスによってけがを負ったときに認められるでしょう。
第三者行為災害に認定されると、被災者は労災保険の給付を請求できると同時に、加害者に対し損害賠償請求権を取得できます。
参照:『業務災害・通勤災害について』厚生労働省
参照:『第三者行為災害のしおり』厚生労働省
| 関連記事 健康経営の取り組み事例7選 |
労働災害の有名な事例
ここまで労働災害の種類とその認定基準について解説してきました。次に実際に労働災害として認められた具体的な事例をご紹介します。
プレス機械とフォークリフトの間に挟まれ死亡
金属製品製造会社で、金型の交換を行っていたときに発生した労働災害です。
従業員がフォークリフトのフォークに金型(270kg)を載せた状態で、フォークリフトをプレス機械に向けて停止させました。そのあと運転席から降り、プレス機械とフォークリフトとの間に立ち入ったところ、フォークリフトがプレス機械に向けて動き出してしまい、従業員は腹部を挟まれて死亡しました。
主な原因として、従業員が運転席を離れる際に、フォークリフトのエンジンを停止させなかったことなどが挙げられます。
飲食店の厨房で一酸化炭素中毒
換気が不十分なファーストフード店の厨房で、従業員3人が一酸化炭素中毒になり、救急搬送された労働災害です。
この店は当時、厨房の換気設備が故障していたため、扇風機のみ設置し、プロパンガス器具計3基を稼働させて営業を続けていました。しばらくして従業員3名が「気分が悪い」と訴えて救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断を受けた事例です。
主な原因として、換気設備の故障を修理せずに放置したこと、一酸化炭素中毒の予兆があったにもかかわらず営業を続けたこと、ガス警報装置を設置していなかったことなどが挙げられます。
道路改修工事中に熱中症を発症
屋外道路改修工事中に、作業者が熱中症を発症し死亡してしまった労働災害の事例です。
8月の炎天下、コンクリート破片をトラックに積み込む作業の途中で従業員がフラフラしているところをほかの従業員が発見しました。すぐに車庫で休息をとらせたものの、回復する様子がなかったため車で病院に送り届けましたが、その後死亡が確認されたのです。
主な原因として、適切な間隔で休憩をとらなかったことや、日照りの強い場所で作業を行っていたことなどが挙げられます。
労働災害の発生状況
ここでは、令和4年の労働災害の発生状況を発生種別ごとにご紹介します。
死亡災害の発生状況
厚生労働省が発表した令和5年3月の速報値によると、令和4年の労働災害による死亡人数は758人で、令和3年同時期の831人から減少しました。
業種別に見ると、死亡者数が最も多いのが建設業(273人)、次いで第三次産業(198人)、製造業(136人)と続いています。
事故の発生状況を割合で見ると、墜落・転落が約30%と最も多く、交通事故(道路)が約16%、はさまれ・巻き込まれが約14%と報告されています。
休業4日以上の死傷災害の発生状況
同じ令和5年3月発表の速報値によると、令和4年において労働災害により4日以上休業した人数は、約27.5万人で、前年同期比87.8%上昇しています。
これは、新型コロナウイルスの感染者が含まれる「その他」の事故が増加したことが原因と考えられるでしょう。
休業4日以上の死傷災害の発生状況の割合は、新型コロナウイルス感染を含めた「その他」の労働災害が約54%と半数以上を占め、転倒が約13%、墜落・転落が約7%と続いています。
参照:『令和4年における労働災害発生状況について(令和5年3月速報値)』厚生労働省
労働災害における企業の義務と発生時の責任
労働災害が起きることのないように、企業は従業員に対して安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、労働契約法第5条により定められている、使用者に課された義務のこと。企業は事前に労働災害を予見・予防し、従業員が安心して働けるように生命、身体、健康に対する危険防止に努めなければなりません。
(労働者の安全への配慮)
引用:『労働契約法第5条』厚生労働省
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
安全配慮義務を怠ったことで労働災害が発生したら、企業は損害賠償責任を負うことになる可能性があります。
5つの責任
従業員の病気やケガが労働災害として認められると、企業には以下の5つの責任が発生します。
| ・刑事上の責任 ・民事上の責任 ・行政上の責任 ・補償上の責任 ・社会的な責任 |
刑事上の責任
危険防止注意業務を怠って従業員を死亡させたり、けがを負わせたりした場合、業務上過失致死傷罪や労働安全衛生法違反に問われる可能性があります。
民事上の責任
労働災害で被災した従業員または遺族から、不法行為責任や安全配慮義務違反で、損害賠償を請求されるかもしれません。
行政上の責任
機械設備の使用停止や作業停止など、行政処分や行政指導を受けることがあります。
補償上の責任
被災した従業員の治療や従業員とその家族の生活を保護する責任があります。労働基準法や労働者災害補償保険法によって、治療と生活補償を目的とする補償が義務づけられています。
社会的な責任
上記4つの責任を負った企業は、世間から責任を追求されたり、批判されたりすることで、信用を失う恐れがあります。
労働災害発生時に求められる対応
労働災害が発生してしまったときに企業は、どのような対応を取ればよいのでしょうか。
労働災害発生時に企業に求められる一般的な対応について、順を追って流れを解説します。
| 1.被災者の救護・現場の対応 2.災害状況の確認 3.労災保険の手続き(病院と労働基準監督署に報告) 4.再発防止に向けた対策 |
1.被災者の救護・搬送、現場の対応
労働災害が発生したらまず、被災した従業員を病院に搬送するなどの救護が最優先です。
二次災害が起きる可能性があるならほかの従業員を避難させ、大規模な事故なら警察や消防への応援要請が必要となるかもしれません。
そのあと、被災者の家族や労働基準監督署へ連絡するなどの対応をしましょう。
2.災害状況の確認、原因の調査
次に事故が発生した直後は、現場にいた関係者から事故の状況や原因などを聞き取って、災害の情報を収集します。事故の発生状況などは、労災申請書類を作成する際や労働災害の認定を受ける際に必要となるため、できるだけ正確に素早く正確に聞き取りましょう。
3.労災保険の手続き
災害の発生状況を正確に把握して、労働災害が認められるのであれば、労災保険の手続きに入ります。労災手続きに必要な書類は、病院に提出するものと、労働基準監督署に提出するものの2つがあります。
病院に提出する書類
病院に提出する書類は、業務災害と通勤災害ともに、利用する医療機関によって様式が異なります。
労災保険指定医療機関を利用した場合は、『療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)』、労災保険指定医療機関以外は『療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)』を提出します。
これらの用紙は、労働基準監督署で受け取るか厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
労働基準監督署に提出する書類
労働基準監督署に提出する書類は、労働災害による休業日数が4日以上の場合は『様式第23号(労働者死傷病報告)』を、休業日数が1〜3日の場合は『様式第24号(労働者死傷病報告)』を提出します。
様式23号は労災発生後速やかに提出します。様式24号は四半期に1度まとめて提出することになります。
参照:『労働者死傷病報告(休業4日以上)様式』厚生労働省
参照:『労働者死傷病報告の提出はお済みですか?』厚生労働省
4.再発防止に向けた対策
同じような労働災害を発生させないように、手続きが完了したら原因の分析と再発に向けた対策を立てましょう。『再発防止対策書』の作成と提出が必要なケースもあります。また、労災専門の窓口がある弁護士に相談し、予防策を打っている企業もあるようです。
労働災害の発生原因と防止策
労働災害の発生を未然に防ぐために、事業主は労働災害の発生原因を知っておく必要があるでしょう。
ここでは労働災害が発生する主な原因と、その防止策についてご紹介します。
労働災害の発生原因
労働災害が発生する原因には、主に「不安全行動」「業務上疫病」「メンタルヘルスの不調」の3つがあります。
「不安全行動」とは、従業員自身やほかの従業員に危険を引き起こす可能性がある行動を指します。
「業務上疫病」は、特定の業務に従事する従業員が発病しやすい疫病や障がいです。たとえば屋外での作業による熱中症や、木材などの粉塵によって引き起こされる呼吸器疾患が挙げられるでしょう。
「メンタルヘルスの不調」は、長時間労働やパワーハラスメントなどが原因となって発生する場合が多いです。従業員の退職や休職だけでなく、ほかの従業員への負担増大を招くため、配慮が求められるでしょう。
労働災害の防止策
労働災害の防止策の一つとして、企業には安全衛生教育を実施することが法律で義務づけられています。従業員を新たに雇い入れたときや、作業内容が変更されたときは指導が必要でしょう。
しかし、これは最低限の防止策であり、労働災害を防止するためには現場に即した教育が必要といえるでしょう。
具体的には、
| ・危険予知活動(KY活動)による業務上のリスク洗い出し ・防止策の実施 ・リスクアセスメントによるリスク低減策の考案と実施 ・従業員のメンタルヘルスケア(医師や保健師による定期的な面談の実施) |
などが効果的と考えられています。
参照:『第13次労働災害防止計画(2018年度~2022年度)』厚生労働省
労働災害と労災保険
最後に労働災害に関連した内容として、人事労務担当者が知っておきたい労災保険の概要と加入条件、補償給付の種類について解説します。
労災保険とは
労災保険とは、労働災害が発生した際に、従業員や遺族が被った損害を保証するために行う保険給付制度です。
労災保険への加入条件
従業員を1人でも雇っている企業は、労災保険に加入して保険料を納めなければなりません。労災保険は雇用保険のように、従業員の労働時間によって加入条件が変わらない公的保険です。
企業の担当者は、保険関係が成立した翌日から10日以内に『保険関係成立届』を、50日以内に『概算保険料申告書』や会社の登記簿謄本を、所轄の労働基準監督署などに提出する必要があります。
労災保険の補償給付の種類
労災保険には、災害の発生状況に応じて7つの補償があり、種類によって、給付条件や補償内容が異なります。
| 種類 | 給付条件 | 補償内容 |
|---|---|---|
| 療養給付/療養補償給付 | 業務や通勤が原因でケガや疾病にかかり、療養が必要となった場合 | 療養(現物)給付 療養費用の給付 |
| 休業給付/休業補償給付 | 業務や通勤が原因で働けなくなり、賃金を受けられない場合 | 所得の補償 ※休業4日目から支給 |
| 傷病年金/傷病補償年金 | 療養(補償)給付を受けてから1年6か月経過しても治っておらず、障害状態にある場合 | 傷病等年金 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金 ※傷病の程度に応じた等級による |
| 障害給付/障害補償給付 | 療養して治ったあと、一定の障害状態にある場合 | 1級から7級は障害補償年金 8級から14級は障害補償一時金 ※傷病の程度に応じた等級による |
| 遺族補償給付 | 業務や通勤が原因で労働者が亡くなった場合 ※遺族へ支給 | 遺族補償年金 ※1回限り前払い可能 ※受給資格者を満たさない場合は遺族補償一時金を支給 |
| 葬祭給付/葬祭料 | 業務や通勤が原因で労働者が亡くなり、葬儀を執り行う場合 ※被災労働者の埋葬を行うにふさわしい遺族へ支給 | 葬祭給付/葬祭料 ※請求期限は死亡から2年以内 |
| 介護給付/介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金をの受給者で、第1級のすべてと第2級の精神神経と胸腹部臓器の障害を持ち、現在介護されている場合 | 介護給付/介護補償給付 複数事業労働者介護給付 ※常時介護と随時介護で金額が変わる ※特定の施設やホームの入居者は除く |
また、労働災害の予防事業の一環として、二次健康診断等給付という制度も用意されています。二次健康診断等給付とは、定期健康診断後の再検査(=二次健康診断)や特定疾患を予防するための保健指導を年度内に一度、無料で受診できる制度です。
労働災害についての知識を深めておくことが必要
企業は労働災害の発生を未然に防ぐため、従業員への教育やリスクの洗い出し、防止策の実施を行うことが必要です。
万一、労働災害が発生してしまった場合、企業は適切な対応を取ることが求められます。適切な対応を怠ると、企業の信用が損なわれる可能性があるでしょう。
従業員の安全や企業の信用を担保するためにも、労働災害が発生した場合に備え、適切な対応方法についての知識を深めておくことをおすすめします。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!