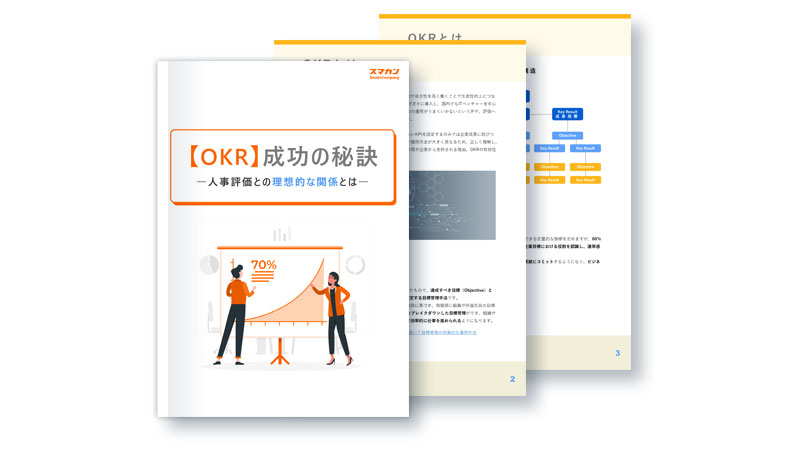- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
人事評価に甘辛調整は必要? 評価の偏りを平均値に調整して、納得感を高めるには?
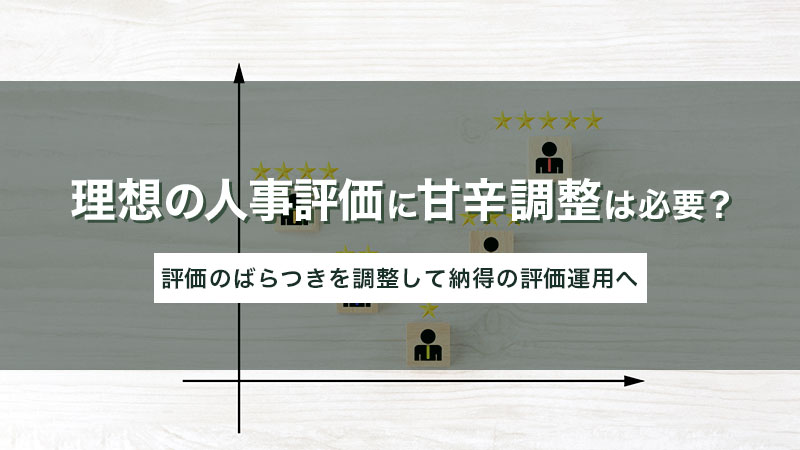
関連資料を無料でご利用いただけます
人事評価では、評価者によって偏りやばらつきが発生することがあります。こうしたばらつきを是正するのが甘辛調整です。当記事では、人事評価の課題を踏まえたうえで、甘辛調整の運用方法について解説します。
目次(タップして開閉)
人事評価における甘辛調整とは
人事評価では評価者によって「厳しすぎる」「甘すぎる」といった偏りが発生することがあります。評価者の評価スキルや部署ごとの評価基準に差があることが1つの原因です。このような評価のばらつきを事後的に調整して、評価の公平性や被評価者の納得感を担保するのが甘辛調整です。
もっとも、多くの企業では、事後的に甘辛調整を行う場合でも、事前調整をしっかりと行っています。事前調整では評価者研修を実施するなどして、評価のばらつきをあらかじめ防ぐようにしています。そのため、以下のような内容を検討して明確化する必要があります。
| ・業績評価、能力評価、情意評価の各項目をどう設定するか? ・絶対評価と相対評価のどちらを採用するか? ・誰を評価者とするか? ・評価を待遇や処遇にどう連動させるか? |
人事評価の課題
人事評価では、従業員の能力や働きぶりが評価され、待遇・処遇に反映されます。人材育成や企業の成長促進を主な目的として運用される制度です。近年は、MBOやOKRといった目標管理制度、コンピテンシー評価、360度評価、1on1ミーティングなどの手法を評価に取り入れる企業が増えています。
一方、評価される従業員が評価に対して納得していないことも少なくありません。人事評価への不平不満の原因は、以下で紹介する4つが代表的です。
評価基準が整備されていない
企業によっては、人事評価の基準が定められていなかったり、従業員に公開されていなかったりします。このように評価基準が不明確だと、従業員は自分の評価の理由を把握できずに納得できません。
また、今後どのように行動をすればよいのかもわからないため、評価結果を業務に活かすのも難しいでしょう。目標を定めたり、改善策を考えたりすることにも支障をきたします。
低い評価結果だけを伝えられた従業員は、同じ業務に従事するほかの従業員と自分を比較し、不公平な扱いを受けていると感じるかもしれません。その結果、不信感を募らせて、モチベーションやエンゲージメントが低下することもあるでしょう。
評価制度に慣れていない
評価制度に慣れていない評価者は適切な評価を行えない可能性があります。とくに、従来とは異なる評価制度を導入した直後にこの問題が生じがちです。組織全体で目的を共有できていなかったり、特定の従業員に業務が集中したりするのが原因です。
こうした状況を防ぐため、評価者のスキルアップを目指して研修などが実施されますが、限界があります。人事評価プロセスも事前に効率化しておかないと、評価者は評価シートや目標管理シートなどの膨大な資料の管理に追われます。結果として、本来の業務にまで手が回らなくなる可能性もあります。
評価者の能力や資質によって差が出る
評価者の能力や資質によって評価に差が出るのはよくあることです。それまでの経験にもとづいた価値観や好悪の感情などが評価に反映される傾向もあります。
人が人を評価する以上、主観が評価に入り込むのを完全に防ぐのは不可能でしょう。しかし、不公平な評価を放置すると、被評価者の不平不満が大きくなります。その結果、スキルやパフォーマンスに優れた従業員が離職すれば、欠員補充のための人事異動や人材採用などで余計なコストが生じたり、また離職率が上がることで会社の評価に関わるなど、結果として企業に損失が生じます。
評価にばらつきが発生する
ここまでで紹介してきた要因によって、人事評価にはしばしば偏りやばらつきが発生します。極端な事例としては、同じ仕事をしていたにもかかわらず、上司が変わった途端に評価が大きく変わることもあります。人事異動によって部署が変われば、上司だけでなく業務内容も変わるので、それまでの評価が引き継がれるとは限りません。
評価のばらつきを是正するため、外部の専門家によるコンサルティングを依頼することもあるでしょう。しかし、外部の専門家が企業内の実情を的確に把握し、誰もが納得する評価方法を指導して改善を促すのは容易ではありません。そのため、管理職などの評価者が情報交換し、客観性と公平性を担保する場として、評価会議を開催している企業もあります。
評価のフィードバックが行われない
人事評価のフィードバックが行われないと、被評価者の不平不満が大きくなる傾向があります。評価結果だけを伝えられた従業員は、自分の良かった点や悪かった点がわからなくて納得できないからです。また、改善につなげるためのフィードバックがなければ、人材育成の手段として人事評価を活用できません。
一方で、評価のばらつきが解消されない限り、フィードバックを適切に行うのは難しいでしょう。上司が変わった途端にアドバイスの内容が大きく変わってしまっては、従業員も混乱するだけです。評価者の間でフィードバックの目的を共有し、評価基準を明確にすることが求められます。
人事評価において甘辛調整が行われている理由
人事評価における評価のばらつきを是正するために甘辛調整が行われます。しかし、甘辛調整は現場を知らない人事担当者が事後的に評価を操作するため、このことに対する批判もあります。そもそも甘辛調整をしなくて済むように、評価者研修などを充実させて事前に対策をするべきだという主張もあります。
人事評価による待遇・処遇に大きな差がなく、多少の不公平感があっても最終的に妥当な人事を実現できる企業ならば、甘辛調整は必要ないでしょう。しかし、実際は人事評価が待遇・処遇に影響するため、評価によって従業員のモチベーションやエンゲージメントが大きく左右されます。評価に納得できない従業員は生産性が低下し、場合によっては離職につながります。
このようなトラブルを防止するため、多くの企業では甘辛調整が実施されています。評価のばらつきを放置することは決して好ましいことではありません。
人事評価における甘辛調整の手法
甘辛調整の代表的な4つの手法を紹介します。どの手法にも一長一短があるため、企業の方針と現状に合致したものを採用するとよいでしょう。
部門平均点による調整
部門ごとの平均点を全社平均点に合わせることでそれぞれの評価点を調整します。
たとえば、営業部の平均点が70点で、全社平均点が65点だとします。この場合、営業部の従業員に対する評価は全体と比較して5点甘いといえます。そのため、営業部のそれぞれの被評価者の評価点を5点ずつ減点します。営業部の田中さんが調整前の点数が85点だとすると、調整後は80点になります。
<甘辛調整前>
| 【営業部】被評価者 | 鈴木 | 佐藤 | 田中 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 点数 | 75点 | 50点 | 85点 | 70点 |
<甘辛調整後>
| 【営業部】被評価者 | 鈴木 | 佐藤 | 田中 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 点数 | 70点 | 45点 | 80点 | 65点 |
部門平均点による調整には、計算が簡単でわかりやすいというメリットがあります。一方、デメリットとしては、部門に被評価者が1人しかいない場合、その1人の点数が何点であろうと全社平均点になってしまいます。また、平均点付近に点数が集中している場合や、点数差が極端な場合、調整が機能しないこともあります。
正規分布による調整
正規分布は、それぞれの評価の割合をバランスよく調整するのに利用されます。
たとえば、SABCDの5段階評価を採用する場合、Sは5%、Aは15%、Bは60%、Cは15%、Dは5%というように事前に割合を決めておきます。絶対評価で鈴木さんに75点、佐藤さんに50点などと点数をつけたあと、相対評価によって被評価者それぞれをSABCDに割り振っていきます。
正規分布による調整には、評価がバランスよくばらけるというメリットがあります。一方、事前に決めた評価の割合が合理的であるとは限らないのがデメリットです。従業員の能力や働きぶりが、きれいな正規分布になるという保証はありません。
標準比較による調整
標準となる評価を受けている従業員(標準者)との比較によってばらつきを調整する方法もあります。
それぞれの部門から3〜4人を選び、その評価を基準となる標準者の評価と比較します。甘辛の度合いについて問題がなければ、その部門の評価を修正せずに採用します。問題があると判断される場合には、その部門全体の評価を上下に修正して調整します。
標準比較による調整には、実在する従業員が基準となるので、比較が簡単で評価しやすいというメリットがあります。一方、デメリットは、相対評価なので合理性が担保されず、被評価者が評価結果に納得しない可能性もあることです。そもそも従業員全員について熟知している人事担当者がいないと、標準者を選ぶこと自体が困難です。
標準偏差による調整
標準偏差を利用してそれぞれの点数を計算し直す調整方法もあります。
標準偏差とは「点数がどの程度ばらついているか?」を表す数値で、値が大きいほど平均点から離れていることがわかります。標準偏差は、それぞれの点数と全社平均点の差を2乗し、この数値を被評価者の人数で割って平均を出したあとに平方根を求めます。
たとえば、全社平均点が65点…(A)の場合、営業部の標準偏差は次の表の通りです。
| 被評価者 | 点数 …(B) | 全社平均 との差…(C) | 2乗 …(D) | 2乗合計 …(E) | 2乗の平均 …(F) | 標準偏差 …(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | 75点 | +10 | 100 | 725 | 241.7 | 15.5 |
| 佐藤 | 50点 | −15 | 225 | |||
| 田中 | 85点 | +20 | 400 | |||
| 計算式 | ー | (B)−(A) | (C)×(C) | (D)合計 | (E)÷3 | (F)平方根 |
全社の標準偏差も求めたうえで、各従業員の点数を次の式で修正します。
| 全社平均点+全社平均との差×(全社の標準偏差÷営業部の標準偏差) |
|---|
たとえば、全社の標準偏差が10…(H)の場合、鈴木さんの調整後の点数は71.5点になります。
| 被評価者 | 点数 | (A)+(C)×{(H)÷(G)} | 調整後の点数 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 | 75点 | 65+10×(10÷15.5) | 71.5点 |
| 佐藤 | 50点 | 65−15×(10÷15.5) | 55.3点 |
| 田中 | 85点 | 65+20×(10÷15.5) | 77.9点 |
標準偏差による調整には、合理的に点数を修正できるメリットがあります。一方、計算が複雑になるのがデメリットです。また、統計にもとづいた調整なので、従業員によっては説明されても理解するのが難しいかもしれません。
甘辛調整をして納得の評価運用へ
価値観や働き方の多様化が進む昨今、評価の公平性や従業員の納得感を担保するために甘辛調整が強く求められています。一方で、調整には人事担当者の負担が大きく、ほかの業務に支障をきたすこともあります。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、Excelなどの表計算ソフトを利用しなくても、評価点数をもとに振り分けられたAランク、Bランクなどの結果をドラッグアンドドロップで簡単に調整できます。軸・調整項目・絞り込み条件も柔軟に設定できるため、社内基準に沿った甘辛調整が実現できるでしょう。
| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 人事評価シートの【Excel】テンプレート |

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!