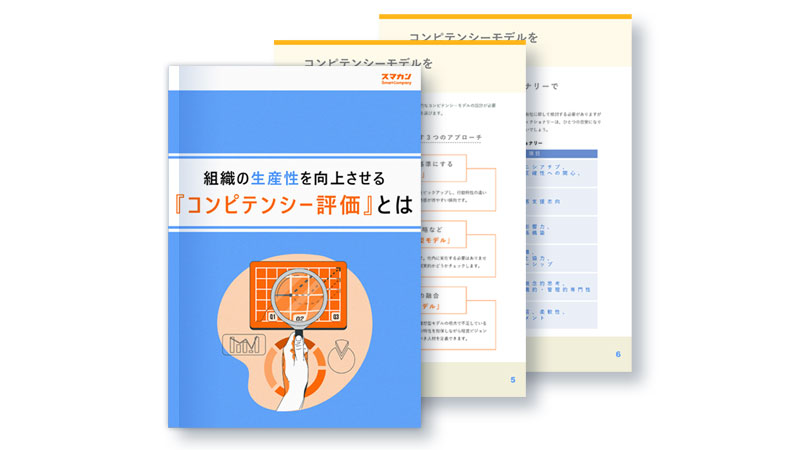- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
コンピテンシーとは? 意味や使い方を簡単に解説|評価や面接に活用
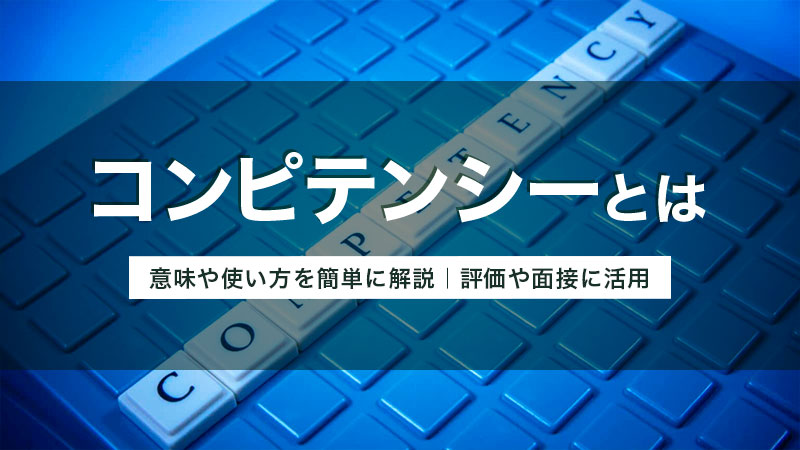
関連資料を無料でご利用いただけます
コンピテンシーとは、優れた成果を出す従業員の行動特性のことを指します。コンピテンシー評価やコンピテンシー面接などという言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、コンピテンシーという概念自体がよくわからない、興味はあるものの効果的な導入方法を知らない経営層や人事担当者も少なくありません。
そこで本記事はコンピテンシーについて解説するとともに、具体的にどのようにコンピテンシーを導入して活用することができるのかご紹介していきます。
目次(タップして開閉)
コンピテンシーとは

コンピテンシーの意味
コンピテンシー(competency)とは、直訳すると「能力」や「力量」などの意味を持ちます。
ビジネスにおいて企業の人事評価や採用面接などのシーンで用いられる概念です。成果を出す従業員の思考や行動特性を参考にし、より成果を出せる人材を増やすために導入されます。
コンピテンシーとはハイパフォーマーの行動特性を指す
コンピテンシーとは、企業の中で高い成果を出す従業員の行動特性のことを指します。
企業でコンピテンシーを導入する際は、パフォーマンスの高い従業員の仕事の進め方や、知識・技術の使い方などを分析して見える化します。
行動そのものに注目するというより、成果につながる行動のきっかけとなる従業員の価値観や性格という、内面的な要素が重視されるのも特徴です。
企業では、知識や豊富な経験があるにもかかわらず、成果を出すことができない従業員がいる一方で、成果を出す従業員もいます。
成果を出す従業員のコンピテンシー(行動特性)を抽出し、どのようにして成果を出しているのかを導き出すことで、企業の業績にも影響するでしょう。
コンピテンシーの類似語や関連語
コンピテンシーの類似語や関連ごとの共通点や違いについて解説します。
コンピテンシーとスキル
コンピテンシーは成果につなげるための技能や能力を発揮するための「行動」や「姿勢」を指す一方で、スキルは従業員本人が持つ「技術」そのものを指します。
具体例としてコンピテンシーは「顧客の声に耳を傾け、課題や悩みを深堀りする」などの姿勢が重視されますが、スキルは「デザイン力」や「企画力」などが挙げられるでしょう。
コンピテンシーとアビリティ
コンピテンシーは成果を出す従業員の「行動特性」や「性格」を指しますが、アビリティは生まれ持った「才能」や、努力して得た「能力」を指します。
スキルとアビリティは似ていますが、スキルは「物事を行う手腕や技量」「役立つ知識や経験」という意味で捉えられる一方で、アビリティは「あることを成し遂げる能力」や「持っている能力の中でも特に優れた能力」という意味で使われることが多いとされています。
コンピテンシーとコアコンピタンス
コアコンピタンスとは、他社に真似できない企業活動の中核となる強みです。
コンピテンシーとコアコンピタンスの違いは、主体が個人なのか組織なのかという点に違いがあります。
コンピテンシーは個人である「従業員」が成果を出す行動特性であり、コアコンピタンスは「組織」として成果や価値を出すことができる強みというイメージを持つとわかりやすいでしょう。
コンピテンシーの歴史と背景
コンピテンシーはどのように生まれ、ビジネスにおいて注目されるようになったのでしょうか。コンピテンシーの歴史と背景をご紹介します。
コンピテンシーの歴史
コンピテンシーという言葉は、1950年代に心理学用語として誕生しました。その後、1970年代にアメリカ国務省から依頼を受けた、ハーバード大学のデイビッド・マクレランド教授による調査が行われ、コンピテンシーという概念が広まりました。
その結果、動機や価値観・使命感といった潜在的な部分が行動の結果に影響することがわかりました。スキルや知識といった目に見える部分は氷山の一角にすぎないということから「氷山モデル」としてコンピテンシーの考え方が基礎づけられたのです。
日本では1990年代のバブル崩壊以降、それまで主流だった評価制度である年控序列型から成果主義へとシフトしていく中でコンピテンシーが認知されていったという背景がありました。
2005年には国家公務員試験の人物試験(面接試験)にも、コンピテンシーの考え方が取り入れられています。
なお、学校教育の現場では「キー・コンピテンシー」といって、社会の多様化に対応できる柔軟な考え方を育成する取り組みが普及しています。
参照:『参考資料』人事院
コンピテンシーが注目される背景
年功序列制度が崩壊して成果主義への移行が進むにつれて、従業員のパフォーマンスを正当かつ客観的に評価する方法が課題として浮上してきました。
育児・介護の両立やテレワークなど働き方の多様化に加え、残業時間の上限規制も導入されているため、従業員一人ひとりの生産性向上も求められる傾向にあります。
さらに近年は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれており、ビジネス環境の複雑さが増すだけでなく社会経済の先行きも予測しづらい状況となっています。
「VUCA」という言葉はもともと軍事用語として使われていましたが、予測不可能な状態という意味合いで2010年頃からビジネス用語としても使われるようになりました。
さらにはコロナ禍を受け、業種によってはビジネスモデルや働き方の抜本的な変革も求められているのが実情です。時代の変化に対応しながら会社の競争力と付加価値を高め、生き残りをはかるためにもコンピテンシーが注目されています。
コンピテンシーディクショナリーとは
「コンピテンシーディクショナリー」とは、コンピテンシーを研究する機関「スペンサー&スペンサー」がコンピテンシーを6つの領域と20項目に細かく分類したものです。
| 達成行動 | 達成思考、秩序・品質・正確性への関心、イニシアチブ、情報収集 |
|---|---|
| 援助・対人支援 | 対人理解、顧客支援志向 |
| インパクト・対人影響力 | 影響力、組織感覚(政治感覚)、関係構築 |
| 管理領域 | 他者の育成、指導、チームワークと協力、チームリーダーシップ |
| 知的領域 | 分析的思考、概念的思考、技術的・専門的・管理的専門性 |
| 個人の効果性 | 自己管理、自信、柔軟性、組織へのコミットメント |
コンピテンシーを導入する際には、基準となるモデルの設定が必要です。組織やチーム、職種によって設定すべき基準やモデルが異なるため、コンピテンシーにはどのような項目があるのかを知っておくとよいでしょう。
コンピテンシーモデルの設定
まずはコンピテンシーのモデルを設定しましょう。
コンピテンシーモデルは架空の人物として設定しますが、共通化したモデルを明確化することで、評価者も被評価者もどのように動けばよいのかという点がわかりやすくなります。
モデルを設定する場合は従業員が目指しやすくするために、職種や階級に応じて設定すること、できるだけ小さい単位で設定することが望ましいとされています。
実在型
実在型モデルは、実在する従業員で安定した成果を出している人物をもとにしたモデルです。自社にいる人物から設定するため、容易にモデルを設定しやすく、イメージも付きやすいといえます。
理想型
理想型モデルは、企業や組織の理念をもとに理想の人物像で設定するモデルです。
たとえば、どのようなときも積極的に動く人物を理想としている場合は「積極性がある」「主体性がある」「自分から提案していく姿勢」などを組み入れるとよいでしょう。
ハイブリッド型
ハイブリッド型モデルは、実在型と理想型の長所を活かして設定するモデルです。まずは実在型でモデルを設定したあと、会社や組織として理想的なコンピテンシー項目を追加して調整します。
理想型モデルとハイブリッド型モデルの場合、会社や組織の理想を取り入れたコンピテンシー項目が入ります。あまりにも高すぎる理想や現実離れした願いを入れすぎないように注意しましょう。
コンピテンシーモデルを設定するポイント
コンピテンシーモデルを設定する際は、
| ・コンピテンシーモデルをできるだけ細かく設定すること ・ハイパフォーマーへのヒアリング |
がポイントです。
コンピテンシーモデルを部署や職種、役職など細分化して設定するほど、より具体的で活躍できるモデルとして参考にしやすいでしょう。
また、コンピテンシーモデルを可能な範囲で細かく設定したら、それぞれの単位で活躍する複数のハイパフォーマーにヒアリングを行い、詳しく把握できるようにします。
さらにヒアリングした内容をもとにモデルを設定することで、実際の状況と行動がモデル化され、従業員側も成果を出して、高い評価を得るにはどうしたらよいのかがわかりやすくなるでしょう。
コンピテンシーのメリット

人材育成がしやすい
コンピテンシーを評価や面接に導入することで、人材育成がスムーズにできるメリットがあります。
すでに成果を上げている従業員の行動特性や思考を基準として評価や面接を行うことで、成果につながりやすい人材育成が行えるようになるからです。
モデルを基準に評価されるようになることで、従業員は具体的に何を変えればいいのかがわかりやすくなるため、企業が求める人物像に近づきやすくなるでしょう。
特にスキルはあるものの結果がともなわないというタイプの人は、行動や考え方を変えることで成果につながりやすくなる可能性があります。
評価者が評価しやすい
人事評価を行う際に「どのような基準で評価すればいいのかわからない」と悩む方は少なくないのではないでしょうか。
評価基準が明確でなかったり納得のいく評価をされなかったりすると、従業員のモチベーションの低下や不満につながる恐れがあります。
コンピテンシーに沿った評価や面接を導入することで、具体的な評価基準が明確化されるため、評価者は評価をしやすくなります。
また、評価項目に当てはまるか当てはまらないかといった評価を行うため、評価者によって評価結果が大きくずれるといったことも起こりにくいでしょう。
評価が公平で納得感がある
コンピテンシー評価は、評価基準が明確に設定されていることが多いです。そのため公平で客観的な評価を行いやすく、被評価者の納得感を得やすいといえます。
評価結果から「今後何をどのようにしていけば評価につながるか」を具体的に知ることができるため、評価結果が目標となり、従業員のモチベーションアップや成長によい影響をもたらすことが期待できるでしょう。
人事戦略につなげられる
コンピテンシー評価を導入することで、自社にはどのような行動特性や思考を持った従業員が必要なのかが具体化されます。
たとえば、自社のハイパフォーマーが持つ思考や能力を、募集要項の求める人物像に記載することで人事採用に活かせたり、研修の際に「どのような行動や思考を持つことで評価につながるか」を具体的に従業員に伝えることで人材育成に活かしたりすることができるでしょう。
自社に必要な人物像や行動特性、思考などが明確化されることで、これらの人事戦略につなげることができ、結果的に企業の生産性向上にもつながるでしょう。
個人の生産性向上=企業の業績向上
コンピテンシー評価では、高いパフォーマンスを発揮している従業員の行動特性をもとに評価基準を設定します。
そのため、仕事の成功につながった行動パターンがほかの従業員にも明らかになり、能力や考え方によい影響を与えることで社内に相乗効果が生まれやすくなります。
予測困難な出来事が目まぐるしく起こる「VUCAの時代」では、既存の考え方にとらわれず、環境の変化に対応しながら仕事にチャレンジする姿勢も行動特性に加味されるでしょう。
思うようにパフォーマンスが発揮できていない従業員に、コンピテンシー評価を通して潜在能力への気づきを促すことで、組織全体のレベルの底上げが期待できます。
なお、コンピテンシーを目標管理に活用することで、従業員に企業や組織の方向性を明確化することもできるでしょう。行動特性に合わせて目標達成のプロセスを示せるため、主体的な行動を通じて従業員一人ひとりの成長が期待できます。
評価結果から従業員の能力に合わせて適材適所に従業員を配置し、パフォーマンスを最適化することで、個人の生産性向上だけでなく企業全体の業績向上も目指せるでしょう。
優秀な人材の確保・定着
コンピテンシー評価を行うことで、優秀な人材を確保したうえで長期にわたって定着させる効果が期待できます。既存従業員の行動特性と照らし合わせて採用する人材を決めるため、採用のミスマッチも防げるでしょう。
たとえば試用期間にコンピテンシー評価を実施して、本採用するかどうかを見極めることも可能です。
評価のフィードバックを通じて、従業員は上司・組織からの期待や評価を実感できるだけでなくモチベーションも向上しやすくなります。発揮したパフォーマンスが認められ、行動に対する課題も明確になるため、能力向上を目指しやすくなるでしょう。
仕事のやりがいも実感できるので会社へのエンゲージメントが向上し、ハイパフォーマーのノウハウが自社に定着することで企業としての競争力も高まるのです。
| 無料ダウンロード資料 組織の生産性を向上させる「コンピテンシー評価」とは |
コンピテンシーのデメリットや課題
コンピテンシーのデメリットを3点ご紹介します。
コンピテンシー導入に時間や労力が必要
コンピテンシーを導入する場合は、コンピテンシーモデルの設定や評価基準、分析などを行わなくてはなりません。さらに、できるだけ小さい部署単位や職種ごとに設定することが望ましいため、その分の手間もかかります。
コンピテンシー評価を導入しようと思っても、導入から運用まですぐに取り入れることができないため、時間と労力がかかることはデメリットの一つといえるでしょう。
コンピテンシーが成功するかどうかはわからない
コンピテンシーの正解は、会社や組織によって異なります。そのため、設定したコンピテンシーモデルがそもそも間違っている場合もゼロではないという点をあらかじめ認識しておきましょう。
設定したコンピテンシーが適切かそうでないかは、運用と効果検証を繰り返してみないとわからないため、適宜調整や確認をして自社に合ったコンピテンシーモデルをつくっていく必要があります。
評価者に負担がかかりやすい
コンピテンシーを評価や採用に活用する場合、評価者や採用担当者に負担がかかりがちです。
特に、部署や職種、役職など、設定するコンピテンシーモデルの単位が細かいと、評価者や採用担当者はすべて理解したうえで、区別しなければなりません。
そのため、複数人の担当者で分けるなどの工夫や配慮が必要です。
コンピテンシーの導入方法
コンピテンシーを導入する際は、以下の手順で進めるとよいでしょう。
- 1.ヒアリング→コンピテンシー抽出
- 2.企業や組織との認識すり合わせ
- 3.コンピテンシー評価段階分け
- 4.テスト導入
1.ヒアリング→コンピテンシーモデルの設定
コンピテンシー導入の際は、まず自社で成果を出している従業員を集め、ヒアリングすることから始まります。自社で成果を出す従業員の行動特性や思考を集め、具体的なコンピテンシーモデルの抽出、設定を行いましょう。
2.企業や組織との認識すり合わせ
コンピテンシーを設定して運用する前に、企業や組織、チームとのすり合わせを行いましょう。
抽出したコンピテンシーモデルの基準の中に、企業や組織の考えに沿っていないものがあった場合には基準から外す必要があります。
3.コンピテンシー評価段階分け
コンピテンシーを運用する前に評価の段階分けもしておきましょう。3~5段階程度にレベルを分けることで、人事評価にも活用しやすくなります。
4.テスト導入
コンピテンシー評価の基準や設定が整ったら、適正に運用できるかどうかをテスト導入してみましょう。
テストの際には、自社のハイパフォーマーを評価基準に照らし合わせて、その基準が適切か確認しましょう。さらに、ほかの従業員へもテストを行って、結果にずれが生じないかを確認するとよいでしょう。
コンピテンシーの具体的な活用シーン
コンピテンシーは、人事・HR領域においてどのような場面で活用されるのでしょうか。
ここでは、具体的な活用シーンを4つご紹介します。
人事評価
コンピテンシーは人事評価において広く活用できます。人事評価に導入することで、成果を出すために何が必要なのかという点を明確化できることで従業員のレベルアップにもつながるでしょう。
明確な基準ができることで、より公平で納得感の高い評価につながり、従業員の満足度やモチベーションも向上しやすくなるでしょう。
採用試験
コンピテンシーは採用面接においても活用することができます。
すでに自社で成果を出している人物をコンピテンシーモデルとして分析することで、人事担当者が具体的な採用したい人物像を共通認識として持つことができたり、採用戦略によい影響を与えたりすることができるでしょう。
効率的な採用試験が行えるようになるというメリットがあるため、採用面接や試験での活用もおすすめです。
人材教育
コンピテンシーは人材教育という面でも役立ちます。コンピテンシーモデルに沿って、研修などの人材教育を行いながら課題を解決していくことで、企業全体として成果を出しやすい組織になっていくことが期待できます。
人事面談や1on1において、コンピテンシーの基準や内容についての達成度合いなどを話してみるのも効果的でしょう。
| 無料ダウンロード資料 1on1ミーティングの効果的な実践方法 |
組織強化
コンピテンシーは会社としての組織強化やマネジメントにも活用できます。
基準とするコンピテンシーに対して、評価が低い従業員の所属部署や役職が本当に適切なのかどうかの判断にも役立ちます。
明らかに基準より低い場合は適材適所の配置ができているかどうかの確認をしてみましょう。
コンピテンシーを評価に導入
続いてコンピテンシー評価について解説します。
コンピテンシー評価の利点
コンピテンシー評価を導入することで、従業員が「成果を出すための行動や姿勢、考え方」を理解することができるという点です。
ただやみくもに目標を設定し、達成に向けて行動するのではなく、達成するために必要な行動や考え方を意識できるようになるため、従業員としても組織としても成長するチャンスになるでしょう。
また、人材教育が思うようにできていないという課題を持つ場合にも有効といえます。コンピテンシー評価を導入することで、そもそも成果を出すためにどうすればよいかが明確になり、従業員はその行動特性に沿った意識を持つ癖がつくようになるため、人材教育にもつながるでしょう。
コンピテンシー評価の課題
コンピテンシー評価を導入する際の課題としては、設定する際や評価の際に時間がかかるという点が挙げられます。
コンピテンシーの設定はより小さい単位での設定が好ましいとされているため、チームや細かい部署ごとに設定したり、評価を行わなければなりません。
評価者は適切な基準を理解したうえで評価をする必要があるため、一定の負担がかかるといえるでしょう。
コンピテンシーを面接に導入

コンピテンシー面接の利点
コンピテンシー面接を導入すると、あらかじめ自社で成果を出すタイプの行動や考え方を把握していれば、採用試験でもその考え方を持つ人物かどうかをチェックすることができます。
たとえば面接において、コンピテンシーモデルの基準に沿った回答をする求職者がいれば、自社でも成果を出しやすい可能性が高いということになるでしょう。
明確な基準があることで、直感や雰囲気など、面接する側の主観が入りやすい場合でも、より客観的な判断をしやすくなります。
コンピテンシー面接の課題
コンピテンシー面接の課題としては、自社に成果を出している人物が少ない場合です。少ない対象者をもとにヒアリングした場合、極端なコンピテンシーモデルになる可能性があります。
万が一設定したコンピテンシーが適切ではなかった場合、採用面接でも正しい基準ではない可能性が高くなります。
コンピテンシーの設定ミスを防ぐためにも、職種やチームごとに細かく分けたコンピテンシーを設定するほか、少ない対象でコンピテンシーモデルを設定する場合には、ハイブリッド型モデルを検討してみるとよいでしょう。
また、コンピテンシー面接の評価では「コンピテンシーレベル」という基準に沿って評価することも必要です。
| レベル | 行動 | 特徴 |
|---|---|---|
| レベル1 | 受動行動 | 受動的な姿勢や行動をとるタイプ |
| レベル2 | 通常行動 | 与えられた仕事をミスなくこなすタイプ |
| レベル3 | 能動行動 | 能動的な姿勢や行動がとれるタイプ |
| レベル4 | 創造行動 | 創意工夫を行い、状況を変化させられるタイプ |
| レベル5 | パラダイム転換行動 | 組織の常識や固定概念を覆すことができるタイプ |
この基準は、コンピテンシーをレベル分けしたものです。自社で活躍しやすいタイプや求められているレベルを明確にしたうえで選考に反映させましょう。
コンピテンシーの重要なポイント
コンピテンシーを自社に取り入れる際に留意すべきポイントについて解説します。
コンピテンシーモデルが常に適切ではない
コンピテンシーモデルを設定し、評価や面接に導入する場合には、設定するコンピテンシーモデルが必ずしも常に適切だとは限らないという点を踏まえておきましょう。
課題や目標によっても、成果を出せる行動や意識はモデルと異なる可能性があります。成果が出ない場合や想定していた結果と異なる結果が出ている場合には、再度コンピテンシーモデルを分析するなどしてみましょう。
表面的な行動だけでは意味がない
コンピテンシーを導入する場合、意識すべきなのは行動だけではありません。コンピテンシーモデルの思考や業務に対する姿勢も意識し、取り入れる必要があります。
表面的に行動パターンを変えるのは比較的簡単かもしれませんが、意識や姿勢を変えることは難しい部分ともいえます。
しかし、そもそもの考え方をコンピテンシーモデルに寄せていくことで継続的で安定した結果を出せるようになるという点を理解しておきましょう。
コンピテンシーを導入して終わりにしない
コンピテンシーを導入して評価や採用に導入したら、分析も行うことが大切です。
たとえば、成果が出せている従業員が多い部署を見つけ出し、従業員の共通点を探します。反対に、成果が出せていない従業員が多い部署は、どのような共通点があるのかも見つけましょう。
設定したコンピテンシーとの違いや、両者を比較した結果、どのような差があるのかを考えることで、今後の課題を解決するヒントになり、新たなコンピテンシーの発見にもつながるはずです。
コンピテンシーの導入で大切なことは、導入して満足するのではなく、積極的な活用を通して全体を捉えて、分析を行うことといえるでしょう。
まとめ
コンピテンシーとは、成果を出している人物の思考や行動特性のことを指します。自社に合ったコンピテンシーモデルを設定し、評価や採用面接などに活用することで、成果を出しやすい組織につながる可能性があります。
評価制度や目標管理にコンピテンシー導入を検討している場合は、ぜひ本記事でご紹介したコンピテンシーのメリットデメリットや注意点、導入方法を参考にしてみてはいかがでしょうか。
コンピテンシー評価・面接も『スマカン』で管理
『スマカン』は、人材データの一元管理、戦略的人事の実行をサポートしながら、コンピテンシー評価や面接を支援するタレントマネジメントシステムです。コンピテンシー評価だけでなく、OKRやMBO、360度評価などさまざまな評価手法にも活用できるでしょう。
『スマカン』は、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化につなげることができるでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!