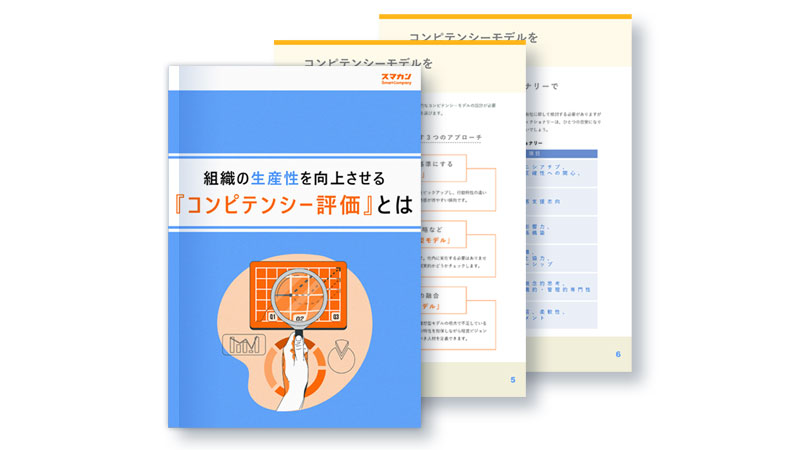- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
コンピテンシー評価とは? 行動特性に注目した評価手法|項目例も紹介
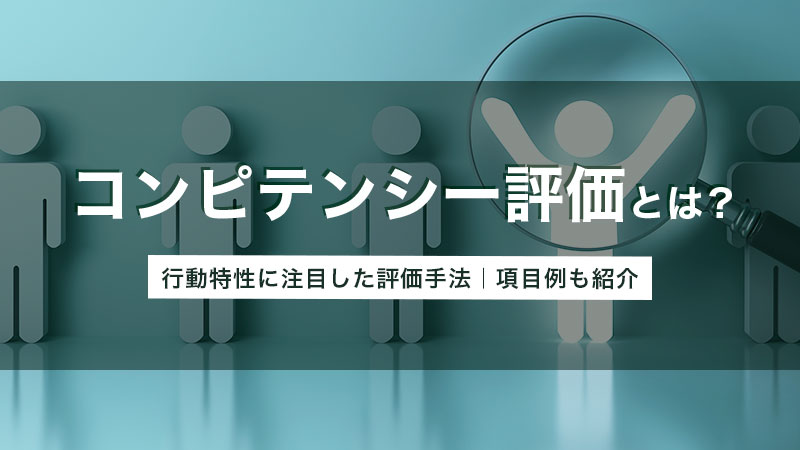
関連資料を無料でご利用いただけます
コンピテンシー評価とは、成果を出す従業員やその行動特性をモデルとし、評価に反映させる評価手法です。コンピテンシー評価を導入すると、企業に合った人材を明確にし、納得感のある人事評価や人材育成にも活かすことができます。
しかし、「コンピテンシー評価がうまく運用できていない」「コンピテンシー評価の適切な項目が具体的にわからない」など、課題を抱えている企業も少なくありません。
そこで本記事は、コンピテンシー評価について解説しながら、項目例やシートの書き方についてもご紹介します。コンピテンシー評価の導入を検討している企業や、すでにコンピテンシー評価を導入しているものの、効果的な運用ができていないという企業はぜひ参考にしてみてください!
目次(タップして開閉)
コンピテンシー評価とは
コンピテンシー評価では、企業で成果を出している従業員や理想のモデル像を明確にして、人事評価に反映します。成果を出すためにはどのような要素が必要なのかが明確になると、従業員の成長を促進できるでしょう。
また、コンピテンシーモデルを確立することで、具体的な評価基準が明確になります。納得感の高い評価につながり、従業員の満足度やモチベーションが向上しやすくなるでしょう。
コンピテンシー評価以外の評価手法には、MBO(目標管理制度)や360度評価などがあります。3つの評価を基準や評価結果の観点で比較すると、以下のように整理できます。
| コンピテンシー評価 | MBO(目標管理制度) | 360度評価 | |
|---|---|---|---|
| 評価基準 | コンピテンシーモデルに沿っているかで評価 | 個人が設定した目標の達成度で評価 | 複数の評価者によって多面的に評価 |
| 評価結果 | 評価者の主観や感情、評価スキルに左右されにくい | 評価者の主観など左右されにくいが、達成基準を明確にできない職種があり、目標の難易度にバラつきが出やすい | 評価者の主観や感情、好き嫌いが入り込みやすい |
以上のことから、コンピテンシーを人事評価に導入すると、評価者による主観的な評価を軽減し、公平性のある客観的な人事評価が実現できる可能性が高まります。
コンピテンシーとは
コンピテンシーとは、優れたパフォーマンスで成果を出す思考や従業員の行動特性のことです。英単語としては、「能力」や「力量」などの意味を持ちます。企業の従業員の中には、同じくらいの経験とスキルがあるにもかかわらず、成果を出せない従業員と成果を出せる従業員がいるはずです。
そこで、成果を出せる従業員のコンピテンシー(行動特性)を明確にすることが大切です。成功している従業員のコンピテンシーを参考にすることで、取るべき行動や姿勢がわかりやすくなるからです。
コンピテンシーは、企業の人事評価や人材採用(面接)などのシーンで用いられる概念で、近年注目されています。
職業資格制度やスキルとの違い
職能資格制度とは、従業員の能力に応じた等級を用意し、各等級に沿って賃金やボーナスを決める仕組みです。年功序列制度など日本型雇用と相性がよい制度といえます。反対にコンピテンシー評価は、成果主義と相性がよい傾向にあります。
コンピテンシー評価と職能資格制度の違いをまとめると、以下の通りです。
| コンピテンシー評価 | 職能資格制度 | |
|---|---|---|
| 評価項目 | 比較的具体性がある | 曖昧(あいまい)になる傾向 |
| 評価の対象になる能力 | 成果を出している職務上の能力(行動特性) | ゼネラリストに必要な能力 |
コンピテンシー評価が注目される理由
コンピテンシー評価が注目されている理由や背景について、どのようなものがあるのでしょうか。
適切な評価ができていない
コンピテンシー評価が注目される理由の一つに、自社の人事評価を効果的に運用できていないという点が挙げられるでしょう。適切な評価ができていないと、従業員の不満を生み出し、意欲の低下や離職にもつながってしまいます。
公平で納得感の高い評価を行うには、客観的な根拠や視点に基づいた評価が大切です。コンピテンシー評価では、設定したコンピテンシーモデルに沿って評価を行うため、公平かつ客観的な視点で評価をしやすくなるでしょう。
年功序列が時代に合っていない
コンピテンシー評価が注目される背景には、現代において年功序列による評価が合わなくなってきた点も挙げられます。
日本では「職能資格制度」による評価が一般的でしたが、人材の流動が活発化している昨今は、成果に基づいた評価が求められてきています。年功序列や勤務年数による評価を続けると、従業員の不満が募ってモチベーションが低下してしまうからです。
そのため、成果を出すために基準となるモデルを設定するコンピテンシー評価が、効果的な評価手法として注目されているといえるでしょう。
人件費のバランスを整える
コンピテンシー評価を行うことで、適切な給与(人件費)にもつながります。
職能資格制度のもとでは、勤務年数が長いほど給与が高い傾向にあり、成果とは関係のない給与設定ともいえるでしょう。勤務年数が長くなれば給与が上がるため、年齢が高い従業員が多くいる企業は、人件費が増える傾向にあります。
一方のコンピテンシー評価の運用では、成果に見合った給与が支払われるため、人件費の適正化が期待できるでしょう。
| 無料お役立ち資料 組織の生産性を向上させる「コンピテンシー評価」を徹底解説 |
コンピテンシー評価のメリット
コンピテンシー評価にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットについてご紹介します。
適切な人事評価につながる
コンピテンシー評価におけるメリットの一つには、適切な人事評価につながる点が挙げられます。
コンピテンシー評価の場合、具体的なコンピテンシーモデルが評価基準になります。評価基準がわかりやすいため、従業員にとっても公平で納得感のある評価につながりやすくなるでしょう。
また、コンピテンシーモデルが明確化されていると、取り組むべき課題がわかりやすくなるため、従業員の意欲を高めて成長を促進できるはずです。
人材育成がしやすくなる
コンピテンシー評価を導入すると、人材育成に取り組みやすくなる点もメリットの一つです。
コンピテンシー評価では、すでに成果を上げている従業員の行動特性や思考性を基準とします。そのため、成果につながりやすい人材像が明確になるため、従業員は何をすればよいか、理解しやすくなるはずです。
コンピテンシーモデルという明確な基準を行動指針として、日々の業務に取り組むことで、人材育成を促進できるでしょう。
評価者の負担を軽減できる
コンピテンシー評価では、評価者の負担を軽減させられるのもメリットです。コンピテンシーモデルを基準として具体的に評価できると、評価に悩むことが減り、これまでかけていた工数も減らせるでしょう。
| 無料お役立ち資料 人事評価シートのテンプレート【Excel版】 |
コンピテンシー評価のデメリット
コンピテンシー評価のデメリットについて、具体的な点を確認してみましょう。
コンピテンシー評価の導入には手間と時間がかかる
コンピテンシー評価を導入する場合は、時間と労力がかかるのがデメリットといえるでしょう。
コンピテンシーモデルの設定から認識のすり合わせなどを綿密に行う必要があります。また、できるだけ小さな部署や職種ごとに設定することが望ましいため、さらに手間がかかる可能性があります。
コンピテンシー評価の運用は、すぐに進められないため、デメリットの一つといえるでしょう。
運用の難易度が高く、必ず成功するとは限らない
コンピテンシー評価は、コンピテンシーモデルを独自に設定するため、会社や組織によって成功の基準が異なります。また、設定したコンピテンシーモデルが間違っている可能性もゼロではない点も認識しておきましょう。
コンピテンシー評価そのものや、設定したコンピテンシーモデルが適切かどうかは、自社で運用を繰り返してみないとわかりません。継続的に運用してみないと、成功したかどうかは判断できない点もデメリットといえるでしょう。
| 無料お役立ち資料 コンピテンシー評価で気をつけたいポイントを解説 |
コンピテンシー評価の導入フロー
コンピテンシー評価を導入する際の具体的な手順やフローをご紹介します。
1.コンピテンシーモデルの設定
コンピテンシー導入の際は、まず自社で成果を出している社員を集め、ヒアリングすることから始まります。自社で成果を出す社員の行動特性や思考を分析して、具体的なコンピテンシーモデルを抽出し、設定しましょう。
2.企業全体や組織との認識すり合わせ
コンピテンシー評価を運用する前に、企業全体や部署とすり合わせましょう。設定したコンピテンシーモデルの基準の中に、企業や組織の考えに沿っていないものがないか、改めて適切な基準を検討します。
3.コンピテンシー評価で用いるランク分け
コンピテンシー評価を運用する前に、評価で用いる評価ランクの分類もしておきましょう。3~5段階のランクに分けることで、人事評価にも活用しやすくなります。評価ランクの設定では、現在の評価手法で使っているものを用いると、社内で混乱が起こりにくくスムーズかもしれません。
4.コンピテンシー評価の検証や調整
コンピテンシー評価の設計ができたら、テストで運用して検証し、全体を調整しましょう。テスト運用で、適切な評価になるかどうかを総合的に確認し、問題がなければ従業員に周知して運用を始めましょう。
コンピテンシー評価の項目例

コンピテンシー評価を運用するにあたって、どのような評価項目を設定すればいいかわからないという方も多いでしょう。
コンピテンシー評価の項目は、部署や職種、チームごとに独自で設計します。ここでは、全社員に共通する項目例を紹介します。各部署やチームごとの項目例としても参考にしてみてください。
| 【状況判断力や認知力】 |
|---|
| ・現在の状況を適切に把握して、どうしたらよいのかを理解している ・行動や意見の先にどのような影響を及ぼすかを理解し、取り組んでいる |
| 【発信力やプレゼンテーション力】 |
|---|
| ・相手が求めているものを理解したうえで、情報を発信している ・情報を適切に与え、好印象を持たれる伝え方ができる |
| 【第一印象、マナー】 |
|---|
| ・清潔感があり、相手に不快感を与えない身だしなみ ・社会人としてのマナーをわきまえ、相手に好印象を与えられる |
| 【業務姿勢や目標への取り組み】 |
|---|
| ・前向きに業務に取り組んでいる ・他社からの意見に耳を傾けている ・目標達成への執着心を持って取り組んでいる |
部署やチームごとのコンピテンシーの評価項目は職務に即して、より具体的かつ専門的なものを設定するとよいでしょう。
コンピテンシー・ディクショナリーも参考にする
コンピテンシー評価では、コンピテンシーを6つの領域に分類した「コンピテンシー・ディクショナリー」が参考になります。モデルや項目を設計する際にお役立てください。
| コンピテンシー・ディクショナリーで定義されている6領域 |
|---|
| ・達成行動 ・援助や対人支援 ・インパクトと対人影響力 ・管理領域 ・知的領域 ・個人の効果性 |
コンピテンシー・ディクショナリーは、上記6領域をさらに細かく、20領域に分類しています。上記を参考にしながら、会社や各部署、チームに適した項目の追加と修正を行うといいでしょう。
コンピテンシー評価の注意点
コンピテンシー評価を運用する際は、注意点もあります。あらかじめ注意点を理解して、効果的な運用を目指しましょう。
コンピテンシー評価の目的は成果を出すこと
コンピテンシー評価の目的は、成果を出すことです。
これまで成果を出してきた従業員を参考にすることで、より多くの従業員が成果を出せるようになる状態を目指すのです。目的を理解していないと、コンピテンシーモデルを設定しても、期待する効果や成果はあわわれないでしょう。
完璧を目指しすぎない
コンピテンシー評価を行う際に注意したいのは、完璧にコンピテンシーモデルの基準を満たす従業員はほとんどいないということです。そのため、コンピテンシーモデルの基準に対して、完璧を求めすぎないという認識を持っておきましょう。
あまりにも厳しく求めてしまうと、従業員の意欲が低下してしまう原因にもなりかねません。コンピテンシーモデルは目指すべき基準の一つとして設定し、適切に評価を行いましょう。
コンピテンシー評価のモデルは定期的に更新する
コンピテンシー評価では、設定するコンピテンシーモデルについて定期的な見直しや更新が必要です。最初に設定したコンピテンシーモデルが、常に正しいわけではないということを認識しておきましょう。
課題や目標、社会情勢やビジネスの状況の変化によって、成果を出せる行動や意識は変化する可能性があります。コンピテンシー評価を運用していても、満足な成果が出ない場合や目指しているものと異なる結果が続く場合は、再度コンピテンシーモデルを分析してみましょう。
コンピテンシー評価は『スマカン』で一元管理
『スマカン』は社内の人材データを一元管理し、戦略的な評価や育成、配置を支援するタレントマネジメントシステムです。
人事評価機能には、コンピテンシー評価などの運用に適したテンプレートが用意されています。評価シート・フォームは自由にカスタマイズ可能。配布から集計、分析までを半自動化できるため、コンピテンシー評価の運用担当者の負担を軽減します。
『スマカン』は、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化につなげられるでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
コンピテンシー評価は、自社で高い成果を出している従業員の行動特性をモデルに、基準を設定する評価手法です。
評価基準や高い成果を出している人の行動特性や思考が明確になり、人材育成を進めやすくなったり、従業員のモチベーション向上を助けたりします。
ただし、導入から運用までに時間と労力がかかるのも事実です。効果的なコンピテンシー評価の運用を目指したいという場合は、あらかじめ余裕をもった計画を立て、導入を進めましょう。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!