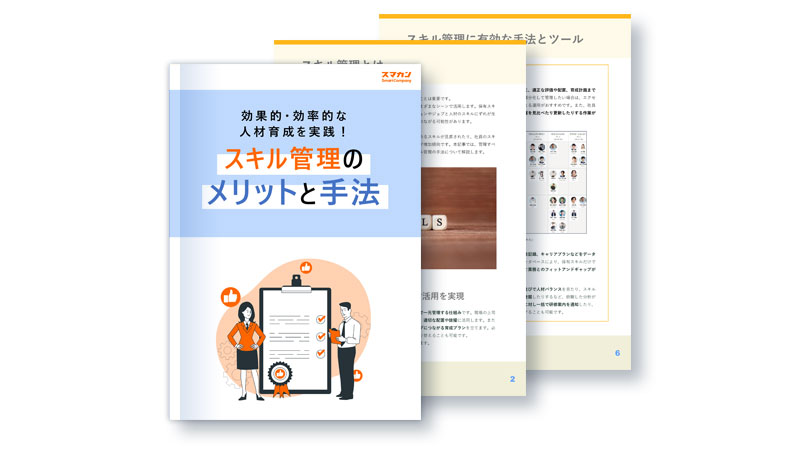- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材育成
人材育成に活用するフレームワーク|7つの種類やポイントを徹底解説

関連資料を無料でご利用いただけます
人材育成にフレームワークを取り入れると、進め方が整理されるため合理的に進められます。人材育成を行う際は、自社に最適な人材育成のフレームワークを理解し、正しく運用したいところです。
しかし「人材育成に使えるフレームワークの種類がわからない」「フレームワークを活用した育成手順がわからない」と感じている企業もあるかもしれません。
そこで本記事は、人材育成において活用できるフレームワークの種類を中心に、重要性や取り組み手順などもご紹介します。人材育成をできるだけ効率的に進めたいと考えている経営者や、人事担当者はぜひチェックしてみてください。
>>>一人ひとりに適した人材育成を実現『スマカン』サービス資料を見てみる
目次(タップして開閉)
人材育成におけるフレームワークの重要性
人材育成では、フレームワークを活用することが重要と考えられています。長期にわたる育成や、継続的に取り組む必要のある作業を合理化できるためです。
一定のルールを適用した人材育成のフレームワークを活用すると、状況を分析しながら秩序立てて育成計画を実行できる可能性が高まるのです。人材育成に関するノウハウやスキルがない企業でも、有効な人事施策を進められるでしょう。
人材育成においてフレームワークを活用しないで取り組むと、計画の策定から実行まで、時間と労力がかかってしまうかもしれません。フレームワークによって、育成のゴールを意識して効率的に進められるはずです。
フレームワークとは
そもそもフレームワークとは「輪郭」や「大筋」を意味する言葉です。ものごとの枠組みや骨となる部分をイメージするとわかりやすいかもしれません。ビジネスにおけるフレームワークとは、共通の考え方や戦略、方向性の枠組みを指します。
たとえば、新たな施策を考える際、まったく知識も何もない状態から始めるより、成功パターンやモデルをもとにしたフレームワークを活用した方が、効率よく進められるはずです。ビジネスで使えるフレームワークにはさまざまな種類があり、目的に沿ったものを見極める必要があるでしょう。
人材育成におけるフレームワークの種類
人材育成に活用できるフレームワークには、複数の種類があります。定番といえる7つのフレームワークの特徴を解説します。
| ・SMARTの法則 ・カッツ理論 ・70:20:10フレームワーク ・カークパトリックモデル ・HPI(Human Performance Improvement) ・思考の6段階モデル ・氷山モデル |
SMARTの法則
人材育成で活用できるフレームワークの1つめは「SMARTの法則」です。目標設定によく使われ、目標を達成するために必要な要因の頭文字を取って名づけられています。
| S(specific) | 具体的でわかりやすい |
|---|---|
| M(measurable) | 測定可能である |
| A(achievable) | 達成可能である |
| R(relevant) | 関連している |
| T(time-bound) | 期限が明確である |
SMARTの法則に沿って目標を管理すると、従業員の段階的なレベルアップにつながります。誰が見ても明確でわかりやすい目標を設定し、期限までに達成したら再度新たな目標を設定するという繰り返しで、従業員に継続的な成長を促せるでしょう。
カッツ理論
人材育成に活用できるフレームワークの2つめは「カッツ理論」です。カッツ理論は、アメリカの経済学者ロバート・カッツ氏によって提唱されました。
カッツ理論はマネジメント層に必要とされる3種類のスキルについて、階層に応じてどのスキルを強化すべきかを明確にしたものです。
課長や係長など下級の管理職ではテクニカルスキル、中間層ではヒューマンスキル、さらに上の管理職層ではコンセプチュアルスキルと、階層が上がるにつれてより重視されるスキルが変わっていくとされています。
| カッツ理論における3つのスキル | |
|---|---|
| コンセプチュアルスキル | 概念化能力 |
| ヒューマンスキル | 対人関係能力・人間理解能力 |
| テクニカルスキル | 業務遂行能力・専門能力 |
| カッツ理論におけるマネジメント階層 | |
|---|---|
| トップマネジメント | 経営層(企業幹部や社長) |
| ミドルマネジメント | 中間管理職(課長や部長) |
| ロワーマネジメント | 下級管理職(係長や主任) |
特に、役職者や管理職の育成に効果の高いフレームワークといえるでしょう。
70:20:10フレームワーク
人材育成に活用できるフレームワークの3つめは、人材の成長度合いを示す「70:20:10フレームワーク」です。アメリカのロミンガー社が、経営者に対して行った『リーダーシップの発揮のために役立ったこと』の調査から導き出されました。
この調査結果から、リーダーシップを発揮するための要素は以下の割合で有効だとされています。
| 仕事の経験 | 70% |
| 他社からの薫陶(くんとう) | 20% |
| 研修 | 10% |
70:20:10フレームワークにより、経営層などリーダーを育てるには、現場の実務経験や環境が重要であることがわかりました。
一方で研修は、リーダーの育成には効果が少ないということになります。特に管理職を育成したい企業は、この法則を意識してOJTなど実務を中心に育成に取り組むといいでしょう。
カークパトリックモデル
人材育成に活用できるフレームワークの4つめは「カークパトリックモデル」です。
カークパトリックモデルは、アメリカ経営学者ドナルド・カークパトリック氏によって提唱された、教育の効果を4段階で測るフレームワークです。
| 段階 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| レベル1 | Reaction(反応) | 研修の満足度 |
| レベル2 | Learning(学習) | 研修の理解度や学習到達度 |
| レベル3 | Behavior(行動) | 研修後の行動変化や職場での実践 |
| レベル4 | Results(業績) | 組織への影響や投資対効果 |
このように4段階の各レベルに応じて教育や研修の効果を測ります。
カークパトリックモデルを使って研修の効果測定のポイントを把握し、レベルごとに内容を評価できると研修の最適化や改善につながり、効果的な人材育成を実現できるでしょう。
HPI(Human Performance Improvement)
人材育成に活用できるフレームワークの5つめは「HPI」です。HPIは、人材の状況と組織の課題を洗い出し、改善することを重視するフレームワークです。
以下のステップに沿って行われます。
| 1.パフォーマンス分析・現状とのギャップの洗い出し 2.ギャップの原因を分析 3.原因を解決するための施策を策定 4.施策の実行 5.施策効果の評価 |
HPIの特徴は、人材の視点から組織の課題と向き合うこと。まずは本来あるべき人材の姿と現状のギャップを明確にしてから、課題の原因を分析します。最終的に人材や組織のパフォーマンス向上を目指し、人材育成につなげます。
思考の6段階モデル
人材育成に活用できるフレームワークの6つめは、教育心理学者のベンジャミン・ブルーム氏が提唱した「思考の6段階モデル」です。
教育では思考を6段階に分類し、各段階の能力を高めることが重要であることを示したものです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| レベル1(知識) | 言葉、方法、事実などを知っているか |
| レベル2(理解) | 内容を言い換えたり、説明したりできるか |
| レベル3(応用) | 知識を他の場面でも活用できるか |
| レベル4(分析) | 全体を分解したり、個々を説明できるか |
| レベル5(統合) | 一つひとつを組み合わせて、全体をつくれるか |
| レベル6(評価) | 基準から情報の価値を判断(評価)できるか |
この6段階に沿って研修を実施したり、人材育成プログラムを構成したりすることで、人材育成を効率的に進められるでしょう。
氷山モデル
人材育成に活用できるフレームワークの7つめは、氷山モデルです。
氷山モデルとは目の前の問題のみと向き合うのではなく、どのような要素から生じているのか全体像を捉えて本質的な解決を目指す考え方です。
| できごと | 具体的に見えている出来事や問題 |
|---|---|
| パターン | 時間軸で捉える変化のパターン(規則性や大局的視点) |
| 構造や思考 | どのような構造や思考が重なってパターンが発生しているのか |
氷山モデルは、氷山と水面でイメージするとわかりやすいでしょう。水面上に見えているもの(できごとや結果)は一部にしか過ぎず、水面下にはさらに大きな氷山(パターンや構造からなる要因)が隠れていることを指しています。
人材育成においては、水面上に見えている部分は結果であり、水面下で隠れている部分は知識やスキル、意識、特性などが当てはまるでしょう。
人材育成でフレームワークを活用するステップ

人材育成について、フレームワークを活用したいと考えているものの、手順がわからない方もいるかもしれません。
そこで、フレームワークを活用しながら人材育成に取り組むステップをご紹介します。
| 1.人材育成の状況確認 2.経営目標とのすり合わせ 3.フレームワークの選定 4.人材育成計画の策定 5.人材育成計画の共有と調整(管理職) 6.人材育成に関する全体周知 7.人材育成を開始 |
1.人材育成の状況確認
人材育成にフレームワークを取り入れる際の最初のステップは、人材育成の状況を把握することです。
企業としての全体像だけでなく、各部署の状況も把握しなければなりません。現場の感覚や意見も聞き入れることで、現場に過度な負担をかけずに育成を進められるとともに、全社的に人材育成に対する理解も深められるでしょう。
2.経営目標とのすり合わせ
次のステップでは、経営目標と人材育成の目指すところをすり合わせます。人材育成の最終目的は企業の成長であるため、経営目標と方向性がズレてしまってはなりません。
会社の経営層や幹部とともに、求める人材像について協議します。経営目標を達成するために必要な人材像と、取り組む人材像に差がないように入念に確認しましょう。
3.フレームワークの選定
次のステップでは、実際に人材育成に活用するフレームワークを選定します。
経営目標や人材育成計画で決定した従業員に成長してほしい人材像をもとに、どのフレームワークを採用すべきか判断しましょう。使うフレームワークによっては、自社の求める人材像とは異なる人材が育ってしまう可能性もあります。フレームワークはそれぞれの特徴を理解したうえで、慎重に選定しましょう。
4.人材育成計画の策定
次のステップでは、人材育成計画を策定します。
経営目標とすり合わせた人材像をもとに、どのような人材育成に取り組むのかを計画します。具体的な期間や育成人数、目標とするスキルなどを明確にすることで、わかりやすい人材育成計画を策定しましょう。
5.人材育成計画の共有と調整(管理職)
人材育成計画が策定できたら管理職へ共有し、必要に応じて調整を行います。現場の細かい要望も踏まえて、現場から理解を得られるような内容に調整しましょう。
現場の従業員から理解や納得が得られていないと、積極的に人材育成に協力してもらえない可能性があります。担当者は、従業員が受け身になってしまわないように現場の声と経営目標、両者のバランスがとれるように調整しましょう。
6.人材育成に関する全体周知
人材育成に関する調整や準備が整ったら、社内全体に周知します。周知を怠ってしまうと現場が混乱し、不満の原因になるかもしれません。人材育成の目的や意義、従業員へのメリットも伝えながら、理解を深めてもらえるように周知しましょう。
7.人材育成を開始
いよいよ人材育成を開始します。人材育成に関する施策を始めたあとも、記録や情報の更新が大切です。あとから見返して改善点を見つけたり、分析したりするためです。PDCAを回しながら、より効果的な人材育成になるように取り組みましょう。
人材育成でフレームワークを有効活用するポイント
人材育成でフレームワークを有効活用するポイントについてご紹介します。どのように活用すると、より効果的に活用できるかチェックしてみましょう。
目的に合ったフレームワークを選定する
人材育成でフレームワークを活用する際は、自社が育成したい人材像に合ったものを選びましょう。
特に経営目標や企業目標の達成を目指すうえで適切なもの、目標達成の道筋となるものを選ぶことが大切です。人材育成の最終目的は、企業の成長です。企業の成長に貢献できるような人材を育成することを意識して、適切なフレームワークを選定しましょう。
PDCAを回す
フレームワークを活用した人材育成では、実践と効果測定、課題発見のサイクルを繰り返すことが大切です。ただ単にフレームワークを活用したからといって、望むような成果が出るわけではありません。PDCAを回し、必要な場合はフレームワークの調整や修正も行いながら改善に努めましょう。
階層や部署で使い分けする
人材育成で活用するフレームワークは、必ずしも1種類だけを選ぶ必要はありません。役職や部署、職種によって適切なフレームワークは異なることが多いです。状況に応じて、適切なフレームワークを選んで使い分けるといいでしょう。
人材育成にフレークワークを活用する注意点
人材育成でフレームワークを活用する際に、注意しておきたい点をご紹介します。あらかじめ注意点を把握し、失敗やトラブルを避けられるようにしておきましょう。
短期的に大きな成果が出るわけではない
フレームワークを活用した場合でも、人材育成は、中長期的に取り組むことで成果が見えてくるものです。短期間で大きな成果が出ると誤解しないようにしましょう。
従業員の知識やスキルは、すぐに身につくものではありません。人材育成によって新たな知識やスキルを覚えたとしても、業務の中で安定して活かせるようになるまでは時間がかかります。急速な成長やスキルアップを求めるのではなく、長い目で人材の成長を見守りましょう。
フレームワークに頼りすぎない
フレームワークを活用することで、人材育成をより効率的に進めやすくなります。しかし、フレームワークに沿うことを意識しすぎるあまり、突発的なトラブルに対して適切に対応できない可能性もあります。
人材育成では、あくまでも経営目標とリンクした人材育成計画を実行することが求められます。人材育成計画に遅れが生じてしまわないよう、フレームワークに沿って人材育成に取り組む場合も臨機応変に対応できるようにしましょう。
人材育成はタレントマネジメントシステム活用も
人材育成は、フレームワークを活用すると合理的に進められるでしょう。しかし、フレームワークの活用だけで人材育成が成功するとは限りません。
人材育成では、人材課題を明確にしたり、人材育成の対象を選定したうえで取り組むことが大切です。そのためにも、まずは従業員のスキルデータの把握が重要でしょう。膨大な従業員情報の把握や管理をするためには、システムで効率化するのがおすすめです。
そこで注目したいのがタレントマネジメントシステムです。タレントマネジメントシステムは、経営目標の達成に必要な戦略人事をサポートする機能が備わったシステムです。
人材育成において、従業員一人ひとりのスキルを把握しやすくなり、個々に適した育成計画の策定に役立つでしょう。組織全体のスキルの過不足も見える化できるため、全体的な育成課題を明らかにする分析や、経営目標を踏まえたうえでの育成に取り組みやすくなるはずです。
タレントマネジメントシステムなら『スマカン』
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、スキル管理や人材育成計画の立案もサポートするクラウドツールです。
従業員一人ひとりが持つスキル情報をシステム上に集約して一元管理しながら、従業員のさらなるスキルアップや具体的な人事育成施策の検討などに効果的です。
集約した情報をもとに、分析機能を活用すると、人材育成における課題解決への近道にもなるでしょう。
『スマカン』は、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織力の強化につなげられるでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
人材育成にフレークワークを活用することで、秩序立てて取り組めるというメリットがあります。何も構想や案がないゼロの状態から始めるよりも、効率的に進められるでしょう。
人材育成にかかわるもの以外にも、フレームワークにはさまざまな種類があるため、より自社の育成目的に沿った適切なものを選ぶことが大切です。まずは自社が育てたい人材像を明確にし、最適なフレームワークを見つけるようにしましょう。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!