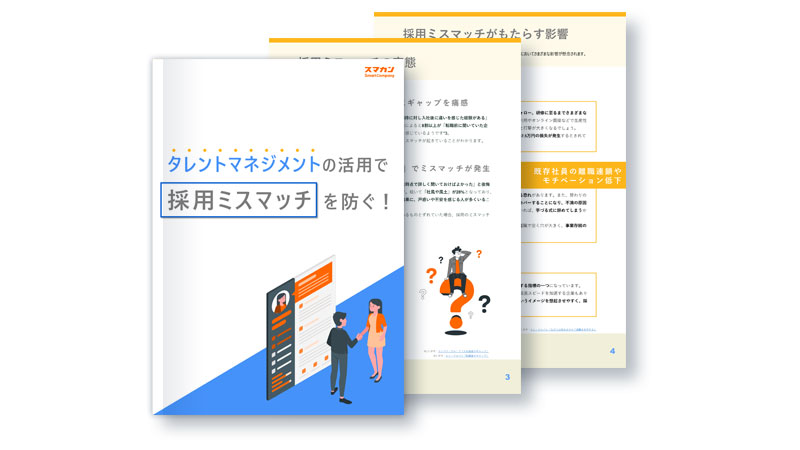- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材採用
ミスマッチとは? よくある事例や原因と対策、対処法を解説

関連資料を無料でご利用いただけます
ビジネスでの「ミスマッチ」とは、企業側のニーズと従業員側のニーズが合致していない状態を意味します。採用活動における「採用ミスマッチ」を指すことが多いですが、「異動ミスマッチ」「人材ミスマッチ」という使い方もあります。
企業としてミスマッチを放置すると、従業員の生産性やモチベーションが低下し、人間関係の悪化を招くなどデメリットが生じるため、可能な限り対処したいところです。
本記事では、ビジネスにおけるミスマッチを中心に、言葉の意味と引き起こされるデメリット、原因と対策を紹介しています。従業員との関係性に悩みを抱えている、企業の経営者や人事採用担当者はぜひ参考にしてください。
>>>ミスマッチ防止にも役立つタレントマネジメントシステム活用法
目次(タップして開閉)
ミスマッチとは
ミスマッチ(mismatch)とは、「不釣り合い」もしくは「釣り合っていないものを組み合わせる」という意味の英語です。そのような状況は、日常のさまざまな場面で考えられます。
ミスマッチはいい意味として「あえて不釣り合いなものを組み合わせて新しさを追求する」場合もありますが、ビジネスでは否定的に用いられるのが一般的です。たとえば、「企業が求める内容と従業員が求める内容が釣り合っていない」という状況が挙げられるでしょう。
ミスマッチと離職率
企業ニーズと従業員のニーズのミスマッチは、離職の原因につながります。厚生労働省の発表によると新卒入社後3年以内の離職率は、高卒者で36.9%、大卒者で31.2%と報告されています。つまり約3人に1人が、入社して3年も経たずに早期で離職しているのです。ミスマッチをできるだけ避けることが、企業の課題といえるでしょう。
参照:『新規学卒就職者の離職状況を公表します』厚生労働省HP
| 関連記事 離職率が高い企業の特徴 |
アンマッチとの違い
ミスマッチとよく似た言葉に「アンマッチ(unmatch)」があります。アンマッチとは「一致しない」「対応しない」という意味です。
ミスマッチは組み合わせたうえで釣り合っていない状態を指します。一方アンマッチは、釣り合わないために、そもそも組み合わせられない状態です。
採用活動に即して具体例を挙げると、ミスマッチは採用後に企業と従業員との間に生じるギャップ、アンマッチは条件が合わず採用できる人が見つからない状態といえるでしょう。2つの言葉は、同じような意味で使用される場合もありますが、厳密には少しニュアンスが違います。
| ミスマッチ | アンマッチ |
|---|---|
| 組み合わせた結果、合っていない | 組み合わせが、うまくいかない |
| 雇用後に発覚 | 雇用前に発生 |
企業におけるミスマッチの種類【よくある事例】
企業と従業員の間のミスマッチには、さまざまな種類があります。主なパターンとして、よくある5つの事例をご紹介します。
人間関係のミスマッチ
ミスマッチの種類1つめは、入社後に起こりがちな人間関係のミスマッチです。
エン・ジャパンの調査によると、退職理由の本音としてもっとも多かったのは「人間関係が悪かった」でした。新入社員は選考段階で採用担当者としか話す機会がないことも多く、いざ入社すると職場の上司や同僚と相性が合わなかったという事例も耳にします。
企業側から見ても、面接では好印象で採用した中途採用の社員が、実際に働き始めると、周囲と問題を起こしてしまったという事例もあるようです。
人間関係は入社してみないとわからないですが、採用時はスキルや経験だけでなく、部署やチームの雰囲気に合いそうな人柄などを見極めるといいでしょう。
待遇や働き方のミスマッチ
待遇や働き方のミスマッチも、人間関係と同様に発生しやすいミスマッチの種類として挙げられます。
たとえば、従業員側の意見として「思っていたよりも賞与の額が少なかった」「聞いていた話と違って残業時間が多かった」という声が上がるケースです。
待遇や働き方のミスマッチは、人事担当者から伝える情報が不足していたり、求職者側が勘違いしていたりすると発生しやすいです。求職者は立場上、遠慮して待遇について踏み込んで聞けないケースもあるため、入社前にフランクな話し合いの機会を設け、相互理解を深めるようにして防ぐようにしましょう。
企業風土や文化のミスマッチ
ミスマッチの種類3つめは、企業風土や文化のミスマッチです。
具体的な事例としては「経営層の権力が強くトップダウンな組織だった」「成果主義・個人主義の考え方が強く、プレッシャーが大きい」などの声が上がるケースです。入社前に抱いていた印象と実態が異なると感じた場合、退職につながる可能性もあります。
企業風土や文化のミスマッチは、たとえ入社後に違和感があっても丁寧に説明すると、わだかまりが解消されやすい項目とされています。担当者として入社後のオンボーディングなど支援する体制を整えることが大切です。
業務内容やキャリアのミスマッチ
業務内容やキャリアに対するミスマッチは、新卒者や未経験者、異動や配置転換の際に起こりやすい食い違いといえます。「異動ミスマッチ」という言葉を耳にしたことがある方もいるでしょう。
たとえば、従業員が新しく配属された部署で「自分がやりたかった仕事ができない」「思い描いていたキャリアを歩めなさそう」という感情を抱く場合です。中途入社に比べて、業界や仕事の内容に関する理解が浅いことが要因の一つとして考えられます。
従業員の自己分析や企業研究不足は企業側で補いきれない要素です。しかし会社として、個々の業務やキャリアパスについて理解する姿勢を見せるとともに、社員が将来を想像しやすくなるような情報を提供すると避けられる可能性もあります。
能力や適性のミスマッチ
ミスマッチの種類5つめは、能力や適性のミスマッチです。企業側が「人材ミスマッチ」と使用する場合、能力や適性を指していることが多いでしょう。
能力や適性のミスマッチは、そもそも従業員の能力や性格が「求める業務をこなすうえで足りない」「期待するスキルレベルに達していない」というケースです。このようなすれ違いは、仕事がスムーズに進まないのはもちろん、本人のモチベーションを下げてしまうことになりかねません。まずは採用活動において選考の段階で、スキルや適性が不十分な人材を採用しないことが大前提です。社内の人材においては、日頃より本人のスキルや能力を把握し、配置シミュレーションを実施したうえで、適材適所に異動を行うことが重要です。
ただし能力や適性のミスマッチは、入社後の教育や研修によって、従業員のスキルを求める水準まで引き伸ばしたり、本来の能力が発揮できる部署に配置転換したりすることでカバーできる場合もあるでしょう。
ミスマッチによる企業側のデメリット
採用ミスマッチをはじめ、企業と従業員のすれ違いを放置すると、どのようなデメリットがあるのでしょうか。企業側のデメリットを3つ確認してみましょう。
従業員のモチベーションの低下
ミスマッチを感じた従業員は、働くモチベーションが低下してしまいます。「自分の求めている待遇や働き方が叶わない」「自分の適性やスキルに合っていない仕事を求められる」というマイナスの気持ちのままでは、業務効率やパフォーマンスが落ちます。その結果、生産性が低下して十分な成果も出せず、評価にもつながらないという悪循環が生まれてしまうでしょう。心身に不調をきたして休職に追い込まれるケースもないわけではありません。
ミスマッチを感じた従業員を放っておくことは、会社の業績や成長が伸び悩むことにもつながり、最終的に企業側の損害になるという意味でデメリットになり得ます。
社内の人間関係の悪化
ミスマッチを感じてモチベーションが低下している従業員は、周りの同僚にもマイナスの影響を与えることがあります。これまでは会社に対して不満を抱いていなかった従業員も愚痴や相談を聞くことで、だんだん不信感が芽生えていくかもしれません。また、従業員の中でモチベーションに大きな差が生まれると、足並みが揃わなくなって衝突が起こりやすくなります。
ミスマッチは従業員個人の問題ではなく、会社全体のチームワークの乱れや生産性低下にもつながるということです。
早期離職による採用コストの損失
入社後にミスマッチを感じ、それが解消されることはないと考えた従業員は、働いた期間にかかわらず退職してしまう可能性があります。そうすると従業員の採用と教育にかけたコストはすべて無駄になってしまうでしょう。
エン・ジャパンの調査では、社員1名が入社後3か月で離職した場合には、概算で187.5万円もの損失が出るという試算がされています。
ミスマッチの原因と対策
企業と従業員のミスマッチを防ぐために、ミスマッチが起きてしまう原因と対策を3点ご紹介します。
募集段階でミスマッチが起きる原因と対策
ミスマッチを防ぐうえで、まず重要なのが募集の段階です。募集する際に、業務内容や待遇、働き方などに関する情報の開示が不足していると、従業員との認識のズレが生まれる原因になります。マイナスな印象を与えそうな情報を隠し、よいところだけ見せようとする姿勢も大いに影響するでしょう。
またミスマッチの原因としてよく起こるのが、経営陣と現場の認識の相違です。経営陣や人事が設定した人材要件が現場が求めているスキルや適性と一致しておらず、結果としてズレが発生するパターンです。
| 関連記事 人材要件の作り方とは? |
面接でミスマッチが起きる原因と対策
ミスマッチは、採用での面接の段階で、候補者と綿密にコミュニケーションをとり、お互いに理解を深めておくことを怠ると発生します。応募者のアピールを鵜呑みにしてしまったり、経歴やスキルばかりに気をとられてしまうなど、適性を見極められていないケースが原因の一つでしょう。ほかには、業務内容や待遇の話に終始してしまい、企業の理念や文化についての理解を得られない場合も同様です。
入社後にミスマッチが起きる原因と対策
徐々にミスマッチを感じてしまうケースもあります。たとえば入社した直後はそこまで不満はなかったものの、会社の制度変更や配置転換による上司や業務内容の変更が、不満の火種になるのです。
ミスマッチを防ぐには、入社後に認識のズレや不安をなくすようフォローすることが大切です。募集や面接の段階で、企業理念や風土、働き方について伝えておくことも大事ですが、従業員が入社したあとには改めて丁寧な説明が必要になるでしょう。
ミスマッチが起こってしまったら?|対処法
ミスマッチを防ぐための原因と対策をお伝えしてきましたが、注意していてもミスマッチが起こってしまったとき、どうすればいいのか対処法を3点ご紹介します。
できるだけ募集段階でミスマッチを防ぐ
まず、ミスマッチが起きたあとに対処するのは非常に難しいことを理解しておきましょう。会社に対して不信感を抱いている従業員の気持ちを変えるのは、そう簡単ではありません。すでに退職の意思が固まっているなら、なおさら難しいでしょう。また、スキルや適性が求める基準に達していない従業員がいたとしても、企業側の一方的な都合で辞めさせることはできません。
そこでミスマッチが起こらないように、できるだけ採用の段階で注意しておくことが何より重要なのです。そこで面接官の判断スキルを高める研修を行うなど、採用効率を高める配慮が第一のポイントといえます。
ミスマッチが起きてしまったら原因を究明する
それでもミスマッチが起きて企業と従業員の認識にズレが発生したら、どうするべきなのでしょうか。まずは可能な限り丁寧な説明やフォローをしましょう。それで両者の溝が埋まるなら一番です。
ただしミスマッチの原因を検討することを忘れてはいけません。それがわかっていなければ、同じようなことを繰り返してしまいます。
ミスマッチが起きてしまったら、原因を究明して次に活かしていくことが大切です。
タレントマネジメントシステムを活用する
ミスマッチが起こってしまったあとの対処法の3つめとして、タレントマネジメントシステムの活用をご紹介します。
タレントマネジメントシステムとは、経歴やスキルなどの人材情報を一元管理して、人事業務の効率化や人事施策への活用をサポートするツールです。社内で活躍している人材の特徴を分析して採用基準を明確にしたり、人材データをもとに希望や適性にあわせた人材配置を実施したりなど、活用方法は課題によってさまざまです。
特に採用ミスマッチの防止に役立てる使い方も注目されており、導入を検討するのも一案です。アンケートやサーベイ機能を使って実施を簡略化し、ミスマッチにつながる予兆を見つけるなどの活用方法もあります。
ミスマッチ防止にタレントマネジメント導入も
ミスマッチとは、企業側のニーズと従業員側のニーズが合っていない状態のことです。
採用ミスマッチが起きると、従業員のモチベーションや生産性が低下したり、早期離職によって採用・教育コストの損失につながったりしてしまいます。挽回するのは大変なので、タレントマネジメントシステムを活用するなど、事前に対策を打ち、面接官の評価スキルを底上げしておくことが望ましいでしょう。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、従業員一人ひとりの能力や適性を、顔が見える状態で見やすくまとめるクラウドツールです。スキルや適性を可視化して採用すべき人物像の明確化や活躍人材の発掘に役立つでしょう。
『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!