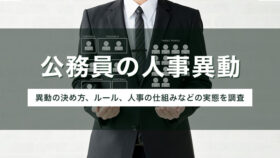- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
シエスタの意味とは|制度の内容や最適な昼寝時間、メリット・デメリットも解説

関連資料を無料でご利用いただけます
スペイン語であるシエスタ(siesta)は、日本語で「日の出から6時間後=正午前後」や「昼寝」を意味します。気温の高いラテンの国々では、日中に効率よく働けないことを理由に、午後から夕方までの暑い時間を休み時間としたことがはじまりとされています。
日本におけるシエスタ制度とは、昼休みを長時間設ける制度です。この間に、従業員が仮眠をとったり気分転換したりすることで、休憩後の生産性やパフォーマンスを高めることを目的としています。
本記事では、シエスタの意味やシエスタ制度の導入によるメリット・デメリット、実際にシエスタ制度を運用している企業事例などを解説します。人事・マネジメント担当者や経営者はぜひチェックしてみてください。
目次(タップして開閉)
シエスタの意味はスペイン語で「昼寝」
そもそもシエスタ(siesta)は、スペインをはじめとしたラテンの国々が発祥とされており、日本語で「日の出から6時間後=正午前後」や「昼寝」を意味します。
シエスタ制度の始まりは、スペインの夏の暑さが影響しています。最も気温の上がる正午過ぎには40度を超えることもあり、効率的に仕事を進められないことから、長い昼休みを設けるようになったのです。
そのため、シエスタが文化として根づいているイタリアやスペインなどでは、正午過ぎから夕方までを休業時間とする企業が多いとされています。
また、シエスタの時間は昼寝だけに使われるのではなく、自分の趣味活動や家族との時間など、リフレッシュの時間として使われることも多いようです。
シエスタ制度(昼寝制度)とは
シエスタ制度とは、企業が昼休みを通常よりも長く設け、従業員にリフレッシュを促す制度です。一般的に昼休みは1時間程度で設定されますが、シエスタ制度では、2〜3時間ほど設けられることが多いとされています。
また、この時間を利用して昼寝の推奨をすることが多いため「昼寝制度」や「パワーナップ制度」と呼ばれることもあります
シエスタ制度の導入目的
シエスタ制度の目的は「生産性を高めること」です。
人間は体内時計によって、昼食後の午後2時頃に最も眠気を感じやすいといわれています。そのため、昼食をとったあとに眠気に襲われる人も多いのではないでしょうか。
この眠気を感じやすい時間に、無理に活動せず昼寝をすることで、午後も集中力を高いまま維持でき、仕事の生産性を低下させずに業務に取り組めるとされているのです。
| あわせて読みたい【関連記事】 労働生産性とは|計算式や生産性向上の方法も徹底解説! |
シエスタ制度が日本で注目されている理由
シエスタ制度への注目が高まる理由として「働き方改革の推進」が挙げられるでしょう。
働き方改革により、企業は就業時間内にできる限り生産性を高め、短時間で大きな成果を出すことへの重要性が高まっているのです。
2014年に厚生労働省は、午後の早い時間に30分程度の短い昼寝をすることで、そのあとの作業効率の改善に役立つと発表しました。
これらの理由や、日本企業によるシエスタ制度導入の影響もあり、日本でも徐々にシエスタ制度が注目されるようになったといえるでしょう。
| あわせて読みたい【関連記事】 働き方改革とは【今更聞けない基礎】 |
シエスタ制度における過ごし方
企業でシエスタ制度を取り入れる場合、過ごし方は基本的に従業員の自由です。
シエスタの使い方を昼寝だけに制限してしまうと、別のストレスを感じさせてしまい、リフレッシュの恩恵を受けられない可能性があるからです。
仮眠をとるほかにも、趣味や余暇、運動、読書、家族団らんなど、従業員それぞれがやりたいことを行う時間としましょう。
シエスタ制度における勤務時間
シエスタ制度を導入した場合、終業時刻を約2時間延長するケースが多いようです。
たとえばシエスタを約3時間設けた場合、本来の休憩時間である1時間に、2時間プラスされることになります。そのため、もともと18時だった終業時刻が20時に繰り下がるということです。
| 本来の就業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|---|
| シエスタ | 3時間(休憩時間1時間を含む) |
| シエスタ導入時の就業時間 | 9:00〜20:00 |
| あわせて読みたい【関連記事】 勤怠管理とは|基礎知識や注意点を解説 |
シエスタ制度の最適な昼寝時間
世界的にみるとシエスタの時間は、3時間としている企業が多く、日本においては1時間半〜2時間としている企業が多いようです。ただし、時間やシエスタの開始時刻は企業によって異なります。
シエスタには、家族団らんや自身の趣味活動、昼寝など、従業員によってさまざまな過ごし方が挙げられるでしょう。
そのなかで、午後を乗り越えるために昼寝をしたいと考えた場合、最適な仮眠時間はどれくらいなのでしょうか。仮眠時間の長さによって得られる効果をご紹介します。
| 仮眠時間 | 得られる効果 |
|---|---|
| 10〜20分以内 | 病気の発症リスクを低減させ、起床後の作業効率が上がる |
| 30分以上 | 熟睡モードに入ってしまい、眠気や倦怠感が残る |
| 1時間以上 | 生活リズムが乱れたり、病気の発症リスクが上がる可能性がある |
10〜20分以内
午後に昼寝をする場合、正午から15時までの間に10〜20分以内で行うことが最適であるとされています。
20分以内が最適である理由は、深い睡眠(ノンレム睡眠)に切り替わる前の浅い睡眠(レム睡眠)にとどめることで脳が睡眠モードに入る前に起きることができるためです。
眠気を引きずらずに起きることができ、午前の疲れをリセットしたり、午後の作業効率が向上したりする効果を得られるでしょう。
ほかにも、仮眠時間を20分以内に収めることで、病気の発症リスクを低減させることができることも発表されています。
30分以上
昼寝が30分以上経過すると、熟睡モードに入ってしまいます。
熟睡モードに入ると、すっきりと起きることができません。無理に起きたとしても、午後に倦怠感や眠気が残る状態で仕事や作業を行うことになり、逆にパフォーマンスが落ちてしまうことが考えられるでしょう。
1時間以上
1時間以上昼寝をしてしまうと、浅い睡眠(ノンレム睡眠)から深い睡眠(レム睡眠)に切り替わり、目覚めた時にだるさを感じます。
起きたとしてもすぐに動き出すことが難しかったり、夜に寝つきづらくなることで生活リズムの乱れや睡眠不足につながったりして昼寝の効果を得られないでしょう。
また「昼寝はいつも1時間以上してしまう」というような長い昼寝の習慣がある人は、昼寝の習慣がない人と比較して、心血管疾患の発症リスクが高いことが報告されています。
参考:『「1時間超の昼寝は死亡リスク3割上昇」の衝撃事実』東洋経済オンライン(2021)
シエスタ制度の効果・メリット
シエスタ制度を導入すると、従業員と企業ともに多くのメリットを得ることができます。具体的に、どのような効果やメリットが得られるのでしょうか。
| ・従業員のモチベーションが高まる ・企業イメージが向上する ・勤務時間の柔軟性が高まる ・ゆっくりと昼食をとれる ・夏の暑い時間に仕事をせずに済む ・ストレスを解消できる ・体力や集中力の回復ができる |
従業員のモチベーションが高まる
シエスタ制度の適切な運用によって、従業員のモチベーション向上につながります。
昼休みにしっかりとリフレッシュできれば、頭がすっきりと冴えた状態で午後から効率よく仕事が行えるため、従業員のモチベーションを高められるのです。
また、シエスタの過ごし方を自由に決められることで、仕事に対する心身のストレスが軽減され、企業に対する満足度向上も期待できるでしょう。
| あわせて読みたい【関連記事】 社員のモチベーションを向上させる方法と施策|事例を交えて紹介 |
企業イメージが向上する
シエスタ制度を導入すると、企業イメージの向上が期待できます。
ホームページや採用サイトで公表することで、外部の人に「先進的なシステムを導入している企業」や「従業員の健康状態を気にかけている企業」という魅力的なイメージを与えられるためです。
また、健康経営の推進や優秀な人材の確保を目指している場合にも、シエスタ制度は有効といえるでしょう。
| あわせて読みたい【関連記事】 今からでも遅くない【健康経営】とは? |
労働時間の柔軟性が高まる
シエスタ制度と一緒にフレックスタイムを導入すると、労働時間が柔軟に選べるようになります。
「大きな仕事を片づけたい日はシエスタ制度を利用し、早く帰宅したい日は利用しない」という選択もできるため、従業員が働き方を自由に選択できます。
また、昼間に長い休み時間を確保できることで、家事と仕事を両立しやすくなり、従業員エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
従業員一人ひとりの希望に適したフレキシブルな働き方が実現できることで満足度向上や離職防止など、企業にとって嬉しいメリットが得られるのです。
ゆっくりと昼食をとれる
シエスタ制度によって昼休みが長時間与えられると、昼食をゆっくりと食べられます。
健康に気を遣った食事ができたり、今まで余裕がなくて足を運べなかった飲食店でランチができるようになったりするでしょう。
ランチをともにする同僚や後輩、家族、友人と、時間を気にせずおしゃべりができる点もシエスタ制度のメリットの一つといえます。
夏の暑い時間に仕事をせずに済む
気温が上がる夏の午後に休憩できる点も、シエスタ制度の魅力です。
年々気温が上昇する夏日には、熱中症や脱水症にも注意しなければなりません。営業などの外出が多い職種の人には、夏の午後の外出がつらいという方が多いのではないでしょうか。
シエスタ制度を活用すれば、最も暑いお昼過ぎの時間を避けて、比較的過ごしやすい午前中や夕方に外出予定を組むなどのスケジュール調整ができるようになるでしょう。
ストレスを解消できる
シエスタ制度をうまく活用できれば、蓄積したストレスの解消が見込めます。
休み時間の使い方を従業員自身が選択し、自身のストレス解消に費やすことで気持ちを切り替えて仕事に取り組めるのです。
ストレス解消の方法は人によってさまざまですが、好きなものを食べることや、親しい友人や家族と話すこと、仮眠、運動、趣味活動などが挙げられるでしょう。
ストレス社会といわれる昨今では、ストレスを我慢して仕事や生活し、最終的に精神疾患に悩まされてしまう人も少なくありません。自社の従業員をそういった事態に陥らせないためにもシエスタ制度の導入は有効です。
| あわせて読みたい【関連記事】 ストレスチェックとは【簡単に】義務化の背景や目的、実施方法を紹介 |
体力や集中力の回復ができる
シエスタ制度の長い休み時間は、気分転換に最適です。
体力や集中力はどんなに鍛えても長く維持することは難しいでしょう。適度に休憩を挟まなければ、気づかないうちに体を酷使してしまったことによる慢性的な疲労や体調不良にもつながりかねません。
少し昼寝をするだけでも、体力や集中力は十分回復できるとされています。
シエスタ制度の導入によって、今までなかなか休憩を取れなかったという人でも、自分を労わりエネルギーチャージする時間をつくれるのもメリットの一つです。
シエスタ制度のデメリットと対策
シエスタ制度によって考えられるデメリットと対策をご紹介します。シエスタ制度の導入を検討している場合は、メリットだけでなく、デメリットも把握して対策を練っておくとよいでしょう。
| ・体内時計が乱れやすくなる ・頭痛が起きやすくなる ・退勤時間が遅くなる |
体内時計が乱れやすくなる
日中に昼寝の時間を挟むと、体内時計が乱れる恐れもあります。
そのため昼間に寝すぎると、夜の寝つきが悪くなり、睡眠の質を下げる原因となるのです。適切な睡眠時間がとれるように、企業側の配慮も検討してみるとよいでしょう。
たとえば、数十分の昼寝に向いているリクライニングチェアを用意したり、長時間の昼寝がもたらすデメリットを従業員に周知したりするなどが挙げられるでしょう。
体内時計が乱れてしまうと、企業が期待しているシエスタ制度のメリットを得られないため、従業員と企業がともに注意したいところです。
頭痛が起きやすくなる
シエスタ中に仮眠を取ると、頭痛に悩まされる人もいるようです。
昼寝から目覚めたときに、血管の拡張しすぎにより血流量が増えることで、強い痛みを感じてしまう人もいます。そのほか、寝るときの姿勢が悪いことも頭痛の原因の一つです。
会社で昼寝を推奨する場合には、椅子に座ったままでも姿勢が悪くならないように寝られる簡易枕の支給などを検討してみるとよいかもしれません。
シエスタ制度の導入によって、健康を損ねる従業員が発生していないかどうか、企業側が確認するようにしましょう。
退勤時間が遅くなる
シエスタ制度を導入すると、退勤時間が後ろ倒しになってしまいます。
昼休みは長く確保できる一方、業務量が多い従業員や会社から自宅が遠い従業員は、退勤時間や帰宅時間が遅くなることが懸念されるでしょう。
健康経営の一環としても有益なシエスタ制度を導入したにもかかわらず、夜の睡眠時間が取れなかったりプライベートの時間を確保できなかったりしては、逆効果となってしまいます。
あらかじめ業務量の精査を行ったり、フレックス制度や時短制度との併用を認めたりするなどの工夫を行うとよいでしょう。
| あわせて読みたい【関連記事】 健康経営の取り組み事例7選|大企業から中小企業、ユニーク事例まで |
シエスタ制度を導入した企業事例
日本において、シエスタ制度を導入した企業を見ていきましょう。企業事例をもとに自社に取り入れられることはないか検討してみてください。
三菱地所株式会社
不動産事業を主に取り扱う三菱地所株式会社は、2018年にパワーナップ制度の導入を開始しました。昼休みの1時間とは別に30分間の仮眠を推奨する、パワーナップ制度の導入目的は、生産性の向上です。
同社は、移転のタイミングで本社に仮眠室を備え付けました。仮眠室には、午後の業務を邪魔しない適度な睡眠がとれるように工夫された、リクライニングチェアが設置されています。
パワーナップ制度を社内に根づかせるために、フリーアドレス化や根気強く制度活用を推奨し続けることで、従業員の意識改革に成功しました。
結果として従業員が業務効率や生産性の向上を実感しているということから、シエスタ制度のメリットである、生産性の向上や集中力の回復に寄与しているといえるでしょう。
参考:『仮眠30分で業務効率アップ 三菱地所が導入した「パワーナップ制度」とは?』厚生労働省
株式会社ヒューゴ
ITコンサルタント企業の株式会社ヒューゴは、毎日13〜16時の間に3時間の昼休みを2007年頃から設けています。従業員は仮眠をとったあと、ジムでのエクササイズやオフィス近辺の散歩、映画鑑賞など好きなことをして過ごすそうです。
シエスタ制度を導入することで、5年間の売り上げは5倍以上に伸び、ケアレスミスや残業時間が大幅に減少したといいます。また、2018年から始まったフレックス制度との併用も相まって、中途採用の応募者も増加したようです。
参考:『日本経済新聞社様よりシエスタ制度(社内の昼寝)とリモートワークについて取材いただきました。』株式会社ヒューゴ
GMOインターネット株式会社
通信事業を営むGMOインターネット株式会社は、2011年より会議室を「おひるねスペース」として12時30分から13時30分まで開放しています。仮眠室内には、昼寝用の簡易ベッドやアイマスク、耳栓が完備されており、20分程度の昼寝を推奨しています。
同社がシエスタ制度を導入した目的は、従業員が頭をクリアにし、クリエイティブな発想を生み出す助けをすることです。
また、予約制の仮眠室やプロによるマッサージを業務の合間に格安で受けられるボディケアサービスのの設置は大きな特徴といえるでしょう。
シエスタ制度を導入する際の注意点
シエスタ制度を実際に導入してみたいと考える企業は、下記のような注意点に気をつけて導入準備を進めるとよいでしょう。
| ・制度の利用は選択式にする ・業務に影響が出ないように配慮する ・睡眠がとれる環境を整備する |
制度の利用は選択式にする
シエスタ制度の利用は、各従業員の希望に合わせて選択できるようにしましょう。
シエスタを利用すると自動的に退勤時刻が遅れるため、早く帰宅したい人は迷惑や不満に感じ、業務へのモチベーションが低下してしまうかもしれません。
制度の導入が、かえって生産性を低下させてしまわないか、社内アンケートを実施したり、任意で利用できるようにしたりするなど、よく検討することをおすすめします。
| あわせて読みたい【関連記事】 社内アンケートとは? 実施のコツやポイント、ツールもご紹介 |
業務に影響が出ないように配慮する
シエスタ制度の導入によって業務に影響が出ないように、細やかな配慮も必要です。
特に、取引先に対しては事前の連絡が求められます。連絡がとれなくなる時間を、制度の導入時に前もって伝えておくと安心でしょう。取引先へ対応できるよう、シエスタ時間中に業務連絡を担当する人材を、外部から雇用するのも一案です。
また社内への配慮として、シエスタを利用する前にほかの従業員にひと声かけるなどの配慮を行うとよいでしょう。
睡眠がとれる環境を整備する
シエスタ制度の効果を最大限に引き出すためには、リラックスして睡眠がとれる環境を整えることが重要です。
毎回同じ姿勢で仮眠すると、質の高い睡眠がとれるといわれています。仮眠室や仮眠用のベッド・リクライニングチェアなどを設置し、従業員が気兼ねなく休息をとれるようにしましょう。
ほかにも、雑音によって従業員の休息が遮られないよう、会議室や業務用のフロアから離れた場所にするなどの配慮も重要です。
シエスタ制度は発祥スペインで廃止の動きも
ここまでシエスタ制度の概要をご紹介してきましたが、スペイン本国では廃止の動きもあるようです。その理由は、早く帰宅したい人が増えているからです。
シエスタ制度には、メリットとデメリットがあります。それぞれをよく理解したうえで、自社の目的に応じて導入の有無を決めるようにしましょう。
シエスタ制度を取り入れて生産性向上へ
シエスタ(siesta)は、日本語で「日の出から6時間後=正午前後」や「昼寝」のことです。気温の高いスペインをはじめとするラテンの国々では、暑い日中に効率よく仕事ができないため、長い昼休みを設けるようになったことがはじまりといわれています。
長時間の昼休みを設けるシエスタ制度は、日本企業でも導入されている施策です。従業員の健康を守り、業務の生産性を高める効果が期待できるとされています。
ただし、昼休みを延長する分、終業時刻が引き伸ばされるというデメリットもあります。シエスタ制度を導入する際には、制度の利用を選択式にしたり、フレックスタイム制度と並行したりするなどの工夫が必要でしょう。
シエスタ制度の導入を検討している場合は、本記事の内容をぜひ参考にしてみてください。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、人事業務の生産性向上を助けるクラウドサービスです。人材情報を一元管理し、人事業務の効率化や適正な人材配置、育成を見越したスキル管理などにお役立ていただけます。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!