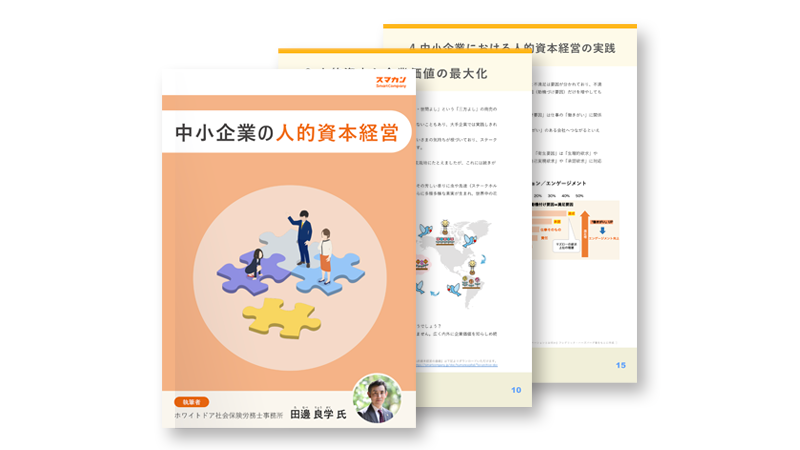- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
働き方改革の具体例や事例8選|参考になる取り組みをご紹介

関連資料を無料でご利用いただけます
働き方改革は、労働者の事情に応じて多様な働き方を選択できるような社会実現を目的とした取り組みです。柔軟な働き方へのニーズが高まっている近年、働き方改革への関心も高まっているはずです。
しかし「働き方改革の具体例が知りたい」「実は働き方改革の詳しい内容を理解できていない」という声もあるでしょう。
そこで本記事では、働き方改革の具体例を中心にご紹介しながら、働き方改革そのものや関連法案についても解説します。
目次(タップして開閉)
働き方改革とは
働き方改革とは、労働環境を見直し、労働者の事情に応じた多様な働き方を実現するための取り組みのことであり、政府が主導しています。
厚生労働省では「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、 自分で選択できるようにするための改革」と定義しています。
現在の日本では少子高齢化が進んでおり、働く能力と意思がある15歳以上の労働力人口が減少しています。さらに、介護や育児など家庭の事情と仕事の両立が難しく働けなくなったという方も多くいるでしょう。
働き方改革によって、多様な働き方を選択できる社会にすることで、労働力人口の増加を目指すという目的のもと、2019年4月から『働き方改革関連法案』が順次施行されました。
働き方改革関連法とは
働き方改革関連法とは、2019年に新たにできた法律ではありません。
労働に関する既存の法律を改正したものの総称を指します。正式名称は『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』で、該当する法律は以下の通りです。
| ・労働基準法 ・雇用対策法 ・じん肺法 ・労働安全衛生法 ・労働契約法 ・労働時間等設定改善法(労働時間等の改善に関する特別措置法) ・パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律) ・労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律) |
たとえば、労働基準法の改正により、残業時間(時間外労働時間)の上限規制、年次有給休暇の取得義務化が実施されています。
さらにパートタイム・有期雇用労働法が改正されたことにより、同一労働同一賃金をはじめ雇用形態による不合理な待遇差が禁止されるなど、労働環境の改革が多方面で進められています。
また、働き方改革関連法では、働き方改革に取り組むうえで3つの柱を立てています。
| ・長時間労働の是正 ・多様で柔軟な働き方の実現 ・雇用形態にかかわらない待遇の保持 |
参照:『「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要』厚生労働省
働き方改革の取り組み内容
働き方改革に取り組むうえでは「働きすぎ」を防がなくてはなりません。
長時間労働や有給休暇の取得を中心として、ワークライフバランスや柔軟な働き方を実現するために政府が発表した内容についてご紹介します。
| ・残業時間の上限規制 ・「勤務間インターバル」制度の導入 ・年次有給休暇の取得を義務化(年5日) ・割増賃金率の引き上げ ・労働時間把握の義務化 ・フレックスタイム制に関する制度拡充 ・高度プロフェッショナル制度の新設 ・産業医や産業保健機能の強化 |
残業時間の上限規制
残業時間の上限は、原則月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないとする規制を設けました。
またこれを超える臨時的な特別の事情がある場合は労使が合意したうえで、
| ・年720 時間以内 ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む) ・月100時間未満(休日労働を含む) ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回が限度 |
としています。
残業時間が労働者の心身の負担になりかねず、ワークライフバランスを乱す危険性もあり、明確に規定されることとなりました。
「勤務間インターバル」制度の導入
勤務間インターバル制度とは、勤務終了後に翌日の出社までに一定の休息時間を確保する仕組みです。
翌日の出勤までに休息を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間などを確保し、心身の健康バランスを保つための試みといえるでしょう。
年次有給休暇の取得を義務化(年5日)
労働者の年5日の有給取得が義務化されることになりました。
法改正前における有給休暇の仕組みでは、労働者から申し出なければならず、企業や従業員によっては希望を出しにくいケースもあり、年休取得率51.1%というデータもあるほどです。
この取り組みによって、最低でも年5日は労働者が休みを新たに確保できるようになりました。
| 関連記事 年間休日の最低ラインは105日? |
割増賃金率の引き上げ
残業に関して、月の時間外労働が60時間を超えた残業は割増賃金率の引き上げる取り組みです。
法改正前における引き上げ率は、大企業が50%、中小企業が25%でした。この取り組みによって、大企業と中小企業ともに50%まで引き上げられることになっています。
労働時間の客観的な把握を義務化
従業員の健康管理の観点から、労働時間の把握についても、客観的な方法での把握が義務化されました。
この取り組みによって、これまで労働時間の客観的な把握の対象外であった裁量労働制の従業員や管理監督者も含めたすべての従業員の労働時間の把握が必要となっています。
フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の対象期間が3か月に拡大されました。
フレックスタイム制とは、一定期間にあらかじめ決められた総労働時間の範囲で労働時間を自由に決められる制度です。
9時から17時などの定時勤務ではなく、始業と終業時間を自由に調整できるため、育児や介護など、物理的に決められた時間で勤務することが難しい従業員にとって、メリットがあります。
フレックスタイム制の対象期間が3か月に拡大したことで、3か月の中で労働時間が調整できるため、柔軟な働き方ができるようになるでしょう。
高度プロフェッショナル制度の新設
高度プロフェッショナル制度とは、専門的かつ高度な技術を持つなど、条件を満たす従業員に対して、健康確保措置を講じたうえで労働時間に関する制限を撤廃する取り組みです。
本制度によって労働基準法が適用されないことになります。労働時間にかかわらず成果や業績で賃金が決定するため、最短時間の労働で生産性を上げることも可能です。
「産業医・産業保健機能」の強化
従業員の健康を守るため、事業場に設置された産業医による従業員の健康相談を強化し、従業員に関する健康情報の取り扱いを適正化することを推進しています。
具体的には、従業員からの相談に応じて対応できるような体制を整備する取り組みや、従業員が安心して健康相談や健康診断などを受けられるよう、情報を注意して取り扱う取り組みが推奨されています。
参照:『働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~』厚生労働省
| 関連記事 勤怠管理の基礎知識や注意点 |
働き方改革の具体例【企業の取り組み】

働き方改革にともない、各企業は法律で定められた項目はもちろん「長時間労働の解消」や「多様な働き方への対応」に向けて取り組みを推進することとなりました。
具体的にどのような取り組みをすべきなのか、5つの具体例をご紹介します。
- 1.テレワークの推進
- 2.フレッタクスタイム制度の導入
- 3.柔軟な働き方を認める制度導入
- 4.ストレスチェックの実施
- 5.業務効率化の実施
- 6.労働時間の管理
それぞれについて詳しく解説いたします。
テレワークの推進
働き方改革の具体例として、テレワークの導入はわかりやすい一例でしょう。
テレワークはオフィスに出勤せず、自宅に居ながら働けるため「通勤の負担軽減」や「時間の有効活用」による生産性の向上も期待できます。
また、育児や介護などの事情を抱える優秀な人材が「通勤が難しい」という理由で、離職してしまうことを防ぐ効果もあるでしょう。
新型コロナウイルスの影響によりテレワークが浸透しましたが、さらに「ハイブリッドワーク」という、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方も注目されています。
フレックスタイム制度の導入
働き方改革の具体例として、フレックスタイム制の導入も挙げられます。
フレックスタイム制とは、決められた総労働時間の範囲で、出社と退社時間を従業員が調整できる制度です。従業員が都合に合わせて働く時間を選択できるため、家事や育児、介護との両立など、柔軟な働き方として注目されています。
働き方改革関連法により、従業員が柔軟な働き方を選択できるように、フレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に延長可能となりました。
なお、清算期間の設定が1か月以上となる場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署への届け出が義務づけられています。違反した場合は罰則の対象となるので注意しましょう。
柔軟な働き方を認める制度導入
働き方の具体例として、従業員にあった柔軟な働き方を認める制度導入も挙げられます。従業員の中には、育児や介護などさまざまな事情で働ける時間が限られている人もいるでしょう。
育児休業の取得を推進・フォローし、時短勤務制度を取り入れると、より多くの従業員が安心して働けるようになります。
特に近年注目された、父親による「産後パパ育休」は通常の育児休業とは別に休暇が取れる制度です。男性の育児休暇取得を促進することで、女性もさらなる活躍が期待できるでしょう。
このように、日頃から従業員同士がフォローし合える職場環境をつくっておくことが、育児休暇の取得促進につながるポイントです。
ストレスチェックの実施
働き方改革の具体例として、従業員の心の健康を守るため「ストレスチェック」の実施も効果があるでしょう。
ストレスチェックとは、従業員が自身のストレス状況について回答するアンケート調査のことです。従業員に結果を通知し、自分の抱えるストレス状況に気づいてもらうことで、メンタルヘルスの深刻な不調を未然に防ぐのが目的です。
2015年より、従業員が50名以上の企業ではストレスチェックが義務づけられており、50人未満の企業は努力義務とされています。大企業のみならず、中小企業でもストレスチェックの導入が求められるようになりました。
| 関連記事 ストレスチェックの義務化とは? |
業務効率化の実施
働き方改革の具体例には、ペーパーレス化やDX化などによる業務効率化も挙げられます。
業務効率化が実現することによって、従業員の残業時間が減り、休日が取得しやすくなるなど、ライフワークバランスを整えられます。
また、テレワークなどをはじめとして、オフィスへの出勤にこだわらない働き方を採用するためにも、システムを活用して業務を進められるような環境を整えることが必要でしょう。
| 関連記事 業務効率化の成功事例 |
労働時間の管理
働き方改革の具体例として、労働時間の管理も重要な取り組みの一つです。
働き方改革の推進で、時間外労働の上限も明確に定められました。従業員の労働時間を適切に管理することで、残業時間を減らし、休暇の取得を促進できるでしょう。
| 関連記事 時間外労働とは? ルールや定義 |
働き方改革の具体例【企業事例】
すでにさまざまな企業が働き方改革に取り組んでいます。そこで、経団連が発表した『働き方改革アクションプラン』で紹介された企業の事例をもとに具体例をご紹介します。
味の素株式会社
味の素株式会社では、2019年度の働き方改革実現のKPIとして
| ・年度平均総実労働時間1800時間以下 ・年度平均有休取得日数 19日以上 ・テレワークデイズの設定と当該期間の利用率100% |
を設定しました。
実現に向けた行動計画として、
| ・部署ごとの労働時間などを目標化 ・本社の消灯時間を設定 ・有給取得目標の設定 ・社内資料を完全ペーパーレス化 ・フリーアドレスの展開 |
などを策定しました。
キヤノン株式会社
キヤノン株式会社では、2019年度のKPIとして
| ・年間総実労働時間1,800時間以下の継続 ・全従業員に年次有給休暇5日以上取得させる ・男性の出産および育児に関する休暇・休業の取得率9割以上を維持 |
を掲げています。
実現に向けた行動計画では、
| ・労使専門委員会を通じた実績確認と施策 ・年休連続取得促進策の継続やリフレッシュ休暇の取得徹底 ・男性が育児に参画しながら就業しやすい環境を整備 |
などを策定しました。
働き方改革による企業側のメリット
働き方改革により、企業が対応すべきことが増え、負担に感じる担当者の方もいるかもしれません。しかし、働き方改革は企業にもたらす多くのメリットがあります。
働き方改革が企業にどのようなメリットをもたらすのか、わかりやすく解説します。
労働生産性の向上
働き方改革の推進に向けて、テレワークの導入やITツールの活用を強化した企業もあるでしょう。
これにより確保できた時間をコア業務に充てたり、手作業で時間をかけて行っていた業務をITツールで簡略化したり、業務効率化につながっています。
従業員が柔軟に働き方を選択できることで、より働きやすい環境が生まれ、労働生産性の向上につながるのは大きなメリットといえるでしょう。
求職者へのアピールと人材確保
働き方改革を進めることで、より働きやすい会社だという点を求職者へアピールでき、結果的に人材確保につながります。
残業時間の少なさや休暇取得のしやすさ、働く場所などは、多くの求職者が注目する点です。企業が働き方改革に積極的に取り組むことで、働きやすさに魅力を感じた優秀な人材の確保が期待できるでしょう。
残業時間の削減によるコスト抑制
働き方改革によって残業時間を削減できれば、人件費や電気代などのコストを抑制できます。
コストを抑制できれば、利益率によい影響が出たり、ほかの予算に充てられたりなど、企業にとって大きなメリットになるでしょう。
働き方改革にはシステム活用がおすすめ
働き方改革の取り組みを推進するためには、多様な働き方の従業員を一元管理できるシステムの導入がおすすめです。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、従業員データを一元管理し、従業員の多様な働き方や雇用形態などの情報を効率的に管理可能です。
日頃から『スマカン』に人材データを集約し可視化できるようにしておくと、必要な情報をすぐに取り出せて、資料作成やマネジメント業務の効率化にもつながります。
働き方改革をスムーズに推進し、定着化していくためにも、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
働き方改革は、労働環境を見直し、労働者の事情に応じた多様な働き方を実現するための取り組みのことを指します。
人材不足の課題を多くの企業が抱えているなか、働き方改革を進めることで人材が働きやすい環境が整備されると、優秀な人材の確保にもつながるはずです。
取り組み方は企業によってさまざまですが、政府が示す取り組みや他社の事例を参考にしながら、自社にも取り入れてみてはいかがでしょうか。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!