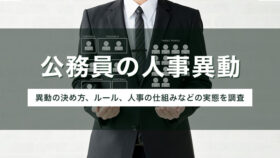- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
ストレスチェックの義務化とは? 概要や対象者、手順を徹底解説!

関連資料を無料でご利用いただけます
ストレスチェックの義務化は、従業員の心身の健康を守るために、労働安全衛生法の改正によって定められました。
近年、従業員のメンタルヘルスを適切に管理する企業が増えています。その背景には、労働安全衛生法の改定によって、従業員が50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務づけられたことにあります。
しかし、ストレスチェックの詳しい内容や実施方法や実施後の対応についてよくわからないと感じている担当者も少なくないでしょう。
本記事では、ストレスチェック義務化の概要を解説しながら、対象者や実施方法なども具体的にご紹介します。
目次(タップして開閉)
ストレスチェックの義務化とは
ストレスチェックの義務化は、労働安全衛生法の改正により2015年12月以降、定められたものです。
具体的には、従業員50人以上いる企業に対し、年1回すべての従業員を対象に実施することが義務づけられています。
また、従業員50人未満の企業においてもストレスチェック実施の努力義務が課せられているため、従業員における心身の健康を守るうえで、定期的にストレスを測ることが重視されているといえるでしょう。
そのため、どのような企業においても、できるだけストレスチェックを実施するのが好ましいといえます。
ただし、従業員側にはストレスチェックを受検することが望ましいとされているものの、義務があるわけではないという点は把握しておきましょう。
たとえば、すでにメンタルヘルスの不調を抱えていたり、ストレスチェックを受検することで負担がかかってしまったりするなど、受検しない理由がある従業員に対して、強制することのないよう注意しなければなりません。
参考:『ストレスチェック制度が始まりました(労働者の皆様へ)』厚生労働省佐賀労働局
ストレスチェック義務化の目的
ストレスチェックを義務化した目的にはどのようなものがあるのでしょうか。ストレスチェック義務化の目的をご紹介します。
従業員によるセルフケアとメンタルヘルス不調の予防を推進
従業員は個人差や状況によって違いはあるものの、毎日の業務を通してストレスを抱えがちです。
抱えているストレスを把握したうえでこれ以上大きくならないよう、従業員みずからセルフケアを行ったり、無理をしすぎないように意識したりすることが大切といえるでしょう。
企業による職場環境改善を推進
企業では、ストレスチェックの結果から、大切な従業員の健康を守るために職場環境を改善することが推進されています。
仮に企業として職場環境の改善を行わないままでいた場合、従業員がメンタルヘルスの不調を抱えて離職してしまったり、訴訟問題につながったりする可能性もゼロではありません。
ストレスチェックを通じて従業員のストレス状態を把握し、問題がある場合は、状況に応じて配置転換や短時間勤務へ変更するなど、柔軟に対応できるのが望ましいでしょう。
ストレスチェックの義務化の背景
ストレスチェックの義務化は、1984年2月に過労自殺が日本で初めて労災認定されたことをきっかけとしています。
日本は国際的に見ても自殺率が高い水準にあり、特に働き盛りの年代が「勤務問題」を動機として自殺するケースが多いことも背景として考えられるでしょう。
近年は精神障害に関する労災請求件数が増加傾向にあり、企業には従業員のメンタルヘルスへの配慮が強く求められるようになりました。
精神障害に関する労災補償状況
厚生労働省『過労死等の労災補償状況』によると、2019年度の精神障害に関する労災請求件数は2,060件で前年度比240件の増加でした。
2020年度は2,051件で前年度比9件の減少でしたが、支給決定件数は608件で前年度に比べて99件増加しています。
精神障害の発病に関与した事象では、上司などからのパワーハラスメントや同僚などからのいじめや嫌がらせが比較的多い傾向にあります。
参考:『精神障害に関する事案の労災補償状況』厚生労働省(2020)
| 関連記事 ハラスメント10種類を一挙解説 |
ストレスチェック義務化の対象企業
ストレスチェックが義務化されるのはどのような企業なのでしょうか。また、義務化されて以降、企業によるストレスチェック実施率はどれくらいなのでしょうか。
ストレスチェックが義務化される対象
ストレスチェックの義務化対象となる企業は、常時使用する従業員が50人を超える企業です。常時使用する従業員とは、正社員や契約社員、パートタイマーやアルバイトなどが含まれます。
常時使用する従業員の定義は2つあり、
| ・期間を定めずに労働契約を結んでいる従業員 (予定も含めて労働契約期間が1年以上ある従業員) ・週の労働時間数が正社員の4分の3以上である従業員 |
とされています。
参考:『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』(2021改訂)』厚生労働省
ストレスチェックに関する罰則規定
ストレスチェックが義務化されたものの、実施しない企業に対して罰則を規定しているわけではありません。
しかし、ストレスチェックを実施した場合においては報告義務があり、労働基準監督署への報告を怠たると50万円以下の罰金が規定されています。
ストレスチェックを実施する場合は、必ず労働基準監督署への報告を忘れないようにしましょう。
ストレスチェックの実施状況
ストレスチェックが義務化された以降、実施状況等はどのような状況になっているのでしょうか。
厚生労働省の『ストレスチェック制度の実施状況』によると、
| ストレスチェックの実施状況 | |
|---|---|
| ストレスチェック義務化対象事業場のうち | 実施した割合は82.9% |
| ストレスチェック事業場の従業員のうち | 受検した従業員の割合は78.0% |
| ストレスチェック実施者の選任状況 | 事業場内の産業医等が58.2% |
| ストレスチェックを受検した従業員のうち | 医師の面接指導を受けた割合は0.6% |
| ストレスチェックを実施した事業場のうち | 医師の面接指導を実施した割合は32.7% |
| 集団分析を実施したのは78.3% | |
というデータがあります。
このように、ストレスチェックが義務化されたことで、多くの企業がストレスチェックを行っていることがわかるでしょう。
ストレスチェックの質問領域や具体的質問
ストレスチェックを実施する際の質問票には、以下の領域に関する項目を含まなければなりません。
| 1.仕事のストレス要因 | 職場における、当該従業員の心理的な負担の原因に関する項目 |
|---|---|
| 2.心身のストレス反応 | 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 |
| 3.周囲のサポート | 職場における、ほかの従業員による当該従業員への支援に関する項目 |
仕事のストレス要因
ストレスチェックで確認したい領域の一つが、仕事のストレス要因です。
従業員が感じる職場環境や業務状況について問う領域であり、仕事と従業員の直接的な質問内容であるため、非常に重要です。
ストレス要因が何なのかを見極めることで、除外したり軽減させたりなど、対応を検討でき、状況を改善するヒントになるでしょう。
たとえば、
| ・仕事の量は適切か ・労働時間が長すぎないか ・働きがいはあるか |
という内容で質問します。
心身のストレス反応
ストレスチェックで確認したい領域には、心身のストレス反応もあります。具体的にストレスが心身の不調としてあらわれているのかや程度などを測る際に役立ちます。
たとえば、
| ・元気や活気があるか ・夜眠れているか ・具体的な体調不良があるか |
という内容で質問を設計します。
周囲のサポート
ストレスチェックでは、企業そのものだけでなく周囲の人との関係性に関する領域も重要です。
職場内外にかかわらず、周囲にサポートしてくれる人がいるかどうかや気軽に相談できる存在がいるかを確認しましょう。
具体的には、
| ・上司や同僚と気軽にコミュニケーションが取れているか ・悩みを相談する家族や友人はいるか ・困ったときに助けてくれる人が周囲にいるか |
という内容が挙げられます。
厚生労働省が推奨する調査票
ストレスチェック義務化にあたり、厚生労働省は、ストレスチェック実施で含むべき領域に関する質問の具体例として『職業性ストレス簡易調査票』を公開しています。
ストレスチェック実施のための準備が進まないという場合は、このようなサポートツールも積極的に取り入れてみましょう。
ストレスチェックの実施方法や手順
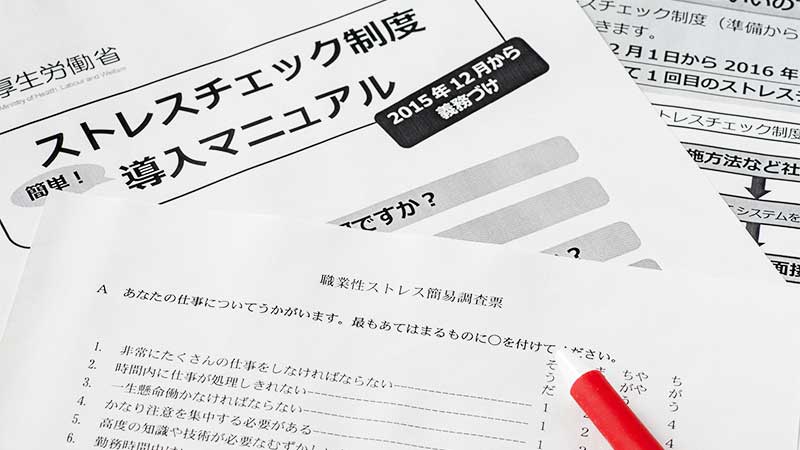
ストレスチェックの実施方法は、どのような流れや手順で進めればよいのでしょうか。具体的なステップをご紹介します。
ストレスチェック実施における注意点
まずはストレスチェックにおいて押さえておくべき注意点をご紹介します。
ストレスチェックを実施する場合、
| ・安全配慮義務 ・プライバシーの保護 ・不利益な取扱いの禁止 |
には注意しなければなりません。
ストレスチェックの実施が目的なのではなく、実施後に状況を改善していくことが大切であるため、実施も従業員の健康と安全をサポートできるような環境整備を意識しましょう。
また、個人的な情報を扱うため、アンケートの回答そのものはもちろん、プライバシーに関する情報が漏えいしないよう徹底しましょう。
さらに、ストレスチェックに関して、受検や面談の有無、結果を提供するかどうかなども含め、従業員に強制してはいけません。ストレスチェックをめぐるそれぞれの内容によって、従業員が不利益な扱いを受けることのないように留意しましょう。
ストレスチェックの導入準備
ストレスチェックの導入準備として、まずはどのようにストレスチェックを実施するのかを決めることが重要です。
まずは大まかに方針を決めたうえで、衛生委員会(従業員が50人以上の事業場に設置義務)によって具体的な内容を決めていきます。
厚生労働省によると、話し合う必要がある事項としては以下の8項目があります。
| 1 | ストレスチェックは誰に実施させるのか |
|---|---|
| 2 | ストレスチェックはいつ実施するのか |
| 3 | どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか |
| 4 | どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか |
| 5 | 面接指導の申出は誰にすればよいのか |
| 6 | 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか |
| 7 | 集団分析はどんな方法で行うのか |
| 8 | 集団分析はどんな方法で行うのか |
参考:『ストレスチェック制度 簡単導入マニュアル』厚生労働省(2015)
具体的な内容が協議できたら、
| ・制度全体の担当者 ・ストレスチェックの実施者 ・ストレスチェックの実施事務従事者 ・面接指導を担当する医師 |
などを選任し、役割分担を行いましょう。
ストレスチェックの実施者は、医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士(外部委託を含む)の中から選ばなければなりません。
注意点として、人事権を持つ者はストレスチェック実施事務に従事できないため理解しておきましょう。また、ストレスチェックに関する決定事項は社内規定として明文化し、従業員全員に周知しましょう。
ストレスチェックの質問事項を設計
ストレスチェックで質問する内容や項目を決めます。参考例として、厚生労働省が推奨する57項目の調査票を参考にしてみると負担なく準備できるかもしれません。
質問項目自体は、最低限含めるべき3つの領域(1.仕事のストレス要因、2.心身のストレス反応、3.周囲のサポート)を押さえたうえで、複雑に捉え過ぎず、ごく一般的な内容の質問を用意すればよいでしょう。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックを実施します。
アンケート自体は用紙もしくはオンライン上のどちらでも構いません。用紙を使う場合は、中が見えないように注意しながら、実施者や実施事務従事者が回収しましょう。
実施者や実施事務従事者は守秘義務が課せられています。アンケートの回答内容など、情報が漏れないように徹底しましょう。
| 関連記事 社内アンケートの質問例文を紹介 |
ストレスチェックの評価
次に、ストレスチェックの評価を行いましょう。回収した質問票に基づき、実施者がストレスの程度を評価して、結果を従業員に通知します。
ストレスチェックに回答した従業員へ必ず通知すべきものには
| ・従業員個人のストレスプロフィール ・ストレスの程度(高ストレスに該当するか否か) ・面接指導の対象か否かの判定結果 |
があります。
評価結果から、高ストレスに該当する従業員や医師の面接指導が必要な従業員を選定しましょう。
結果を保管するのは実施者または実施事務従事者です。ストレスチェックの結果を第三者が閲覧できないように、保管場所に鍵をかけたりパスワードによる管理をしたりするなど、厳重に扱いましょう。
面接指導の実施
ストレスチェックの結果から高ストレスに該当したら、本人が面接指導を望む場合は医師による面接指導を実施します。
従業員が面接希望を申し出できるのは結果が通知されてから1か月以内です。さらに面接指導は申し出から1か月以内に行わなければなりません。面接指導の結果は事業所で5年間保管しておきます。
企業は、面接指導後1か月以内に医師からの意見聴取をしなければなりません。そこで、面接を行った医師と連携しながら就業上の措置や対応を必要に応じて実施します。
従業員の状況によって、配置転換や時短勤務、場合によっては休職なども含め、医師とともに検討しましょう。
集団ごとの集計・分析
ストレスチェックの実施者は、企業からの依頼に基づき、ストレスチェックの結果を企業の各部署や課、グループなどの集団ごとに集計・分析し、企業に提供します。(努力義務)
企業は集計・分析の結果を踏まえて職場環境の改善に取り組みましょう。
なお、従業員規模が10人未満の場合、個人が特定されかねないため、従業員全員の同意がない限り、企業は結果の提供を受けられません。
ストレスチェックにおける高ストレス者への対応方法
ストレスチェックの評価で「高ストレス」に該当したら、従業員の希望や本人の了承を得たうえで医師との面接を行いますが、希望しない場合は面接を行えません。
面接ができない従業員を高ストレスのまま何もせずにしておくのは、企業として安全配慮義務上好ましくありません。
相談窓口の整備
医師との面接以外にも、悩みを相談できるような窓口を設置するのがおすすめです。
相談窓口は、社内設置だけでなく、外部委託で設置する方法もあるため、どちらの方法がよいのか検討し、従業員が相談しやすい環境を整備しましょう。
支援体制を整備
高ストレスに該当した場合、休職するケースもあるかもしれません。そのため、休職に関する社内ルール等を確認し、見直しをはかるなどの対応も必要でしょう。
また、一度休職をしたことで、復帰に不安を感じる場合もあるでしょう。そのため、休職中も人事担当者と定期的に連絡を取ることや、カウンセラーとの面談実施など、サポート体制を整えておくことが大切です。
休職した場合も、復帰できるような体制を整えておくことが従業員の安心につながります。
まとめ
ストレスチェックが義務化され、より一層企業として従業員の心身の健康を守ることが重視されています。ストレスチェックで大切なのは、従業員がストレスチェックを受け、安心して働けるよう適切な対応をとることや改善につなげることです。
企業として従業員のストレスチェックを定期的に実施し、結果に応じて職場環境の改善や労働環境の整備などに努めましょう。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!