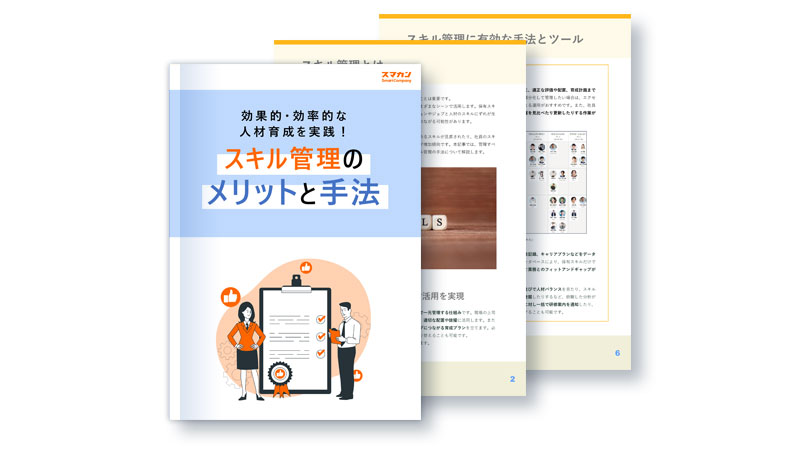- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材管理
- 人材育成
ポータブルスキルとは? 具体的なスキルや鍛え方を解説
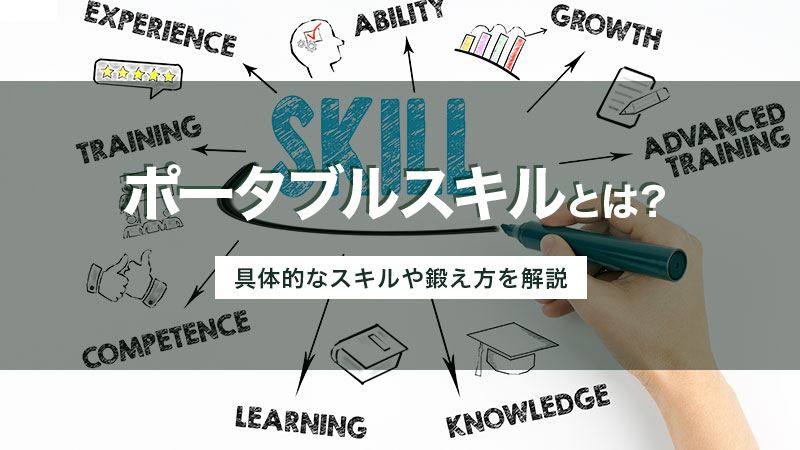
関連資料を無料でご利用いただけます
ポータブルスキルとは、どのような業種や職種でも活かせる「持ち運び可能なスキル」のことです。
ポータブルスキルは、就職や転職を希望する個人が自己PRの材料とするだけでなく、企業が従業員に求めるスキルとして人材採用や人事評価、人材育成などに取り入れられるようになってきました。
しかし、ポータブルスキルが「具体的にどのようなスキルを指すのか、いまいち理解できていない」と感じている経営層や人事担当者も少なくないでしょう。
そこで当記事では、ポータブルスキルについて解説しながら、具体的スキルや鍛え方、活用方法なども紹介します。
目次(タップして開閉)
ポータブルスキルとは?
ポータブルスキルは「持ち運び可能な(portable)能力(skill)」のことを指します。どのような業種や職種にでも活かせる「汎用性の高いスキル」とイメージするとわかりやすいでしょう。
厚生労働省はポータブルスキルについて、以下のように定義しています。
職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル
引用:『ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)』厚生労働省
具体的なポータブルスキルには
| ・コミュニケーション能力 ・論理的思考力 ・問題解決力 |
などが挙げられます。
このように、ポータブルスキルは働くうえで基本的かつ重要な能力であり、どのような企業でも必要とされるスキルといえるでしょう。
アンポータブルスキルとは
ポータブルスキルの対義語に「アンポータブルスキル」があります。
アンポータブルスキルは「持ち運び不可能な能力」を意味し、特定の企業や業種、職種でしか活用できない技術的なスキルのことを指します。
たとえば、
| ・社内独自のシステムへの理解 ・自社オリジナル商品への深い知識 |
などが挙げられます。
アンポータブルスキルは、特定の企業や業種、職種にとっては毎日の業務を行ううえで重要な能力ではありますが、汎用性が高いスキルとはいえません。そのため、長い目でキャリアを見ると、ポータブルスキルを磨くことが重要という考え方もあります。
ポータブルスキルと類似したスキルをあらわす「トランスファラブルスキル」も持ち運び可能とされます。しかし、社会人経験のない学生やポストドクターなどを対象としている点で、ビジネスパーソンを対象とするポータブルスキルと異なります。
ポータブルスキルが必要な理由
ポータブルスキルが必要とされる理由には、具体的にどのような点が挙げられるのでしょうか。
自分のキャリアのため
ポータブルスキルが必要とされる理由の一つには、キャリアを見据えてできるだけ市場価値を高める必要があるためです。
終身雇用や年功序列制度がなくなりつつある社会において、転職は一般的なものになりました。転職を成功させるためには自分の市場価値を高め、企業に欲しいと思ってもらえる人材にならなければなりません。
そのためにも、汎用性が高くどのような企業でも必要とされるポータブルスキルを身につけておく必要があるといえるでしょう。
時代の変化に対応するため
近年、ITをはじめとするテクノロジーの発展によって、従来の働き方やビジネスモデルの転換を迫られることが少なくありません。
このような時代の変化があっても、ポータブルスキルを有したビジネスパーソンであれば柔軟に対応し、活躍の幅を広げられるでしょう。
企業にとっても、ポータブルスキルを有した従業員の存在は重要です。社会情勢やビジネスの変化があっても、ポータブルスキルを有した従業員がいることで、柔軟に対応することができるでしょう。
ポータブルスキルの要素
厚生労働省「“ポータブルスキル”活用研修」では、ポータブルスキルの構成要素は「仕事のしかた」「人との関わり方」の領域において、9つあるとしています。
そこで、ポータブルスキルの9つの要素をそれぞれ確認してみましょう。
仕事のしかた
仕事のしかたは成果を上げるために重要となる行動のことです。
仕事のしかたに関する要素は、
| ・現状の把握(情報収集能力や分析力など) ・課題の設定(課題発見能力や統計分析力など) ・計画の立案(リサーチ力、ネゴシエーション能力など) ・課題の遂行(実行力、プロジェクトマネジメント力など) ・状況への対応(臨機応変力、トラブル対応能力) |
の5つに細分化され、以下の表のようにまとめることができます。
| スキル | 定義 |
|---|---|
| 現状の把握 | 情報収集を行い、評価や分析を行う |
| 課題の設定 | 自身の問題意識に沿って、改善策などを設定する |
| 計画の立案 | 目的に向けて具体的な計画を立てる |
| 課題の遂行 | 成果にこだわって納期を守ったうえで業務を遂行する |
| 状況への対応 | 変化に臨機応変に対応する |
人とのかかわり方
人との関わり方は、組織内外の関係者とコミュニケーションをはかり、連携しながら業務を遂行していく対人マネジメントスキルです。
具体的要素として
| ・社内対応(コミュニケーション能力、ネゴシエーション能力など) ・社外対応(コミュニケーション能力、交渉力、バランス感覚など) ・上司対応(コミュニケーション能力、ビジネスマナーなど) ・部下マネジメント(マネジメント能力、育成スキルなど) |
の4つに細分化され、以下の表のようにまとめることができます。
| スキル | 定義 |
|---|---|
| 社内対応 | 異なる価値観や利害関係のあるメンバーと調整し、合意形成をはかる |
| 社外対応 | 異なる価値観や利害関係のある社外関係者と調整し、合意形成をはかる |
| 上司対応 | 上司へ報告したり意見を伝えたりする |
| 部下マネジメント | 部下の強みを把握しながら業務を采配し、育成する |
ポータブルスキルの具体例
ポータブルスキルには9つの要素があることがわかりました。実際にポータブルスキルといわれるスキルにはさまざまな種類があります。
そこで、具体的なポータブルスキルの例として、ジャンル別に表でまとめながらご紹介します。
現状把握に関するポータブルスキル例
現状把握に関するポータブルスキルの例は、以下のようなものが挙げられます。
| 具体的スキル | 内容 |
|---|---|
| 分析力 | 問題や課題の原因を分析し、効果的な解決策を考える能力 |
| 情報収集力 | 問題点についてさまざまな角度から情報収集を行う能力 |
| 本質把握力 | 少ない情報から、本質を見つけ、把握できる能力 |
| メタ認知能力 | 客観的な視点で物事を見つめ、取るべき行動を正しく理解できる能力 |
現状把握においては、現在の状況を分析するだけでなく、客観的視点で今後の対策まで考えられる能力を含むと考えてよいでしょう。
コミュニケーションに関するポータブルスキル例
コミュニケーションに関するポータブルスキルの例には以下のようなものが挙げられます。
| 具体的スキル | 内容 |
|---|---|
| 説得力 | 異なる考えを持つ人に、疑問や不安を解決して納得させることのできる能力 |
| 傾聴力 | 相手の意見に耳を傾け、信頼を得る能力 |
| 牽引力や統率力 | 目的に向かって周囲を巻き込み、引っ張る能力 |
| 対話力 | 一方的なものではなく、互いに会話を通して合意形成をはかる能力 |
コミュニケーションにおいては相手との良好な関係を保ちながら、円滑に業務を進めていくことが大切です。
課題解決に関するポータブルスキル例
課題解決に関するポータブルスキルの例は、以下のようなものが挙げられます。
| 具体的スキル | 内容 |
|---|---|
| 分析力 | 問題や課題の原因を分析し、効果的な解決策を考える能力 |
| 試行力 | 不安要素がある場合でも、積極的に試みる能力 |
| 変革力 | これまでの考え方にとらわれず、新たな発想で変化を成し遂げる能力 |
| 行動力 | 課題を解決できるような工夫や試みを行い、挑戦し続ける能力 |
課題解決においては、そもそもの課題について分析したり、本質を見極めたりしたうえで、課題解決に向けて積極的な行動を取る力が大切です。
ポータブルスキルの活用シーン

ポータブルスキルは、企業組織の中でどのような活用シーンがあるでしょうか。具体的なシーンを例をあげてご紹介します。
人材採用
ポータブルスキルを採用活動でも重視することで、即戦力として活躍できる人材を確保できる可能性が高まります。
専門スキルを保有する応募者を中途で採用できたとしても、必ずしもすぐに活躍できるとは限りません。
しかし、ポータブルスキルに秀でた応募者なら、技術や知識が不十分でも、みずからの課題を見つけ意欲的に学習してスキルアップしたり、コミュニケーションを深めたりしながら、業務を円滑に進めていけるでしょう。
人材育成・能力開発
ポータブルスキルの保有状況について、人事が把握しておけば、個人に合わせた育成計画を立てられます。
ポータブルスキルは、日常業務の中で培うことができるため、特殊な業務を経験させたり高度な資格を取得してもらったりする必要はありません。
従業員個人のキャリア形成をサポートすると同時に、ポータブルスキルに優れた従業員を増やすことで企業の成長も促進されやすくなるはずです。
人材配置
ポータブルスキルを踏まえた人材配置を行うことで、部署やチームの課題を解決する糸口にもなります。
人材配置を検討するときは、従業員のポータブルスキルとのバランスを考えながら、異動先で上手に人間関係を構築できるか、思う存分能力を発揮できるかなどを考慮することが大切です。
適材適所の人材配置を実現すれば、従業員のモチベーションが向上して生産性がアップし、優秀な人材の離職を防止する効果も期待できるでしょう。
ポータブルスキルの鍛え方
ポータブルスキルは日々の業務を通して鍛えられます。
しかし、個人差が出てきたり、スキルの偏りが生じたりするものです。従業員が効率的にポータブルスキルを身につけるにはどうしたらよいのでしょうか。
そこで具体的なポータブルスキルの鍛え方に注目してみましょう。
従業員の長所と短所を把握する
ポータブルスキルを鍛えるまず第一歩として、自分自身への評価をもとに長所や短所を正しく把握することが挙げられるでしょう。
従業員の自己評価と上司や同僚などからの他者評価を組み合わせて、長所と短所が明確になると、本人の伸ばすべきスキルが見えてきます。
評価は、5段階評価など基準があると忠実に把握しやすいでしょう。360度評価を実施しているなら、その評価結果が現状把握の手掛かりになるのです。
研修を実施する
ポータブルスキルを鍛えるためには、企業としてポータブルスキルに関する研修を実施したり、外部研修を受講させたりするのも効果的です。
厚生労働省が『“ポータブルスキル”活用研修』のテキストを公開しているので、これを参考にして企業内研修のカリキュラムを作成するとよいでしょう。
参考:『“ポータブルスキル”活用研修』人材サービス産業協議会
外部研修を受講させる方法は、ポータブルスキルを学べる研修やオンライン講座などを積極的に受講させる取り組みがあります。
このような外部研修に従業員が参加しやすいように、企業が受講費の一部を負担したり、長期休暇を認めたりするなどの制度を設けることも考えられるでしょう。
日々の業務を改善する
ポータブルスキルを鍛えるために、日々の業務の改善に取り組んでもらうことも効果的です。
たとえば、ポータブルスキルの一種であるスケジュール管理能力には、ゴールから逆算して進捗管理したり、生産性を高めるためにタスクを効率化したりする過程が含まれます。このような業務改善の経験は、別の部署やチームに移ったときにも活かせるでしょう。
また、定期的な1on1ミーティングは、対話の中で部下に課題に気づいてもらい、改善策を一緒に考えていく機会です。
このように企業側がサポートしながら、従業員のポータルスキルを高めていくことで、企業全体の成長も期待できるでしょう。
目標管理と評価制度の見直し
ポータブルスキルは、目標管理と評価制度の見直しによって伸ばせる可能性があります。
たとえば、MBO(目標管理制度)やOKRの導入です。
MBOとは、みずからの意思で目標を設定し、その達成度を人事評価にも反映させる仕組みです。MBOでは、従業員みずから考える機会が豊富にあり、課題発見能力や状況把握力、課題遂行力を磨けるでしょう。
OKRとは、組織目標の達成を目指しつつ、従業員に高めの目標にチャレンジさせる制度です。OKRでは、定性的な「目標(Objectives)」と定量的な「主要な結果(Key Results)を設定します。
短いスパンで目標に取り組むことで、進捗管理能力が養われたり、優先順位を設定して業務に取り組む能力が身につきやすくなるでしょう。
ポータブルスキルを伸ばすなら「人材管理の効率化」
ポータブルスキルは従業員個人にとって重要であるだけでなく、変化の激しい時代に企業が成長していくうえでも欠かせないものです。そのため人材採用や人事評価、人材育成などのあらゆる場面でポータブルスキルが評価の対象とされつつあります。
一方で、従来の人事業務にポータブルスキル関連の研修や評価業務も加わると、人事担当者の負担が増加することにもつながりかねません。
そこで人事担当者の負担を軽減し、人材管理業務を効率化するのに役立つのがタレントマネジメントシステムです。
タレントマネジメントシステム『スマカン』では、ポータブルスキルの有無も含めた従業員のスキル管理を実施できます。より自社に適した人事評価や目標管理、育成計画を進めてみてはいかがでしょうか。
『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!