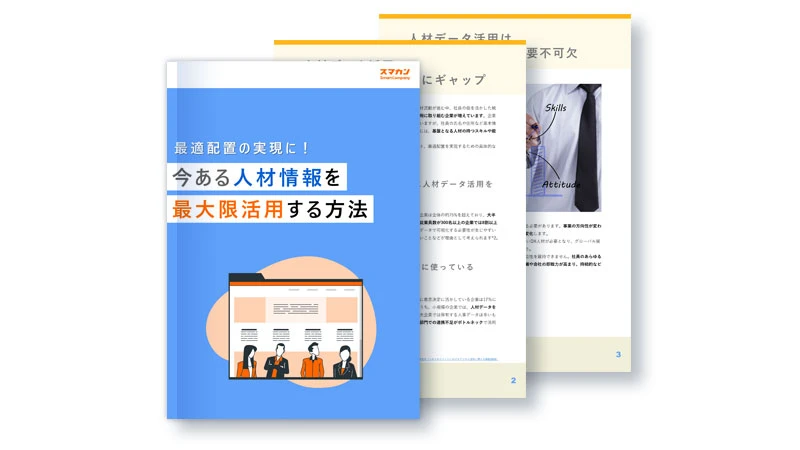- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
【2022・2023年】人事労務の法改正まとめ |企業の対応ポイントも解説
![[2022年版]人事・労務法改正の要点まとめ 企業の担当者が対応すべきポイントとは](https://smartcompany.jp/wp-content/uploads/2022/06/thumb_column_220616_3-1.jpg)
関連資料を無料でご利用いただけます
人事労務に関連する法改正は毎年のように行われており、その都度対応に追われている担当者や経営者も少なくないでしょう。
本記事は、人事労務の2022年法改正を振り返るとともに、2023年以降に施行が予定されている法改正の要点をご紹介します。企業が押さえておきたい実務対応とあわせてチェックしてみてください。
目次(タップして開閉)
2022年の人事労務法改正
2022年は人事労務に関連するさまざまな法改正がありました。代表的なものを8つ挙げます。
| 1.雇用保険マルチジョブホルダー制度 2.傷病手当金|支給期間の通算化 3.中小企業におけるパワハラ防止法の適応 4.育児・介護休業法(4月施行) 5.女性活躍推進法 6.個人情報保護法 7.育児・介護休業法(10月施行) 8.社会保険適用拡大 |
【2022年1月】雇用保険マルチジョブホルダー制度
雇用保険マルチジョブホルダーとは、「複数」の事業所で働く「65歳以上」の労働者が、一定の条件を満たすと雇用保険に加入できる制度です。従来は「1つの事業所」で週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあることが条件の一つでした。
2022年1月施行の法改正により、65歳以上の方は、複数の事業所の勤務を合計して雇用保険の加入条件を満たすことができるようになったのです。
| 雇用保険マルチジョブホルダー制度における加入条件 |
|---|
| 1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者 2.2つの事業所の1週間の所定労働時間が合計20時間以上 (ただし、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満) 3.2つの事業所それぞれで31日以上の雇用見込みがある |
ただし、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、条件を満たしていても雇用保険への加入を強制するものではありません。また、一度加入すると任意脱退は認められておらず、退職するか上記条件のいずれかが当てはまらなくなった場合にのみ、雇用保険の資格を喪失します。
【企業の実務ポイント】
□ 加入を希望する従業員への対応
□ 新たに加入した従業員の給与計算に注意
マルチジョブホルダー制度において、雇用保険の加入手続きは労働者が行います。ただし労働者から申し出があった場合、企業は必要な手続きの準備に協力しなければいけません。具体的には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に必要事項を記入することや、手続きに必要な雇用契約書、勤怠表など資料の準備です。
マルチジョブホルダー制度が適用となった従業員の給与からは、新たに雇用保険料を徴収することになります。
【2022年1月】傷病手当金の支給期間の通算化
2022年1月施行の法改正で、傷病手当金の支給期間が以下のように変更になりました。
| 改正前 | 傷病手当金の支給開始日から「起算」して1年6か月 |
| 改正後 | 傷病手当金の支給開始日から「通算」して1年6か月 |
傷病手当金とは、同一の病気やケガによって業務を行えない場合、本人や家族に支給される手当です。出勤している期間は受給できません。
従来の制度では、支給開始から1年6か月の間、出勤月を差し引いた月数分しか傷病手当金は支給されませんでした。2022年1月から、業務を行えない月が1年6か月になるまで支給されることになり、療養と業務を両立しやすくなったといえるでしょう。
【企業の実務ポイント】
□ 傷病手当金を受け取る従業員の勤怠管理の徹底
□ 支給開始日の把握
担当者は、対象の従業員の出勤日数や支給開始日などの適切な管理が求められます。
| >>>無料ダウンロード 人事書類をペーパーレス化【スマカンのご紹介】 |
【2022年4月】中小企業におけるパワハラ防止法
2019年5月に成立したパワハラ防止法(労働施策総合推進法)では、職場のパワーハラスメントを防ぐため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされています。大企業は2020年6月より施行されており、これまで中小企業は努力義務とされていました。
2022年4月施行の法改正で企業規模にかかわらず、すべての企業において適用されています。中小企業が新たに講じるべき措置は以下の4つです。
| 職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置 |
|---|
| 1.事業主の方針の明確化およその周知・啓発 2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 3.職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 4.併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止など) |
出典:厚生労働省リーフレット
【企業の実務ポイント】
□ 事前防止(説明と周知)
□ 発生時のフォロー体制の整備(被害者保護、相談窓口の設置など)
中小企業の担当者は、新たに上記4つの措置を講じ、パワーハラスメント防止に努めなければいけません。どのような行動・発言がパワハラに該当し、なぜ行ってはならないのか、行った場合にどのような処遇があるかなどを、会社全体に周知する必要があります。
被害にあった従業員を守る体制を整備することも重要で、相談窓口を設置し、対応マニュアルやフローも用意します。パワハラに関する規定を、就業規則に追加する必要もあるでしょう。
【2022年4月】改正育児・介護休業法
育児・介護休業法における法改正は、2022年に4月と10月に2回にわたって施行されました。4月の施行では、以下の2点が適応されています。
【1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化】
企業は、育児休業に関する研修の実施や相談窓口の設置、休業取得事例の収集や提供、促進に関する方針の周知、いずれかの措置を講じなければいけません。妊娠や出産(本人または配偶者)を申し出た労働者に対して個別に周知したり、意向を確認したりすることも必要です。法改正の前は、努力義務にとどまっており、周知や確認は求められていませんでした。
【2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
従来の休業取得条件は、「引き続き雇用された期間が1年以上」かつ「1歳6か月までの間に契約が満了しない」ことでしたが、2022年4月より撤廃されています。
【企業の実務ポイント】
□ 研修の実施
□ 対象となる従業員の把握と個別対応(面談等)
従業員が円滑に育児休業の申し出ができるよう、育児休業に関する研修の実施や、周知と休業の取得について意向確認を個別に行う必要があります。
個別周知の方法は、面談・書面交付・FAX・メールなどのいずれかです。育児休暇の取得を控えさせるような個別周知や意向の確認とならないよう注意しましょう。
【2022年4月】改正女性活躍推進法
2022年4月施行の法改正により、女性活躍推進法の対象が、従業員301人以上から101人以上の企業に拡大されました。女性活躍推進法は、働きたい女性が個性やスキルを十分に発揮して、活躍できる職場環境を後押しするために定められています。具体的には、行動計画の策定や自社の女性従業員の活躍に関する情報公開を義務づけています。
厚生労働省は、以下の項目を必ず把握し、自社の課題分析を行うこととしています。
| ・採用した労働者に占める女性労働者の割合 ・男女の平均継続勤務年数の差異 ・管理職に占める女性労働者の割合 ・労働者の各月ごとの平均残業時間数などの労働時間の状況 |
【企業の実務ポイント】
□ 必要な人材情報の集計にかかわる自社管理システムの点検
□ 数値に基づく課題や目標設定
従業員数が101人以上の企業は、自社の女性活躍状況を把握して課題を分析し、行動計画をまとめる必要があります。計画には、計画期間、数値目標、取り組みの内容、取り組みの実施時期を盛り込まなければいけません。
【2022年4月】改正個人情報保護法
個人情報保護法は、個人情報に関する権利・利益の保護を目的とした法律で、2005年より定期的に法改正が行われてきました。
2022年4月施行の法改正では、技術の進化やグローバル化を視野に入れたものとなっています。具体的には以下の6点です。
【1.本人請求権の拡大】
法令違反が行われていなくても、本人請求により、個人情報の停止・削除が可能になりました。
【2.事業者債務の追加】
個人情報の漏えいが発生し、本人への通知と個人情報保護委員会への報告が義務化されました。(※個人への影響が大きい場合)
【3.事業者の自主的な取り組みの推進】
企業の特定分野を対象とする団体を、個人情報の保護団体として認定できるようになりました。
【4.データ活用の促進】
仮名加工情報が新設され、取り扱い義務が緩和されました。これにより、個人を特定できないように変換した情報であれば、データの利活用ができるようになります。また、本人が関与していないうちに個人情報が拡散されないよう、事業者は提供先への確認義務が設けられました。
【5.法令違反に対する罰則強化】
措置命令違反、報告義務違反、個人情報の不正流用などをした個人や法人に対する罰則が強化されました。
【6.外国事業者への罰則追加】
日本にいる個人の情報を取り扱う外国事業者も、報告徴収や命令の対象とし、罰則が適用されるようになりました。
参照:『個人情報保護法 令和2年改正及び令和3年改正案について』個人情報保護委員会
【企業の実務ポイント】
□ プライバシーポリシー改訂
□ 漏えい発生時のシミュレーションと体制準備
2022年4月施行の法改正で、コーポレートサイトなどのプライバシーポリシーを見直す必要があるでしょう。さらに万一個人情報が漏えいし、本人への影響が大きい場合は、個人情報保護員会への報告が義務化されたため、緊急時に備えて対応フローを用意しておくといいかもしれません。
【2022年10月】改正育児・介護休業法
2022年施行の育児・介護休業法の法改正は、4月に続いて10月にも施行されました。10月に適応開始されたのは、産後パパ育休(出生時育児休業)です。産後パパ育休は、男性が育休とは別に、子どもの出生後8週間以内で最大4週間の休暇を取得できる制度です。加えて上限を2回として、育児休業の分割取得が可能となりました。
【企業の実務ポイント】
□ 就業規則の追加(=労働基準監督署への届出)
□ 休暇に備えた人材配置の適正化
産後パパ育休については、就業規則への追加と同時に労働基準監督署への届出が必要です。
育児休業の分割取得について従業員から申し出があった場合、ほかの従業員への周知を忘れないようにしてください。出産を控えた社員本人や、家族が出産を控えている男性社員などが業務から離れても支障が出ないように、業務体制も見直すといいでしょう。
【2022年10月】社会保険の適用拡大
2022年10月から、段階的にパート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されます。以前は常時雇用する従業員数501人以上の企業にとどまっていましたが、今回施行の法改正で101人以上の企業まで拡大されます。さらに2024年には、51人以上の企業にまで適用される予定です。
社会保険の加入条件は以下の4つで、すべてを満たさなければいけません。
| 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.賃金の月額が8.8万円以上あること 3.雇用期間が2か月を超える見込みがあること (今回の法改正で「継続して1年以上使用される見込みのある従業員」から変更) 4.学生ではないこと |
【企業の実務ポイント】
□ 対象従業員への個別ヒアリング・事前説明
□ 給与計算に注意
法改正による社会保険の適用拡大により、企業側の社会保険料の負担が増える可能性があります。今回新たに対象となった従業員の給与からは、社会保険料が控除されるため、事前に説明する必要があるでしょう。
社会保険の対象となるために、従業員から労働時間を増やしたいという要望が出るケースも考えられます。早めに従業員へ周知し、意向を確認するといいでしょう。
2023年の人事労務法改正
2023年はも人事労務に関連するさまざまな法改正の施行が予定されています。主なものを3つ挙げます。
| 1.改正労働基準法|中小企業の時間外労働割増賃金率引き上げ 2.給与のデジタル払い解禁 3.改正育児・介護休業法|取得状況の公表義務化 |
【2023年4月】改正労働基準法|中小企業の時間外労働割増賃金率引き上げ
改正労働基準法により、2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられる予定です。今後は、大企業に限らず中小企業においても割増賃金率が「50%」となります。
大企業では2010年4月よりすでに始まっていましたが、中小企業では適用が猶予され、25%が維持されていました。
しかし、2023年4月施行予定の法改正で、企業規模にかかわらず50%の割増賃金率が適用されます。
【企業の実務ポイント】
□ 就業規則の追加(+労働基準監督署への届出)
□ 長時間労働者への対応
□ 全社的な残業時間削減への取り組み
割増賃金率50%への引き上げに合わせて、就業規則の改訂と労働基準監督署への届出が必要です。起算日についても正確に記載しましょう。
そして月60時間を超える時間外労働をした従業員に、割増賃金率50%を適用した賃金を計算し、支払う必要があります。従業員の希望があれば、代替休暇を付与することもできますが、その場合は労使協定の締結が求められます。
そもそも担当者として労働時間を適切に把握するとともに、時間外労働時間の削減に取り組むことも重要です。
【2023年4月】給与のデジタル払い解禁
2023年4月に注目されている施行予定の法改正として、給与のデジタル払いが挙げられます。企業は労働者の同意があれば、スマホ決済アプリや電子マネー(〇〇pay)によって賃金を支払えるようになります。
【企業の実務ポイント(導入するのであれば)】
□ 従業員の同意を得る
□ 就業規則の追加(+労働基準監督署への届出)
企業は労働者から求められても、必ずしもデジタル払いを導入する義務はないので、ニーズを調査するといいかもしれません。
実際にデジタル給与を導入する場合は、労働者の同意と労使協定の締結が必要です。なお、企業側はデジタルマネーを提供している資金移動業者を選択肢として提示するだけでは不十分です。銀行口座や証券総合口座も選択肢として提示したうえで、デジタル払いについて同意をとる必要があります。
【2023年4月】改正育児・介護休業法|取得状況の公表義務化
2023年4月に施行予定の改正育児・介護休業法によって、常時雇用する従業員数1,000人を超える企業は、育児休業の取得状況を年1回以上、公表しなければいけません。これまでは「プラチナくるみん認定」を取得している企業を対象としていました。
公表すべき育児休業の取得状況とは、①男性の育児休業等の取得率または②育児休業等と育児目的休暇の取得率です。同時に、算定期間である公表前事業年度の期間と①②どちらの割合であるかも公表する必要があります。
【企業の実務ポイント(導入するのであれば)】
□ 公表に向けたデータ集計と公開準備
企業は、公表する前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、データを算出し、自社サイトや厚生労働省が運営する『両立支援のひろば』にて公表します。
参考:『両立支援のひろば』
2024年の人事労務法改正
2024年も人事労務に関連する法改正の施行が予定されています。
【2024年4月】改正働き方改革関連法|時間外労働の上限規制の適用拡大
2024年4月に施行予定の改正働き方改革関連法によって、建設や物流業界に大きな影響が懸念されています。
改正働き方改革関連法は段階的に適用されており、なかでも時間外労働時間の上限規制は、2019年4月から大企業、2020年4月から中小企業で始まっています。
これまで以下の事業や業務においてはさらに適用が猶予されていました。
| 1.建設事業 2.自動車運転業務 3.医師 4.医⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業 |
時間外労働の上限規制とは、原則として残業時間を「⽉45時間/年360時間」とする規定です。36協定における特別条項を締結する場合であっても、「年720時間/複数月80時間以内/月100時間未満」を超えることはできません。
2024年4月に、上記業種・業務の5年間の猶予が終わります。時間外労働の上限規制が新たに設けられた建設・物流業界では、会社の利益や労働者の収入が減少する恐れがあり、「2024年問題」と呼ばれています。
【企業の実務ポイント(導入するのであれば)】
□ 働き手の確保
□ 低賃金・長時間労働の抜本的な改革<
上記業種・業務に該当する企業の担当者は、適切な労働時間の把握などが求められます。2024年問題に対しては、労働環境の改善や多様な働き方に対応することで人手を確保したり、ITツールの活用で労働生産性を向上させることで利益を維持するなどの全社的な取り組みが必要となるでしょう。
人事労務の法改正で必要な実務対応ポイント
人事労務に関しては毎年さまざまな法改正があり、担当者は多くの対応に追われることでしょう。施行前に慌てることのないよう、就業規則の改訂やデータの可視化、雇用環境の整備に努める必要があります。従業員に対する周知も忘れてはいけません。
法律に従わないと、助言や指導、勧告の対象となり、公表されるケースもあります。そうなると企業の社会的イメージを損なうだけでなく、従業員の不満につながり離職が増える可能性もゼロではありません。
法改正による現場の変更点や必要な対応に取り組むのは、人事労務担当者の急務といえるでしょう。
| 関連記事 人材情報の一元管理するには? |
まとめ
2024年にかけて人事労務に関わる法改正が多数予定されています。法改正に迅速に対応するには、人材情報の見える化など適切な人材管理が必要でしょう。
クラウド型人事システム『スマカン』
『スマカン』は従業員一人ひとりの情報を一元管理し、さまざまな人材施策に役立てられるクラウド型人材管理システムです。情報を集約して必要なときに必要な情報が取り出しやすくなれば、素早く社内状況が把握でき、煩雑な業務の効率化につながるでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランですので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報や人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントシステムにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と導入実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!