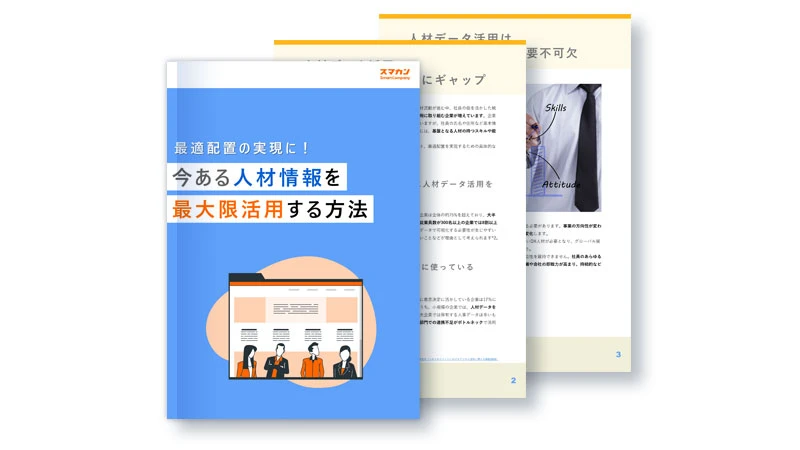- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材管理
人材配置を最適化するには? 目的と方法、適材適所の実現に向けた考え方
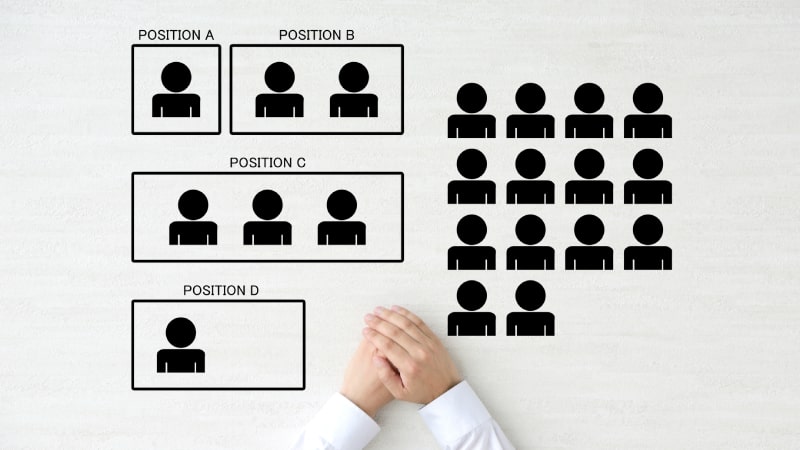
関連資料を無料でご利用いただけます
人材配置とは、従業員を配置、異動することです。人材配置の最適化とは、従業員一人ひとりの能力・適性に応じて人材を配置することを指します。適材適所の人材配置は、人事戦略の一つであり、経営目標や企業ビジョンを達成するためにも重要だと考えられています。生産性の向上、コスト削減、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上および離職防止など、組織の活性化が期待できるでしょう。
当記事では、人材配置の種類や最適化の方法、実現に向けた考え方をご紹介します。「適性に応じて人材配置ができていない」「人が定着しない」とお悩みの人事担当者や経営者、人材育成に力を入れたいマネジメント層の方もぜひご活用ください。
>>人材配置の最適化をサポート『スマカン』サービス資料はこちら
目次(タップして開閉)
人材配置とは
企業において人材配置とは、単に従業員を配置、異動することを指します。ただし、人材マネジメントの観点からすると、会社の目指す方向性に沿って従業員のスキルや適性、希望などを踏まえ、適切に配置しなければ意味がありません。
人員配置、人事配置の違い
人材配置とよく似た言葉に「人員配置」「人事配置」があり、人材配置とほぼ同じ意味でビジネスシーンで使われます。ただし、人員配置は医療・福祉分野の専門用語でもあり、利用者人数に応じた専門家の配置基準を指すこともあります。
人材配置の最適化
人材配置の最適化とは、ここでは、従業員一人ひとりの能力・適性に応じて人材を配置することを指します。人材配置の最適化によって、生産性の向上、コスト削減、組織の活性化、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上および離職防止が期待できます。
人材配置の種類
人材配置には、大きく分けて以下の5種類があります。人材配置と聞くと、異動や配置転換を思い浮かべがちですが、それだけではありません。
| 1.人材採用 2.人事異動 3.昇進・昇格 4.雇用形態の変更 5.解雇・リストラ |
1.人材採用
人材配置の最初の段階が、人材採用です。部署やポジションに不足が発生した場合、新しく従業員を採用して配置します。
人材採用には大きく分けて新卒採用と中途採用の2種類があります。中途採用は欠員補充の意味合いが強く、人手不足の部署にそのまま配属されます。一方、日本の新卒採用は、人材育成の一環として複数の部署をジョブローテーションするケースが多いです。
2.人事異動
人材配置の次の段階が、人事異動です。本人の適性と希望を考慮して、能力を最大限に発揮してもらうために実施します。あるいは人材育成の観点から、今よりチャレンジングなポストに配属して、スキルアップをはかることもあります。
人事異動には、定期的なものと突発的なものがあります。突発的な異動の理由は、欠員補充、新プロジェクト・新部署の発足、部署の統合など、企業によって多岐にわたります。中には玉突き人事のような事案が発生することもあります。
| 関連記事 玉突き人事はリスク? |
3.昇進・昇格
昇進・昇格も人材配置の一種です。職位が上がったり、新たに役職を得たりすることを指します。従業員のモチベーションやエンゲージメント向上にもつながるため、人材育成の観点からも効果的な人材配置の手段といえるでしょう。
4.雇用形態の変更
雇用形態の変更も人材配置に含まれます。契約社員から正社員への変更や、フルタイムから時短勤務への変更などが一例です。業務内容と雇用形態が見合うように、柔軟な判断が求められる人材配置といえるでしょう。
5.解雇・リストラ
解雇・リストラも人材配置の一つと考えられています。事業縮小や業績が悪化した場合に、経費削減の一環として整理解雇(リストラ)を行うことがあります。ただし、解雇には正当で合理的な理由が必要なので、実施の際は注意しましょう。
6.組織体制の変更
会社の組織体制が変わる場合も、人材配置が行われます。業務の担当者変更をはじめ、部署の新設や統合・廃止などさまざまな形で行われますが、経営戦略の見直しの一環として行われる場面も少なくありません。
スタートアップ企業や中小企業など経営の意思決定が迅速な企業では、積極的に組織変更が行われる傾向にあります。配置する人材のスキルやポテンシャルによって組織・会社の生産性に大きく影響するため、人材配置にあたっては慎重かつ客観的な判断が必要となります。
人材配置を最適化する目的
人材配置の最適化する目的は、最終的に経営目標や企業ビジョン、事業計画を達成することです。従業員を適性や希望に応じて適切な部署に配属・異動させることによって、生産性やモチベーションの向上につなげる考え方です。
さらに、人材配置の最適化には人材育成を効果的に進める目的もあります。今までに経験のない業務内容を任せることで、スキルアップの機会を与えることにもなります。人材配置は、効果的なタレントマネジメントの一つともいえるでしょう。
| 関連記事 タレントマネジメントとは |
人材配置を最適化するための流れ・考え方
人材配置を最適化するには、以下の4つの流れに沿って進めるといいでしょう。
| 1.定員計画 2.要因計画 3.人員計画 4.代謝計画 |
1.定員計画
人材配置の定員計画とは、目標達成のために必要な人員数を算出した計画です。おおよその人件費も試算し、経営目標の実現に向けたコストも予測します。
2.要員計画
人材配置の要員計画は、部門ごとに必要な人員数を割り出した計画です。定員計画で算出した人員数をより詳しい計画に落とし込みます。
3.人員計画
人材配置の人員計画は、「具体的にどこのポジションに誰を配置するのか」を検討する段階です。要員計画を遂行するために、具体的に計画を詰めていきます。従業員一人ひとりに対して、人件費を考慮したうえで、配置転換、雇用形態の変更、昇進・昇格などを検討します。全体のバランスを見て、特定のポジションにおいては、新規採用や解雇を実施するという結論に至ることもあるでしょう。
なお、定員計画、要因計画、人員計画、代謝計画の4つをまとめて「人員計画」を指すこともあります。
4.代謝計画
人材配置の代謝計画とは、要員計画と人員計画のギャップを埋めるための計画です。綿密に要員計画を策定できたとしても、人員計画と照らし合わせると、人材不足が発生することもあるからです。新卒採用や中途採用で人手不足を解消したり、再配置を検討するなど、適切な計画になるように手直しするのです。
人材配置の最適化で得られる効果
最適な人材配置ができると、具体的にどのようなメリットや効果があるのでしょうか。ここでは、代表的なものを3点ご紹介します。
| 1.業績や生産性向上 2.コスト削減 3.従業員のエンゲージメント向上、離職防止 4.人材育成 |
業績・生産性の向上
人材配置の最適化によって生産性の向上を実現できるでしょう。たとえば、パフォーマンス面で課題を抱えた部署に優れた社員を配置すると、課題を解決したうえで業務効率を高められます。業務に比較的ゆとりがある部署から人手不足が慢性化している部署に社員を異動させれば、社員一人あたりの負担を軽減され仕事量の不公平も是正されるでしょう。
さらに、社員の希望や能力・特性に合わせた人材配置を行うことで個人のパフォーマンスが向上し、会社全体の業績アップも期待できます。人件費の節約や時間外労働の削減にもつながるでしょう。
経費の削減
人材配置を最適化できると、必要なポスト適正な人材を配置でき、人件費に無駄が少ないので、コスト削減も期待できます。新規採用コストも抑えられる可能性があります。
さらに、戦略的な人材配置は、従業員のスキルアップを後押しできます。いままでアウトソーシングしていた業務があるならば、内製かできるように人を育てられるかもしれません。そうすると外注費用の削減につながります。
従業員のエンゲージメント向上、離職防止
定期的に人材配置を変更することで社員のマンネリを防ぎ、組織も活性化されます。定期的に仕事の環境が変わったり社員の希望に添った業務を担当したりすることで、モチベーション向上にもつながるでしょう。良好な人間関係の維持にも効果的です。
また、人材配置の変更によって社員が持つ本来の能力を発揮できる可能性が高まります。その結果、社員のエンゲージメントを高められると同時に離職防止も期待できます。社員が長期にわたって会社に定着することで業務のノウハウが豊富に蓄積され、会社の競争力も高まるでしょう。
| 関連記事 従業員エンゲージメントとは |
人材育成
人材育成の一環として、計画的に人材配置の見直しが行われる場合があります。ジョブローテーションと呼ばれることもあり、ほかの部署や業務で経験を積ませて社員の潜在能力を発掘する効果も期待できます。最近では後継者の育成を目的に、サクセッションプランという形で人材配置を戦略的に実施する会社も増加傾向にあります。
| 関連記事 サクセッションプランとは |
社員を異なる部署に配置することで強み・弱みが見える化されるため、適材適所の人材配置に活かして更なる業績向上も目指せるでしょう。部署間のコミュニケーションが活性化されるだけでなく、仕事の幅が広がって新たなアイデアが生まれるきっかけにもなります。人材配置は会社・社員を成長させる戦略としても重要な役割を果たしているのです。
誤った人材配置の取り組み方
人材配置を最適化すると、さまざまなメリットが得られますが、一方で誤った取り組み方をしてしまうと期待する効果は得られません。「人材配置が上手に機能していない」「非現実劇な人員計画になってしまう」とお悩みの担当者も多いでしょう。誤った人材配置の取り組み方をご紹介しますので、未然に防ぐ際の参考にしてみてください。
| 1.頻度が高い 2.構築コストをかけてしまう 3.「なんとなく」で決める |
1.頻度が高い
人材配置を頻繁に行いすぎると、従業員のスキルを伸ばしきれないまま、中途半端な人材育成を進めることになってしまうかもしれません。未経験の業務を含む部署に配置された従業員を、短期間で異動させることはなるべく避けましょう。成功体験を得られずに新たな異動が発生すると、精神的な負担となり、早期離職につながる危険さえあるのです。チームとしても生産性を落としてしまう一因となってしまうでしょう。
人材配置はすぐに結果を求めるのではなく、従業員の成長スピードを加味しながら、人材配置の最適化に向けて適宜見直しをすることが重要です。
2.構築コストをかけてしまう
人材配置を行うと、人間関係の構築コストが必然的にかかってしまうものです。信頼関係を一から築き上げるには、手間と労力がかかります。その結果、従業員は精神的に疲弊してしまうかもしれません。
3.「なんとなく」で決める
根拠もなく「なんとなく」で人材配置を決めるのは、最適なの人材配置とはいえません。生産性やエンゲージメントの向上、人材育成など期待する効果が得られないからです。従業員のスキルを把握して配置前にシミュレーションをするなど、人員計画に沿って実施しましょう。
最適な人材配置への取り組み方
人材配置を最適化するための重要ポイントをご紹介します。
| 1.人材情報の整理、可視化 2.スキルや適性の把握 3.従業員へのヒアリングで希望を把握 4.効果測定 |
1.人材情報の整理、可視化
人材配置を最適化するためには、現状の人材データ情報を整理しておくことが大切です。社員の氏名や雇用形態はもちろん、現在担当している業務内容や勤務態度などを項目立てて整理します。
整理した人材情報は人事部で一元管理し、必要に応じて分析データを管理職などの関係者に提供できる体制を整える必要があります。現場の管理職しか人材情報を持っていない状態だと会社としての評価が行えず、部署をまたいだ人員配置が難しくなるからです。人材配置の効果を最大限に発揮するために社員の現況を現場に確認したり、人事評価の結果を集約したりして人員情報を最新に保っておくようにしましょう。
| 関連記事 人材情報の一元管理とは |
2.スキルや適性の把握
社員のスキルや適性の把握も、人材配置の最適化には必要不可欠です。学歴・職歴や志望動機といった面接時の情報をはじめ、保有している資格や社内・社外の研修受講状況、過去の人員配置や人事異動の経緯などをとりまとめておきます。
業務を遂行するために必要な人数や知識・技術の把握も欠かせません。人材配置後に社員が思うようにパフォーマンスを発揮できなければ、生産性だけでなく社員エンゲージメントも低下してしまうからです。人事評価の結果や面談記録も一元管理して、必要な時に確認・比較できる環境を整備しておきましょう。
3.従業員へのヒアリングで希望を把握
あらかじめ社員の希望をヒアリングしておくと、適材適所の配置を検討する材料が増えて人員配置の最適化を実現しやすくなります。会社の人事戦略のもとで異動を決めるケースもありますが、特に転居や通勤時間の増加・勤務時間の変更が伴う場合には、トラブル防止の観点から対象者の理解を得ることが重要です。
現在担当している業務への考え方や今後のスキルアップへの関心などの、キャリアビジョンも把握しておく必要もあります。評価面談以外でも、1on1ミーティングやアンケート・従業員サーベイなどを活用して人員配置に対する社員の意見を聞く機会を設けると、本音を引き出しやすくなるでしょう。
4.効果測定
人材配置の実施後は、効果測定を行いましょう。売上高や成長率、従業員満足度などをアンケートなどでデータを収集し、人材配置の実施前後で比較します。
生産性向上、コスト削減、エンゲージメントの観点から効果が出ているのであれば、成功例として蓄積し、次回の人材配置に活かすとよいでしょう。思ったような効果が見えない場合は、改善方法を検討する必要があります。
| 関連記事 社内アンケートの実施方法 |
人材配置の最適化にはシステムの活用も
人材配置の最適化は、最終的な経営目標の実現のために実施する、戦略的なものです。適切に実施すれば、生産性の向上、経費削減、エンゲージメント向上、人材育成など組織全体の活性化につながります。
人材配置を最適化するには、事前に配置シミュレーションを行うなど現状の把握や従業員へのヒアリングが重要です。実施後の効果測定や見直し、再配置も欠かせません。人材配置表の作成に手間がかかるため、専用のシステムを導入するのがおすすめです。
『スマカン』は従業員一人ひとりのスキルや経験をクラウド上で一元管理し、最適な人材配置に役立つタレントマネジメントシステムです。直感的な人材配置のシミュレーション機能や、人材配置の効果測定に役立つアンケート機能など、多方面から人材配置の最適化をサポートします。自社の人事課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせない…といった無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!