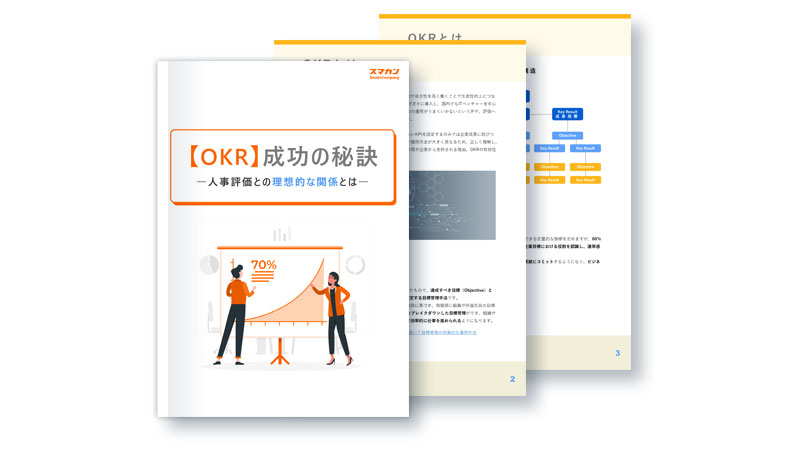- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
MBOとOKRの違いとは? 目標設定やメリット・デメリットも紹介!
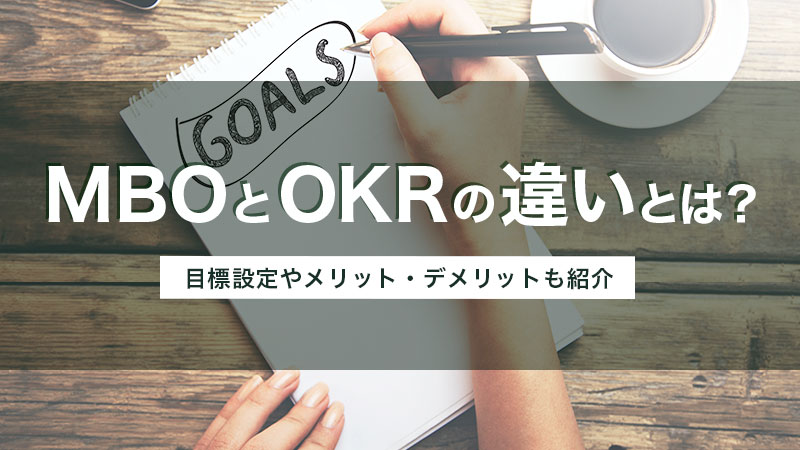
関連資料を無料でご利用いただけます
「MBOとOKRの違いがわからない」
「MBOとOKRどちらを導入すべきなのかわからない」
企業における目標管理の方法として、MBOとOKRはそれぞれ代表的な方法の一つです。
しかし、MBOとOKRについて正しく理解できておらず、両者の違いもよくわからないという経営層や人事担当者もいるかもしれません。
そこで当記事では、MBOとOKR違いに焦点を当てて解説しながら、それぞれのメリットやデメリットも含めてご紹介します。
目標管理がうまくいっていない企業や、目標管理の見直しを検討している企業はぜひ参考にしてみてください。
目次(タップして開閉)
MBOとは
MBO(Management By Objectives)とは、従業員みずからが設定した目標の達成度に応じて、評価や日々の業務管理、人材マネジメントに活用する目標管理方法です。
MBO(目標管理制度)は、目標に対する達成度を基準にしてスムーズでわかりやすい評価ができ、従業員の納得感が得やすく、人事評価にも活用できる点がメリットです。
OKRとは
OKR(Objectives KeyResults)とは、1つの目標(O)に複数の結果(KR)が付随する目標管理の方法です。
目標を達成するために必要な結果を設定し、その内容に従って、各部署や個人レベルに必要な業務や役割を割り振っていきます。
OKRは、目標に対する進捗確認を頻繁に行うため、最終的な評価に対して公平で納得度が高いものになりやすいでしょう。
MBOとOKRの違い
MBOとOKRの違いにはどのような点があるのでしょうか。両者の具体的な違いを確認してみましょう。
MBOとOKRにおける特徴の違い
MBOには、
| ・個人やチームの目標が企業目標とリンクしている ・従業員が目標設定を行い、管理していく ・基本的に目標期間は1年単位 |
という特徴があります。
MBOは、従業員自身が企業の目標とリンクした個人目標を立て、上司からの承認をもらったうえで達成に向けて取り組むものです。
また、目標期間は比較的長いスパン(1年間)で目標達成に向けて取り組み、年度末に自己評価と上司の評価を行います。
OKRには、
| ・Oを達成するために必要な目標がKR ・KRの進捗率でOの達成度も測れる ・基本的に目標期間は四半期 |
という特徴があります。
OKRでは、Oに組織の目指すゴールとして定性的な目標を設定し、KRにはOを達成するために必要な定量的な目標を設定します。そのため、KRの進捗率を測ることで、Oの達成度を測れるようになっています。
また、定期的に進捗確認を行い、四半期ごとに評価を行います。
MBOとOKRにおける目的の違い
MBOの目的は、人事評価の指標として活用することです。達成度や業績によって従業員の報酬が決定される場合も多いでしょう。
また「従業員の成長」や「モチベーション向上」「より公平で客観的な評価」なども目的として挙げられます。
MBOを導入すると、従業員の主体的な動きを促進できるとともに、達成度に基づいて客観的に評価できるため、より透明性の高い公平な評価につながるでしょう。
主体的な行動や納得感の高い評価によって、従業員のモチベーションが向上しやすくなるのです。
| 関連記事 人事評価は好き嫌いで決まるのか? |
OKRの目的は、企業が大きな目標を達成し、業績を伸ばすことです。
そのため、個人レベルの評価や報酬には直接的に反映させません。個人の報酬と連動していると、報酬のために低い目標を設定してしまい、Oが達成できない危険があるため、人事評価や報酬とは切り離すものというのがOKRの考え方です。
| 関連記事 OKRと人事評価の関係 |
MBOとOKRにおける評価頻度の違い
MBOの目標に対する評価は、半年から1年に1度を目安に行います。まとまった期間を通して、目標に対しての結果や貢献度、行動について期末に評価するのです。
OKRの場合は、四半期に一度の頻度で評価を行い、比較的短いスパンで目標や方向性を見直せるため、柔軟な対応ができるとされています。
| 無料ダウンロード資料 目標管理の運用ガイド |
MBOとOKRにおける目標設定の違い
MBOにおける目標は、定量目標と定性目標を組み合わせたり、どちらか一方のみを決めたり、組織や状況によって設定方法はさまざまです。
OKRは、O(最終目的)は定性的に、KR(重要な中間指標)は定量的に設定します。最終的にKRの進捗でOの達成度が測れるため、評価をスムーズに行えます。
MBOとOKRにおける目標の共有範囲の違い
MBOにおける目標の共有範囲は、本人と上司までなど限定的です。同じ部署内や企業全体には、共有されないのが一般的とされています。
一方でOKRにおける目標の共有は、企業や部署など広範囲です。従業員それぞれの目標が組織全体に公表され、達成するための調整や見直しが随時行われます。
MBOとOKRにおける達成基準の違い
MBOの目標の達成基準は、100%以上です。MBOは報酬と連動する可能性があるため、従業員が低めの目標を設定しがちです。たとえ目標が低くても、業績などに影響が出ないよう、確実に達成することが求められるのです。
OKRの達成基準は、60~70%程度です。OKRのO(最終目的)は、ストレッチ目標であることが一般的で、簡単に100%以上達成できないためです。
MBOとOKRのメリット・デメリット

MBOとOKRにおいてメリットとデメリットにはどのような点があるのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットの違いにも注目しながら確認してみましょう。
MBOのメリット
MBOのメリットは、以下の通りです。
| ・従業員の自主性が向上する ・従業員のモチベーションが向上する ・評価しやすい ・業務管理がしやすい |
MBOは従業員本人が目標を立てるため、自主的に考えて行動する姿勢を促せ、モチベーションを維持しやすいのがメリットです。
また、目標の達成に応じて評価するMBOは、誰から見ても判断基準がわかりやすく、従業員からの納得が得られやすい傾向にあります。それによって、従業員エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。
さらにMBOは、最初に会社の目標とリンクした内容で設定されます。上司の立場としては部下の業務管理がしやすく、マネジメントにおいてメリットが多いでしょう。
MBOのデメリット
MBOのデメリットは、以下の通りです。
| ・目標に関係のない業務の優先度が低くなりがち ・目標を低く設定するケースがある ・管理者や上司の負担が大きい ・変化に対応しにくい |
人事評価と連動しているMBOは、目標に関係する業務が優先されがちで、従業員が達成しやすいレベルで目標を設定してしまう傾向にあるため、人材育成の観点でデメリットといえるでしょう。
マネジメント担当者も、目標設定から評価まで部下をサポートする必要があり、大きな負担を抱えてしまいます。
また、MBOは1年単位で目標に取り組むため、突発的なトラブルや変化に対応しにくいという懸念もあります。
OKRのメリット
OKRのメリットは、以下の通りです。
| ・目標設定がスムーズ ・業務の優先度が明確 ・柔軟な対応が可能 ・従業員エンゲージメント向上 |
OKRは全体が達成したい目標(O)から逆算して、部署や個人の目標(KR)を設定します。
あらかじめOが示されていれば、KRはOの達成に必要な指標を数値化すればよく、比較的スムーズに目標が決まります。
従業員は、会社が示す最終目標から業務の優先度を理解しやすく、効率的に取り組めるでしょう。また、会社の目標に向かって取り組む姿勢を促すことができるため、企業全体で団結力や連帯感が育まれ、エンゲージメント向上も期待できるでしょう。
四半期のスパンで目標を設定し、その目標を随時見直すのも、柔軟に対応できるという点でOKRのメリットといえます。
| 関連記事 OKRとKPIの違いとは |
OKRのデメリット
OKRのデメリットは、以下の通りです。
| ・運用に手間がかかる ・従業員のモチベーション低下の危険性もある |
OKRでは、導入する際にOKRの仕組みを説明したり、定期的に進捗を確認をしたりする必要があるため、運用に手間がかかります。
また、最初に高い目標を設定して60%程度の達成率を求めるOKRの特徴は、従業員のモチベーション低下につながる可能性も否めません。結果的に難易度が高過ぎると感じる従業員も多く、達成率が低いと意欲を削いでしまうリスクがあるのです。
MBOとOKRの課題点
MBOとOKRにおいて、共通の課題をご紹介します。どちらかの目標管理方法を導入する場合は、課題も意識して取り組みましょう。
人事評価へ反映する場合は工夫や配慮を行う
MBOもOKRも、最終的には企業の目標達成や業績向上につなげることが大切です。
特にMBOは、評価や報酬と連動するため、人事評価を行うためのものと捉えがちですが、本来は会社の目標達成を軸にしなければなりません。
MBOの運用では、目標を低く設定してしまう傾向があります。また、逆に高い目標を掲げたために、達成率が悪く、評価や報酬に影響してしまうこともあるでしょう。
そのためMBOもOKRも人事評価に反映させるなら、どの程度反映させるのか、目標の難易度をあらかじめ設定するなどしましょう。さまざまな工夫や配慮をすることで、バランスの取れた人事評価につながります。
上司と部下のコミュニケーションを大切にする
MBOもOKRも、上司(目標管理者)と部下の信頼関係は重要です。
目標設定の際はもちろんのこと、目標達成のために相談やサポートの機会が必要であるためです。上司と部下の間でコミュニケーションが噛み合わないと、最終的に結果や評価に対して不満を抱く原因にもつながりかねません。
日常的にコミュニケーションを取り合って信頼関係を深めておくと、課題の早期発見や目標の修正など、達成に向けた行動をいち早く取れるでしょう。
MBOとOKRどちらがいいのか
MBOとOKRはどちらも特徴とメリットがあるため、一概にどちらの方が優れているとは言い切れません。会社の方向性や目的によっても、MBOとOKRどちらを選ぶべきかは異なります。
目標の達成度によって従業員の評価や報酬に反映させたいならMBO、会社としてより高い目標を達成や業績を伸ばすために個人レベルまで細分化した取り組みを目指したいならOKRがおすすめです。
MBOとOKRは併用できる
MBOとOKRは併用することもできます。MBOは人事評価と連動した目標管理制度であるのに対し、OKRは自社の目標や業績を達成させる管理方法であるため、双方を上手に取り入れ、デメリットを補い合うこともできるでしょう。
どちらにもメリット、デメリットがあるため、無理にどちらか一方を選ぶのではなく、両方を導入して取り組むのもおすすめです。
MBOとOKRの効果を最大化させる共通のポイント
MBOもOKRも効果を最大化させるために、押さえておくべき共通のポイントをご紹介します。
明確な目的を従業員と共有する
MBOもOKRも導入する目的を明確にして、従業員に共有しなければなりません。どちらのやり方も、最終的には組織の目標を達成するために、会社全体で目的を理解することが重要です。
MBOは、従業員みずから目標設定を行い、達成度を人事評価に反映します。しかし、達成度だけを見てそのまま人事評価に反映すると、達成度が低かったときは著しく評価が下がってしまい、従業員の意欲が低下する恐れがあります。反対に達成度が高いときは他者から「目標が低すぎたのではないか」といった誤解や不満感、不公平感を招く恐れもあるでしょう。
MBOは人事評価と連動するものの、もっとも重要なのは企業の目標を達成することです。従業員のモチベーションやエンゲージメントを低下させないためにも、達成度そのものだけでなく、達成に向けて取り組む姿勢や成果に至るまでのプロセスも加味するようにしましょう。
OKRは会社として大きな目標を達成し、業績を伸ばすための管理手法です。会社全体の目標をまず設定して部署、チーム、個人の目標を逆算して設定していきます。従業員一人ひとりの目標が、会社全体の目標の達成につながっている点を理解してもらうようにしましょう。
目標管理業務をシステムで効率化する
MBOやOKRの運用は、目標管理システムやタレントマネジメントシステムを活用すると効率化できます。
目標の設定や進捗を確認する1on1の記録などを一元管理し、可視化できるため、日々目標を意識した行動が取りやすくなるでしょう。
集約しているデータを活用して、人材育成や配置転換などにも活用できれば、戦略人事の遂行にも役立ちます。
『スマカン』で目標の管理をサポート
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、カスタマイズ自由な目標管理シートを使って、組織に適した目標管理をサポートします。
OKRやMBOなど各手法に合わせたテンプレートが用意されており、直感的な操作で柔軟に変更や設計ができるようになっています。
運用開始までの構築サポートも充実しており、担当者の手間を最小限に抑えて始められます。
『スマカン』は、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織の強化につなげられるでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
MBOとOKRには、目的や評価頻度、期間、達成基準など、さまざまな点に違いがあります。
MBOは目標に対する達成度を判断基準にスムーズな評価ができ、従業員の納得感も得やすく、人事評価にも活用できる点がメリットです。
OKRは会社の目標から逆算して最終的に個人目標を設定するため、組織として団結しながら取り組めます。目標に対する進捗確認を随時行い、最終的な評価も公平で納得感のあるものになりやすいといえるでしょう。
どちらにもメリットデメリットがあるため、両者の特徴や細かな違いを理解したうえで、自社の目的や課題に合わせて検討してみましょう。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!