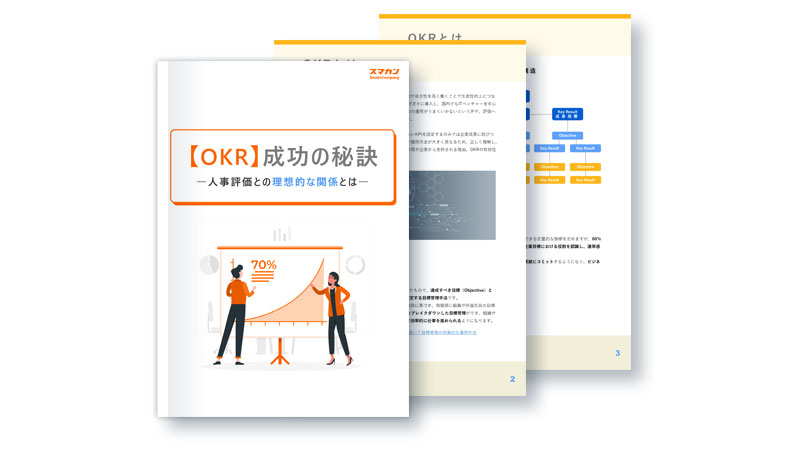- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
定性評価とは? 人事評価における方法や定量評価との違い、注意点を解説

関連資料を無料でご利用いただけます
企業の人事評価において「定性評価の運用がうまくいかない」「どんな項目を設定したらよいかわからない」という方は少なくないでしょう。
当記事では、人事評価における定性評価の方法や定量評価との違い、注意点について解説しします。企業の人事担当者や経営者、マネジメント層の方々は、ぜひ参考にしてください。
目次(タップして開閉)
定性評価とは
定性評価とは、数値であらわせないものに対する評価や、その評価方法のことです。個人の性質や耐性、仕事に対する姿勢や気持ち、業務方針や目標達成までのプロセスなど、目に見えないものや客観的に形にしづらいものを評価する際に定性評価を用います。
定性評価の具体例
定性評価における観点ごとに、評価対象の具体例をご紹介します。
| ・任された業務にいち早く取り組み、終わらせている ・部下に営業ノウハウを積極的に教えている ・営業目標の達成に向けてリーダーシップを発揮している ・顧客からのクレーム対応を引き受け、最後まで責任を持って対応している ・いつも清潔感のある身だしなみと笑顔で、お客さまからの評判もよい |
上記のような、数値であらわせない定性的な部分を見逃さずに評価するのはとても重要です。
定性評価と定量評価
定性評価とその反対である定量評価について詳しく解説します。
定量評価とは
定量評価とは、数値に基づいた評価や、その評価方法、その評価方法で導き出される評価結果そのものを指します。
定量評価は人事評価、マーケティング、市場調査、統計調査、満足度調査と、あらゆるビジネスシーンで活用されています。また経営判断や学術研究などの分野でも、重要な役割を担っています。
定性評価と定量評価の違い
定性評価と定量評価、2つの評価の違いを解説します。
定性評価は「数値であらわせないものに対する評価」であり、定量評価は「数値であらわせるものに対する評価」です。
| 定性評価 | 行動や成果を数値化できないもの (業務に対する意識、姿勢、工夫など) |
|---|---|
| 定量評価 | ○件、○%など数値であらわせるもの (目標達成率、顧客獲得件数、コスト削減率など) |
定性評価と定量評価の違いを具体的に見てみましょう。
「お客様のニーズを引き出す対話をするよう努めた結果、顧客獲得件数は1.5倍となった」というケースでは、前半の「お客様のニーズを引き出す対話をするよう努めた」ことは定性評価です。「顧客獲得件数は1.5倍となった」ことは定量評価です。
| 関連記事 定量評価とは?についても解説 |
定性評価向きの人事評価の項目
企業の人事評価において定性評価に向いている項目をご紹介します。
定性評価向きの項目は、仕事に向き合う姿勢や組織内での役割認識、さらには業界や職種、地域を超えて普遍的に求められる能力を示すものです。
具体的には、コミュニケーション力、リーダーシップ、共感力、積極性、協調性、創意工夫、スピード、規律性、責任感、知識が挙げられます。
定量評価向きの人事評価の項目
反対に、人事評価において定量評価に向いている項目をご紹介します。
定量評価に向いている項目は、目に見えて分かる具体的な数値で表現できるものです。
具体的には、売り上げ、受注件数、アポイントメント獲得率、クレーム件数などが挙げられます。
人事評価では2つを組み合わせるのが大切
人事評価では、定性評価と定量評価の2つを組み合わせることが大切です。
先述の通り、定性評価と定量評価は評価対象が全く異なっています。そのため、どちらか1つだけを採用した場合、評価しきれない成果や要素が出てきてしまい、偏った評価内容となってしまうでしょう。偏った人事評価は、社員のモチベーションにも影響を与え、ひいては企業の評価を損ねることにもつながります。
公正な人事評価を行うためにも、定性評価と定量評価の2つを組み合わせることがポイントといえます。
定性評価の評価方法
定性評価は定量評価と異なり、数値であらわせないので評価が難しいと考える方も多いかもしれません。そこで定性評価の評価方法やポイントを詳しく解説します。
項目設定
定性評価では、評価する項目を明確に設定する必要があります。評価するべき項目があいまいだと、評価自体の信頼性が薄れてしまうでしょう。
定性評価の項目例をご紹介します。
| スピード | ・担っている業務にすぐに対応しているか ・報連相を適切に素早く行っているか |
|---|---|
| 協調性 | ・チーム内で協力し合っているか ・必要に応じて社外の人間とも適切に連携できているか |
| 積極性 | ・業務に主体的に取り組んでいるか ・苦手な業務、不得意な業務にも前向きに取り組んでいるか |
| 責任感 | ・担っている業務を最後まで遂行しているか ・締切のある業務の期日を守れているか |
| 規律性 | ・服装などの身だしなみや言葉遣い、振る舞いに問題はないか ・勤怠管理や時間厳守などは適切か ・資料や職場環境の整理整頓ができているか |
| 創意工夫 | ・課題に気づき、改善案の提案などができているか ・業務の中で工夫を重ねているか |
| 知性 | ・課題に気づき、改善案の提案などができているか ・業務の中で工夫を重ねているか |
目標設定
基準があいまいになりがちな定性評価をスムーズに行うためには、目標設定が有効でしょう。目標がなければ、何をどの程度評価するべきかが判断しづらいからです。なお、目標設定と同時に、達成までの期日を設ける必要があります。
定性評価での目標設定には、2つの手順があります。
1.組織目標と職位目標を設定する
まず始めに、会社として目指す「組織目標」と、社員個人の役職に合わせた「職位目標」を設定します。
2.必達レベルと努力レベルを設定する
次に、必ず達成したい「必達レベル」と、ここまで達成できればさらによいという「努力レベル」を設定します。
評価基準と点数のつけ方
目標設定が終わったら、定性評価を行う際の基準と点数を設定します。一定の基準に沿って客観的に定性評価ができるよう、基準と点数を決めるのがポイントです。
評価基準と点数のつけ方の一例をご紹介します。
| 必達レベルに未達 | 1点 |
|---|---|
| 必達レベルに到達し、努力レベルに未達 | 2点 |
| 必達レベルに到達し、努力レベルにも到達 | 3点 |
このように、評価が高くなるにつれて点数が高くなるように設定します。また、評価基準の点数は、自社の状況に合わせて、4段階や5段階にするなど適切に設定します。評価基準は、先に設定した評価項目ごとに設けます。
定性評価の書き方・具体例
実際に定性評価を行う際の書き方と具体例をご紹介します。
定性評価では、結果だけでなくそこに至る過程も評価するのが一般的です。定性評価をほかの評価と上手に組み合わせると、社員は「自分をよく見てくれている」と感じ、組織への信頼が増し、モチベーションや生産性のアップにもつながるでしょう。
定性評価においては、先述した評価項目ごとに評価基準と点数を設け、達成度を測ります。評価者が評価を伝える前に、被評価者が自己評価を行うと、より効果的といわれています。
「売り上げアップの背景を評価するとき」の具体例
売上アップしたことについて、その成果に至った背景を定性評価する場合の具体例をご紹介します。
| ・顧客へのフォローを強化し、口コミでの紹介を増やしていった ・商品をより分かりやすく伝えるHPの導線を改善し、問い合わせ件数が増えた ・直接売上に貢献しないが、必要な雑務の効率化を促進した |
「経験の浅い新入社員の評価するとき」の具体例
業務経験の浅い新入社員を評価する際は、仕事へのモチベーションや協調性、規律性などを評価します。業務経験が浅いため、数値で測れる業績や売上に結びつくサポートが期待できないからです。
| ・雑務を積極的に引き受け、ほかの社員がコア業務に集中できる環境をつくった ・商品知識についての勉強会を自主的に開催した ・自分のデスク周りにとどまらず、こまめに清掃し、オフィスの美化に努めた |
定性評価のメリット
定性評価を人事評価に取り入れるメリットは、どのようなものがあるでしょうか。主なものを3つご紹介します。
数値であらわすことができない仕事を評価できる
定性評価は定量的に評価しにくい業務や職種を評価できます。総務職や経験が浅い社員など成果を数値であらわしにくい社員は、定性評価の比重を上げると、公正な評価につながりやすくなるでしょう。
また、目に見える結果がすぐに出なくても、評価に値する業務や行動について、評価できます。
モチベーションアップにつながる
定性評価を取り入れると、従業員のモチベーションアップにもつながる点はメリットです。被評価者が自身の役割や周囲からの期待を理解しやすくなるので、取り組むべき業務に集中できるからです。
定量評価だけでは網羅できない点を評価できると、不公平感も緩和する可能性があるので、モチベーションの維持や向上を後押しするのです。
評価頻度を自由に設定できる
定性評価では、評価者の裁量で評価のタイミングを決められる点もメリットでしょう。必然的に、評価頻度も自由に設定できることになります。
一方、定量評価の評価時期は、設定した数値目標の結果が出るタイミングである場合が多いです。
定性評価のデメリット
反対に定性評価のデメリットには、どのようなものがあるでしょうか。主なものを2点ご紹介します。
評価の難易度が高い
定性評価は、定量評価よりも評価の難易度が高いといえます。定性評価は、定量評価のように客観的に判断する数値基準を設定できないためです。
定量評価は数値結果を見て判断できますが、定性評価は結果を導き出した過程も踏まえて評価しなければいけません。
定性評価は評価者の経験やスキルに左右される傾向にあるため、評価者の負担は大きく、評価スキルの向上も求められる点はデメリットでしょう。
評価に対する不満が生まれやすい
定性評価は評価の難易度が高いゆえに、不満が生まれやすい側面もあります。
定性評価の基準は、評価者スキルに依存しがちになるため、あいまいになりやすいといえます。そこで、可能な限り統一的な評価項目を設け、いかに納得感を得るかがポイントになります。
| 関連記事 人事評価に対する不満要因とは |
定性評価制度を設計する手順
定性評価を取り入れるにあたって、制度設計の手順をご紹介します。
1.現行制度の課題を洗い出し、経営課題と照らし合わせる
現行の人事評価制度を見直し、課題を洗い出します。洗い出された人事課題を経営課題と照らし合わせ、取捨選択と深掘りをしていきます。
2.経営層・人事部門において評価制度の方針を決める
経営層または人事部門において、定性評価の制度方針を決めます。中長期的に組織力を向上させるためにも、目先の成果だけを追わないようにしましょう。
3.評価項目を決める
定性評価の項目は、成果(業績)評価、能力評価、情意評価という3つの枠組みを基準に、自社に必要な評価項目を決めます。先にご紹介した「スピード」「協調性」などの定性評価の項目例も、ぜひ参考にしてみてください。
4.評価方法を決める
定性評価の運用に適した評価手法を決めます。
評価手法の例としては、目標管理制度(MBO)、コンピテンシー評価、360度評価、ノーレイティングなどがあります。絶対評価と相対評価、どちらを採用するかも調整しましょう。
| 人事評価の方法に関する記事一覧 MBO(目標管理制度)とは コンピテンシー評価とは 360度評価とは? ノーレイティングとは? 絶対評価と相対評価の違い |
5.評価者へのトレーニングを実施する
評価制度の運用を始める前に、評価者トレーニングを実施します。主な対象者は、評価を行う管理職以上となるでしょう。360度評価も併用する場合は、一般社員も対象です。この場で、人事評価制度の目的や意義、人事評価エラーについても理解を得るといいでしょう。
定性評価を人事評価に導入する注意点
定性評価を人事評価に導入する際の注意点をご紹介します。
目標設定時の注意点
定性評価の目標設定時は、以下の点に注意しましょう。
| ・「いつまでに」という明確な達成時期を設定する ・職種や役割に応じて、定量目標と定性目標を使い分ける ・少し頑張れば到達できそうなストレッチ目標も設定する ・DO目標(〜をする)ではなく、BE目標(〜な状態にする)も設定する |
変化の速い現代のビジネスシーンでは、目標設定時と状況が変わってしまうこともあるでしょう。毎月のフォローミーティングなど、定期的に調整する機会を設けるといいかもしれません。
評価時の注意点
定性評価で実際に評価する際は、以下の点に注意しましょう。
| ・被評価者との関係性(好き嫌い)を加味せず、客観的な事実に基づく ・評価項目ごとに独立して評価する(項目Aの結果を項目Bに影響させない) ・360度評価など多面評価も取り入れる ・評価者自身に評価の癖があるなら自覚する ・人事評価エラー・バイアスを理解する ・直近の印象に惑わされず、評価期間全体で評価する ・被評価者に自己評価や振り返りを促し、自分ごととして考えてもらう |
先に言いにくいことを伝え、最後に褒めたり、期待を投げかけたりして締めると、前向きな定性評価の制度になるでしょう。中長期的な人材育成という観点から、評価のフィードバックを通じて期待と課題を従業員本人に伝えるといいかもしれません。
| 関連記事 人事評価と好き嫌いの関係性 |
人事評価の公平性を高めるには、タレントマネジメントシステムも
主観的な感情に左右されがちな定性評価ですが、そもそも公平な人事評価制度の運用には、タレントマネジメントシステムの導入も一案でしょう。
タレントマネジメントシステムとは、人材情報を集約し、従来より効率的で実感のある人事評価や人材育成を目指すものです。
『スマカン』は、社員データを顔写真つきでクラウド上に一元管理し、情報を直感的に把握できたり、人事評価の効率的な運用をサポートしたりするタレントマネジメントシステムです。
一人ひとりの能力や評価結果、設定目標を紐づけて管理できるので、公平性のある人事評価や今後の育成方針を立てるのにお役立ていただけます。目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
定性評価を人事評価に取り入れると、従業員の数値であらわせない過程や行動、意識などを評価できます。定量評価と併用すると、より公平で適切な人事評価が行えるでしょう。
ただし定性評価は、客観的な指標を設ける定量評価に比べると、評価者の負担が大きく評価スキルが求められます。そこで、明確な評価項目の設計や目標設定が重要といえるでしょう。
適切な項目設定を行い、多面評価や評価者研修も取り入れながら、より精度の高い定性評価を人事評価に取り入れてはいかがでしょうか。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!