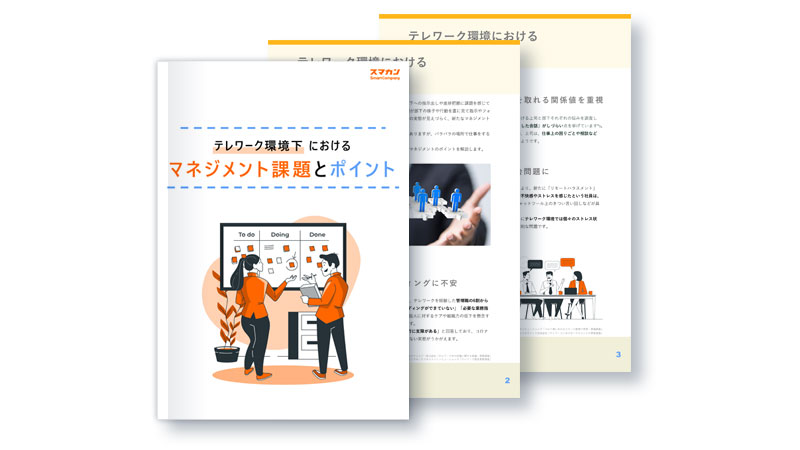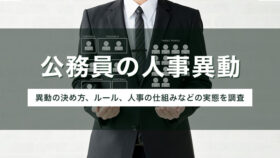- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
ハイブリッドワークとは? テレワークとの違いやメリット、導入ポイントもご紹介!

関連資料を無料でご利用いただけます
ハイブリッドワークとは、オフィスワークやテレワークなど、複数の働き方を組み合わせる働き方です。コロナ禍や働き方改革の影響で、ハイブリッドワークの導入を検討する企業も増えてきました。
しかし、ハイブリッドワークがより注目されるようになったのは、働き方改革や新型コロナウイルスの流行以降であるため、ハイブリッドワークの詳しい内容がわからないというケースも少なくありません。
本記事ではハイブリッドワークの意味や特徴を解説しながら、メリットやデメリット、始め方、運用ポイントや適切な環境もご紹介します。
目次(タップして開閉)
ハイブリッドワークとは
ハイブリッドワークとは、会社に出勤するオフィスワークと場所を選ばずに仕事ができるテレワークを組み合わせる働き方です。
たとえば、週5日勤務の中で、2日をオフィスワーク、3日をテレワークなどと組み合わせることができます。柔軟な働き方を選択できるとともに、ライフワークバランスも整えやすい働き方として特に近年注目されるようになりました。
また、従業員の希望に応じて働き方を決められるケースもあり、希望者だけがテレワークをするという方法で、状況に合った働き方ができるのも特徴の一つです。
ハイブリッドワークが注目される背景
ハイブリッドワークが注目されている背景は、新型コロナウイルスの影響によって各企業に浸透したテレワークです。
テレワークは、場所を選ばずに働ける方法としてメリットがある一方で、コミュニケーションや運用の側面で課題も見えてきました。
そこで、より最適な働き方を模索するなか、従来のオフィスワークとテレワークのそれぞれのメリットを取り入れるられるハイブリッドワークが注目されるようになりました。
ハイブリッドワークのメリット
ハイブリッドワークには、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットを確認してみましょう。
フレキシブルな働き方による業務効率化
ハイブリッドワークでは、自分の体調や家族の都合に合わせたフレキシブルな働き方を選択できます。最適な環境で働けるため業務効率化が進みます。
在宅で仕事ができると、体調不良で外出がつらいときや子どもが急に発熱したときなどでも、休暇を取る必要がなくなります。その結果、1人の従業員が休んだために業務が滞ることも減るはずです。
従業員満足度・エンゲージメントの向上
ハイブリッドワークは、従業員それぞれの事情を考慮した働き方です。そのため、従業員の会社への満足度やエンゲージメントが高まり、生産性向上につながります。
また、フルタイム勤務が難しい従業員でも働き続けられる可能性があり、勤務形態による不満を解消し、優秀な人材の離職を防ぐ効果も期待できます。
多様な働き方の実現
多様な働き方を整備しておくと、社会情勢の変容に柔軟に対応できます。震災の発生や疫病の流行など非常事態への備えにもなるでしょう。
また、最近は従来とは異なる働き方を求める人も増えてきました。育児や介護と両立したい従業員や、プライベートを充実させたい従業員でも柔軟に働けることは、企業のPRポイントです。
ハイブリッドワークが充実した企業には、採用活動の際に優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
従業員のモチベーションや満足度が向上
ハイブリッドワークを導入することで、従業員のモチベーションが向上し、成長する可能性が高まります。一人ひとりのモチベーションや主体性が向上すると、目標も達成しやすくなるはずです。
柔軟な働き方ができると、ライフワークバランスも整いやすくなり、従業員満足度にもよい影響が生じるでしょう。
生産性の向上
ハイブリッドワークは、生産性の向上にも効果的です。オフィスワークとテレワークを組み合わせることで、従業員は業務内容に応じて効率的に仕事を進められます。
会議や周囲との調整が不要な業務を行う際はテレワーク、商談や打ち合わせなどが必要な場合はオフィスワークを選ぶなどすると、より生産性を高めて業務に取り組めるでしょう。
人材確保
ハイブリッドワークによって柔軟な働き方が実現すると、優秀な人材の確保にもつながります。
柔軟な働き方ができる環境では、今いる従業員の満足度や採用活動における企業イメージが向上しやすくなるためです。多くの企業で人材不足が課題となるなか、ハイブリッドワークによって人材不足の解消にも効果が期待できます。
ハイブリッドワークのデメリット
ハイブリッドワークには、デメリットがあるのも事実です。具体的にどのようなデメリットがあるのか確認してみましょう。
業務状況を把握するのが難しい
ハイブリッドワークのデメリットは、従業員の業務状況を把握するのが難しいところです。特にオフィス以外の場所にいる従業員と連携しにくい場面があるでしょう。
緊急性の高いタスクや顧客からのクレームが発生した際、速やかに対応できる従業員がいないという事態にもなりかねません。
評価制度に不満が生じる可能性がある
ハイブリッドワークのデメリットとして、評価に不平不満が募る可能性が指摘されています。
どんなに公平な評価を意識していたとしても、オフィスワークとテレワークでは、評価が分かれてしまう可能性があります。
たとえば、マネジメント層が出社していることが多い場合、出社している従業員の方が業務状況が把握しやすいため、評価しやすいというケースです。
このような状況では人事評価の公平性や客観性が損なわれ、最悪の場合、優秀な人材が離職してしまう原因にもなってしまうでしょう。
勤怠管理が複雑になる
ハイブリッドワークのデメリットには、テレワークとオフィスワークが混在するため勤怠管理が複雑になりがちな点が挙げられます。
そのため、誰がいつ出社するのかチーム全体で把握できるようにしておくなど、連携を取る必要があるでしょう。
社内のコミュニケーションが不足しやすい
ハイブリッドワークのデメリットとして、社内コミュニケーションが希薄になってしまう懸念点もあります。テレワークが多いと、従業員同士のコミュニケーションが希薄になりやすいとされています。
連絡や相談をしたいと思っても、チャットやメール、電話を使わなければならず、すぐに解決できない場合もあるでしょう。
コミュニケーション不足は従業員エンゲージメントを低下させる恐れがあります。
その結果、組織力が低下することさえあるため、従業員がコミュニケーションを積極的に取り合えるような機会を設けるなど工夫しましょう。
セキュリティ面の不安
ハイブリッドワークのデメリットとして、テレワークによるセキュリティ面の不安も捨てきれないでしょう。テレワーク環境でのセキュリティ対策は各企業にとって大きな課題といえます。
情報漏えいを発生させないように、適切なリモート環境を整備するとともに、従業員のITリテラシーを高めるための教育コストをかける必要があります。
ハイブリッドワークの導入方法
ハイブリッドワークのメリットとデメリットを踏まえて、ハイブリッドワークの導入方法をご紹介します。ポイントを押さえながら円滑に業務を回す方法を理解しておきましょう。
社員それぞれの業務状況を把握する
まずは従業員それぞれの業務状況を把握します。業務内容がテレワークに適しているか、在宅に切り替えて問題ないかなどを確認しましょう。
ハイブリッドワークにすることで、特定の従業員に業務が集中する事態は避けなければなりません。
チームのメンバーが別々の場所で仕事をする場合、うまく連携が取れなくなる可能性が高まります。報連相などビジネスの基本ルールを押さえて、事前にルールを決めておくとよいでしょう。
リモート環境を整備する
業務がスムーズに進むようにリモート環境を整備します。その際に便利なのが、Web会議システムや勤怠管理システムです。
特に在宅におけるテレワークは、情報漏えいや不正アクセスなどの懸念があります。セキュリティ対策を実施したり、テレワーク組の従業員にITリテラシー研修を実施したりする必要があります。
同時に、社内にITスペシャリストを常駐させるとよいでしょう。在宅でのテレワークでは、突然インターネットがつながらなくなったり、Web会議システムなどで不具合が生じたりすることがあるためです。
このようなネットトラブルに関する問い合わせに対応できる人材がいるとよいでしょう。すみやかに人材を確保できない場合は、アウトソーシングするのも一案です。
ツールを活用する
従業員同士のコミュニケーションを円滑にし、業務を効率化ためのツールを活用すると便利です。
具体的には、従業員同士が気軽にテキストをやり取りできるチャットツールや、従業員一人ひとりの進捗状況を見える化するタスク管理ツールなどです。
これらの便利ツールはテレワークだけでなく、オフィスワークを改善する際にも役立ちます。
ハイブリッドワークを成功させるポイント

ハイブリッドワークを成功させるには、さまざまなポイントがあります。あらかじめ成功のためのポイントを押さえて効率的に進めましょう。
従業員の管理を行う
ハイブリッドワークを成功させるうえでは、従業員の業務状況やモチベーションを管理することが必要です。そのためにはサーベイを実施するとよいでしょう。
サーベイは、企業における組織課題や従業員の意識など、物事の全体像を把握するために広く行う計測や測定です。従業員からデータを集めることで課題を把握し、その結果に合わせた適切な施策を実施して組織の改善や強化につなげます。
サーベイの中でも、従業員が会社や自社製品に対してどの程度の愛着心を持っているかを調べるエンゲージメントサーベイや、職場環境や人間関係に対する従業員満足度を把握する従業員調査は特に役立ちます。
ハイブリッドワーク導入直後は、1週間から1か月おきに簡単な質問を繰り返し行うパルスサーベイも有効です。従業員の変化や企業の問題点をリアルタイムに把握し、大きな問題に発展する前に改善しましょう。
事前にある程度のルールを決めておく
ハイブリッドワークを成功させるには、事前にルールを設定しておくことが大切です。最低限のルールとしては、「勤務場所」「労働時間」「評価方法」などが挙げられます。
注意点として、細かすぎるルールを設定してしまうと、管理が大変になったり従業員も働きにくくなったりするため、ハイブリッドワークのメリットが活かされません。
まずは最低限のルールのもと運用し、途中経過や従業員の声を踏まえてルールを追加するなどするとよいでしょう。
セキュリティに関するリテラシーを高める
ハイブリッドワークを運用する際は、テレワークを安全に行うためにもセキュリティに関する教育を実施しましょう。
業務の属人化を防ぐ
ハイブリッドワークでは、業務の属人化を防ぎ、リスク回避の準備をしておくことが大切です。
たとえば、顧客や取引先への緊急対応が必要な際、テレワークによって担当者が不在であれば十分な対応が出来ない場合もあるかもしれません。
対応できる責任者やメンバーが最低1人は出社しておくようにルールを決めたり、業務に関するマニュアルを策定したり、属人化を防ぎつつ緊急時に備えましょう。
オフィス環境を整備する
ハイブリッドワークを成功させるためには、適応できる環境を整備するのが重要なポイントの一つです。
たとえば、フリーデスク制を採用したり、遠隔でも問題なく活用できるシステムやツールを導入したりする方法があります。
オフィスワークでもテレワークでも、問題なく業務ができるよう環境を整備しましょう。
ハイブリッドワークで必要な環境
ハイブリッドワークを導入する場合、環境整備が重要ですが具体的にはどのような環境が必要なのでしょうか。ハイブリッドワークを導入するうえで、整えておきたい環境についてご紹介します。
運用ルールの周知
ハイブリッドワークを導入する際は、ハイブリッドワークに関するルールや社内規定を策定し、従業員全員に周知して理解してもらうことが大切です。
適切なルールをバランスよく設定することで、柔軟な働き方を認めるハイブリッドワークも成功しやすくなるでしょう。
フリーアドレスの導入
ハイブリッドワークでは、オフィスの席を固定しないフリーアドレス制の採用がおすすめです。
オフィスへの出社とテレワークが混在するのであれば、従業員の席を固定することは必ずしも必要ありません。出社する日は、業務状況や周囲の状況を踏まえて自由な席で働けるような環境にしておくとよいでしょう。
ただし、オフィスワークを希望するメンバーの場合、固定席がよいという場合もあるでしょう。いきなり全面的にフリーアドレスにするのではなく、オフィスの一部から始めてみてもよいかもしれません。
社内コミュニケーションの活性化
ハイブリッドワークでは、社内コミュニケーションの活性化がよりいっそう重要となります。
テレワークを選ぶ従業員が多ければ多いほど、工夫して意図的にコミュニケーションの機会を設けるようにしましょう。
たとえば、Web会議システムを使った1on1ミーティングや朝会などの実施が考えられます。社内イベントの開催や月に1回は部署全員が出社する日を設定するなどのルール設定も有効です。
組織として一体感を持つためにも、従業員同士のコミュニケーションを大切にしながらハイブリッドワークを運用しましょう。
評価制度の見直し
ハイブリッドワークでは、企業がそれまで運用してきた人事評価制度が機能しないこともあり注意が必要です。
たとえば、評価者がオフィスへ出社することが多い場合、同じように出社している社員を評価する偏りが生じる危険性があります。
オフィスワークなら、日頃から勤務態度や業務状況を把握しやすく、対面で話す機会も多いため、必要以上に評価が高くなりやすいでしょう。一方、テレワークは状況がわかりにくく、コミュニケーションが取りにくい場合もあるため、評価が低くなってしまうかもしれません。
評価への不満は、従業員の離職リスクにもつながります。そのためハイブリッドワークを導入する企業では、評価制度を見直したうえで、客観的な成果に基づく評価制度を取り入れるなど制度設計を見直しましょう。
ハイブリッドワークの事例
ハイブリッドワークを導入する企業の事例をご紹介します。ハイブリッドワークを導入しようと検討している企業は、他社の事例を参考にしてみましょう。
株式会社ベネッセホールディングスの例
株式会社ベネッセホールディングスは、1995年からスーパーフレックス制度を、2009年から在宅勤務制度を導入し、柔軟な働き方を推進してきました。
2020年2月以降は、withコロナ時代の新しい働き方として、出社と在宅を組み合わせたハイブリッド勤務を導入しています。
参照:『ベネッセコーポレーション、 出社・在宅の「ハイブリッド勤務」環境を推進』 株式会社ベネッセホールディングス
株式会社サイバーエージェントの例
株式会社サイバーエージェントでは、2020年6月から全従業員を対象に「リモディ」を運用しています。
リモディとは、特定の曜日をリモートワークとする施策です。移動をともなう社内会議や大人数の会議はビデオ会議に変更するなど、リモートワークの利点を活かしながら、チームワークや活気のよさを両立させています。
福井県の例
行政機関でもハイブリッドワークの導入が進んでいます。福井県では、2019年4月から会議のオンライン化やテレワークの実践など先駆的な働き方改革を展開しています。
週1回以上在宅勤務を行うこととし、在宅勤務でも秘匿性の高い情報を取り扱えるシステムも導入し、ハイブリッド施策を成功させました。
参照:『知事が率先してテレワーク。福井県の先進的な働き方改革を支えるMicrosoft 365』
まとめ
ハイブリッドワークは、オフィスワークとテレワークを組み合わせる新しい働き方です。
導入を検討している場合は、デメリットや運用ポイントを理解したうえで、あらかじめリスクを抑えることが大切といえます。
本記事でご紹介した内容を踏まえ、あらかじめデメリットやリスクを解消できるように準備したうえで始めましょう。
ハイブリッドワークの推進ポイントとして、さまざまな業務をシステム化することが挙げられます。
『スマカン』は、従業員一人ひとりの業務の進捗状況を可視化したり、1on1ミーティングの面談ログを一元管理したりできるタレントマネジメントシステムです。
特に人事評価の運用効率化と適正化に適しており、評価の偏りに対しても甘辛調整などが直感的に操作できるため、従業員の納得が得られやすくなるでしょう。人事評価の公平性と客観性を担保するためにお役立ていただけます。
システムを活用しながら、ハイブリッドワークを効果的に進めてみてはいかがでしょうか。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!