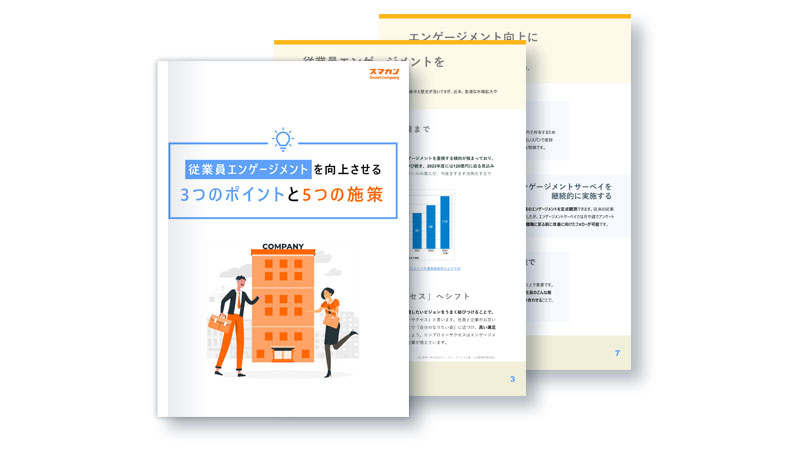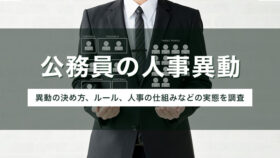- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事戦略
エンゲージメントサーベイとは? 質問項目や目的、満足度調査との違いも

関連資料を無料でご利用いただけます
エンゲージメントサーベイは、従業員と企業の関係性をスコアリングして把握するために重要な調査です。
企業として従業員のエンゲージメントが高いと、従業員のモチベーションや組織力、離職防止や業績など、さまざまなよい影響が生じるでしょう。
しかし、エンゲージメントサーベイについて詳しく知らない場合や、実施したものの効果が出ていないケースも少なくありません。
そこで当記事では、エンゲージメント対策を検討している企業の経営層やご担当者向けに、エンゲージメントサーベイを総合的に解説しながら、満足度調査との違いや目的、質問項目などもご紹介します。
目次(タップして開閉)
エンゲージメントサーベイとは
エンゲージメントサーベイとは、従業員の愛社精神や帰属意識など、「会社とのつながりの強さ(エンゲージメント)」を定量的に把握するための調査です。
調査方法は、紙のアンケートなどではなく、インターネット上で行われるのが一般的です。
エンゲージメントサーベイを実施することで、従業員の会社や仕事に対する思いを捉えることができます。さらにどのような原因があるのかを調べ、改善策を検討するなど、会社と従業員の関係性を良好にするきっかけにもなるでしょう。
エンゲージメントサーベイと従業員満足度調査の違い
エンゲージメントサーベイは、従業員の愛社精神や信頼感を定量的に測定しするもの、従業員満足度は、単純な満足度を調査するものです。
エンゲージメントサーベイは、働きがいを調査したうえで離職防止や生産性向上、組織力の強化などを目的としています。従業員満足度調査は、働きやすさを調査したうえで、労働環境の改善を目的としていると解釈するとわかりやすいでしょう。
エンゲージメントと従業員満足度の違い
エンゲージメントは「企業と従業員との関係性」など会社への全体的な心情であり、従業員満足度は従業員が会社や仕事に対してどれだけ満足しているかの度合いです。
従業員満足度が高い状態だと、会社や仕事にポジティブな気持ちを抱くことになるため、エンゲージメントも高くなります。このように、従業員満足度はエンゲージメントを構成する要素の一つともいえるでしょう。
エンゲージメントサーベイを実施すべき企業
特にエンゲージメントサーベイを積極的に実施すべき企業には、以下のような特徴や傾向があります。
| ・隠れた組織課題を見つけたい ・人材流出が増加している ・組織力を強化したい |
企業として成長していくためには、人的資源を有効に活用しなければなりません。
しかし、人材と企業の関係性に課題がある場合、組織力が低かったり、離職者が多かったりなど、うまくいかない要因があるはずです。これ以外にも見えにくい組織課題を見つけて解決するために、エンゲージメントサーベイが有効といえます。
エンゲージメントサーベイの目的
エンゲージメントサーベイを実施する目的にはどのようなものがあるのでしょうか。一般的に、何のためにエンゲージメントサーベイが実施されているのかをご紹介します。
企業と従業員の関係性の把握
エンゲージメントサーベイを実施する目的は、企業と従業員の関係性を測定するためという点が挙げられます。関係性が強いと従業員は「会社のために」という気持ちを持って、目標達成に向けて業務に取り組みます。
一方で、関係性や思いが薄い場合は、目標達成の意識が低かったり、仕事へのモチベーションが低下しているかもしれません。
関係性を把握できると、状況に応じて対策を実施できるため、従業員のモチベーション向上や組織力の強化、業績の向上も期待できるでしょう。
組織課題の可視化
エンゲージメントサーベイの結果から、見つけにくい組織課題を可視化することもできます。
エンゲージメントサーベイを定期的に実施するなかで、個人のモチベーションや組織との関係性の変化などを捉えられるでしょう。
変化を俯瞰(ふかん)的に捉えたり傾向を分析したりすることで、問題の兆候も早期に発見できるようになるかもしれません。
組織強化やチームマネジメントへの活用
エンゲージメントサーベイは、組織力の強化やチームマネジメントにも活用できます。
部署やチーム単位の課題を管理職や責任者にフィードバックすることで、改善に取り組めるようになるはずです。さらにメンバーにも共有すると、全員が課題を意識して業務に取り組めるようになるでしょう。
人事課題や人事施策への活用
エンゲージメントサーベイの目的として、人事課題の発見や人事施策の実行も挙げられます。
エンゲージメントサーベイの結果を分析することで、課題の把握や原因の究明、改善策の実施など、人事課題の解決や人事施策の実行に役立つでしょう。
人事課題に対して効果的な人事施策が実行できると、従業員の満足度も向上しやすくなります。
離職防止
エンゲージメントサーベイの実施から効果的な改善策が実施できると、エンゲージメントや会社に対する満足度の向上を促進し、従業員の離職防止につながります。
また、エンゲージメントサーベイの実施によって離職を決めるまでの「心の変化」や「本音」に気づきやすくなるため、離職の原因を早期に突き止められ、さらに離職防止効果が期待できます。
| 無料ダウンロード資料 離職率を改善するには? |
エンゲージメントサーベイの質問項目例
エンゲージメントサーベイで、よくある質問項目例をご紹介します。
総合的な評価を測定する質問項目
満足度や幸福度など「企業に対して総合的にどのような評価をしているのか」を測るための質問項目で「エンゲージメント総合指標」といいます。
具体的な質問例は
| ・知人や友人に自社を進めたいか ・成長できる機会はあったか ・今後もこの会社で働きたいか |
などが挙げられます。
仕事のモチベーションを測定する質問
仕事への熱意や意欲、活力など、仕事そのものに対するモチベーションを測るための質問で「ワークエンゲージメント指標」といいます。
具体的な質問例は
| ・自分の能力やスキルを活かせていると感じるか ・仕事が楽しいと感じているか ・仕事をしていると時間が経つのを早いと感じるか |
などが挙げられます。
「エンゲージメントを向上させる要因」を知るための質問
従業員が企業に貢献できていると感じているかを測るための質問項目で「エンゲージメントドライバー指標」といいます。
エンゲージメントを向上させる要因は、組織とのかかわり方、職務の難易度、業務上必要な資質などを指し、貢献できているという認識があるかどうかを把握するための指標です。当事者意識や自己肯定感についての質問を含めるとよいでしょう。
具体的な質問例は
| ・仕事で自分の意見を反映されているように感じるか ・組織の目標を理解しているか ・最近1週間で、褒められたり肯定的な言葉や反応を受けたか |
などが挙げられます。
エンゲージメントサーベイの代表例
エンゲージメントサーベイの代表例として、「eNPS」「Q12(キュートゥエルブ)」「一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)」をご紹介します。
eNPS
eNPSは「Employee Net Promoter Score(エンプロイー・ネット・プロモーター・スコア)」の略です。
日本語で
| ・従業員(employee) ・本当の(Net) ・推奨者(Promoter) ・点数(Score) |
と訳され、それぞれを合わせると「従業員が自分の職場を親しい知人や友人にどれくらい勧めたいかを点数化したもの」です。
他人への推奨度から、会社への評価やエンゲージメント、職場に対する満足度を測るシンプルな指標として使われています。
eNPSを測る方法は、従業員に対して「あなたの知人や友人に推奨できる度合いはどれくらいか」という質問で測定できます。
この質問に対する回答を10点満点とし、0~6点を批判者、7~8点を中立者、9~10点を推奨者といいます。
| 関連記事 eNPSを徹底解説 |
Q12(キュートゥエルブ)
Q12はアメリカの調査会社であるギャラップ社と、アメリカ心理学者フランク・L・シュミット博士によって開発されたエンゲージメントサーベイです。12個の質問項目で構成されています。
| 【代表的な12の質問】 |
|---|
| 1.仕事で何を期待されているか 2.仕事を適切に行なえる設備やツールを持っているか 3.日々において、自分が得意な作業をする機会があるか 4.過去1週間において、自分の仕事で褒められたか 5.上司や同僚などから、1人の人間として気にかけてもらっているか 6.職場内に、自分の成長を助けてくれる人はいるか 7.自分の意見は、職場内で尊重されているか 8.会社の目的やミッションを通じて、自分の仕事に意味があると思うか 9.周囲の従業員が、質の高い仕事をしているか 10.職場内に親友はいるか 11.直近の半年間において、職場の人間から自分の進歩を評価してもらえたか 12.直近の1年間において、成長や学びの機会があったか |
質問に対する回答は
| ・完全にあてはまる(5点) ・ややあてはまる(4点) ・どちらともいえない(3点) ・やや当てはまらない(2点) ・完全に当てはまらない(1点) |
の5つが選択肢として用意されており、合計点数を出して平均スコアを算出します。
全体的なエンゲージメントを測定し、平均点である3.6点を基準に、点数の低い質問項目を課題として施策を検討するとよいでしょう。
参考:『Who's Responsible for Employee Engagement』GALLUP
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)
一般性セルフ・エフィカシー(GSES)は、自己効力感の測定方法で、坂野雄二氏と東條光彦氏が開発した尺度です。
もともと「セルフ・エフィカシー」という言葉自体は、カナダの心理学者アルバート・バンデューラ氏が提唱した概念です。特定の成果や行動などが求められる際に「自分はできると信じることのできる力」があるかどうかを指しています。
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)では
| ・行動の積極性 ・失敗に対する不安 ・能力の社会的位置づけ |
という3つのカテゴリーで16の質問を行い「はい」か「いいえ」の2択で回答を用意して、高得点ほど自己効力感が高いといえます。得点が高ければ自己効力感が高い傾向にあり、低い場合(10 点以下)は抑うつ傾向が見られる可能性もあります。
メンタル不調を抱える従業員を見つけるきっかけになる方法として活用してみるのもよいでしょう。
参考:『一般性セルフ・エフィカシー尺度作成の試み』坂野雄二・東條光彦著|J_STAGE
エンゲージメントサーベイのメリットや効果
エンゲージメントサーベイの実施によって得られるメリットや効果にはどのようなものがあるのでしょうか。一般的に得られる主要なメリットや効果をご紹介します。
生産性向上
エンゲージメントサーベイにおけるメリットの1つめは、組織として生産性を向上できることです。
たとえばエンゲージメントサーベイで得たデータを活用すれば、社員の特性や傾向が把握でき、適材適所への人材配置が期待できるでしょう。
適切な人材配置は、従業員の意欲や主体性アップにつながり、結果として個人の生産性向上に直結します。生産性が高まることで従業員に余裕ができ、社内コミュニケーションの活性化にもつながるでしょう。
社内コミュニケーションの活性化によって会社の雰囲気がよくなると、エンゲージメント向上も期待でき、より企業全体の生産性が高まるという好循環が生まれやすくなります。
モチベーション向上
エンゲージメントサーベイにおけるメリットの2つめは、従業員のエンゲージメントやモチベーションの向上です。
エンゲージメントサーベイをきっかけに、会社と従業員の関係性を向上させられると、従業員の満足度も向上し、意欲も上がりやすくなるでしょう。
離職防止
エンゲージメントサーベイにおけるメリットの3つめは、離職防止や予防です。
エンゲージメントサーベイで「従業員のエンゲージメントが低い」とわかったら、エンゲージメントを上げる努力が必要です。エンゲージメントが低い原因の把握から始め、改善策の検討と実行に移りましょう。
改善策の実施によって課題が解決すれば、離職防止や予防に効果が見込めるはずです。また、従業員を大切にする姿勢や対応そのもの自体が、企業への信頼感にもつながるでしょう。
採用活動への効果
エンゲージメントサーベイにおけるメリットの4つめは、採用活動にも効果が期待できることです。
エンゲージメントサーベイで得たデータをもとに、採用すべき人材がわかるのはもちろん、従業員の知人や友人などを紹介してもらうリファラル採用など信頼性の高い採用を進められます。
従業員のエンゲージメントが高い状態なら、積極的に自分の会社を周囲に紹介することもあるでしょう。さらにリファラル採用は、マッチング率も高く、効率的に採用活動を進められます。
エンゲージメントサーベイのデメリットや注意点
エンゲージメントサーベイのデメリットや注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的なデメリットを把握して、トラブルの発生や失敗を避けられるように注意しましょう。
コストがかかる
エンゲージメントサーベイのデメリットには、コストがかかるという点があります。
エンゲージメントサーベイを実施するためには、調査ツールの導入や外部委託を行う必要があり、金銭的コストがかかります。また選んだ方法によっては、回答の分析に時間がかかる場合も少なくありません。
そのため、できるだけコストを抑えつつ、迅速に調査結果から改善施策までを行えるような方法を選ぶようにしましょう。
従業員の協力が得にくい
エンゲージメントサーベイは、少なからず回答する側の従業員に負担がかかります。回答する時間の確保が難しかったり、質問に答えること自体が面倒なことと捉える従業員もいたりするかもしれません。
しかし、調査ではできる限り多くの回答を収集することで、より信頼性の高い調査結果になり、有効な改善策の実施につながります。そのため、エンゲージメントサーベイの理解を得られるよう、事前に周知するなどして協力を得られるようにしましょう。
改善されないことへの不満が募る
エンゲージメントサーベイの難しい点の一つとして、結果的に状況が改善されない場合があります。時間を割いて調査に協力したものの、会社の状況にまったく変化がなく、課題が解決できないと、ネガティブな感情となり、その後は協力されにくくなってしまうかもしれません。
そのため、改善に努めるのはもちろんですが、改善が難しい場合は、状況の共有や方向性を示し、会社の姿勢を従業員に伝えましょう。
| 関連記事 エンゲージメントサーベイは無駄? |
エンゲージメントサーベイのポイント
エンゲージメントサーベイを実施する際に意識したいポイントについてご紹介します。
従業員の理解と協力
エンゲージメントが低い企業では、企業に対して否定的な見方をする従業員も多く見受けられます。
否定的な見方をする従業員が多いと、調査を行っても「適当に回答をする人」や「回答自体をしない人」も出てくるでしょう。正確な回答がそろわないと、正確な調査はできません。
そのため、エンゲージメントサーベイを実施するには、従業員の理解を得る必要があります。また理解を得るには、以下を伝えることが大切です。
| ・エンゲージメントサーベイを実施する目的 ・フィードバック方法 ・回答に必要な手順 ・サーベイの実施で従業員が得られるメリット |
伝える際にもメールだけで済ませるのではなく、事前説明のためのMTGなどを実施するとていねいに感じられます。
惰性に注意
エンゲージメントサーベイを実施する際は、惰性で実施することのないよう注意しましょう。
継続するために定期的に実施する場合、従業員の回答も惰性になってしまう危険性もあります。その結果、1回1回の調査の重要性を従業員にも理解してもらえるよう、伝えることが大切です。
そのためにも、調査結果の報告や改善策の共有などもていねいに行うようにしましょう。
継続して実施
エンゲージメントサーベイは、効果を確認する意味でも、定期的に実施しましょう。
また現段階での課題が改善されても、取り巻く環境は常に変わります。環境の変化による「従業員の心境」を見逃さないためにも、定期的に実施するのがおすすめです。定期的な実施によって、変化の指標を「可視化」できるでしょう。
運用方法の効率化
エンゲージメントサーベイでは、以下のような工程で実施されます。
| ・質問の設計 ・調査データの集計・分析 ・個人や組織へのフィードバック ・調査結果に基づいた改善 |
しかし、実施そのものに時間がかかるうえに、管理も煩雑です。多くの工数を割かなければならないため、できるだけ効率化できる方法や自社に合った運用方法を見つけましょう。
効率化するためには、エンゲージメントサーベイのシステムを利用すると、工程の負担を削減できます。
エンゲージメントサーベイの選び方
エンゲージメントサーベイの選び方について、特に押さえておきたいポイントをご紹介します。
比較する
エンゲージメントサーベイにはさまざまな種類があるため、複数比較して理想的なものを選ぶようにしましょう。
まずはシステムやツールを活用するのか、外部委託するのかなどの実施方法を決めたうえで、さらにサービスを比較してみましょう。
コスト
エンゲージメントサーベイの予算を踏まえ、どれくらいのコストがかかるのかを確認しましょう。機能やサービスが多い場合、コストも高くなりがちです。エンゲージメントサーベイは定期的に実施するものでもあるため、かかる費用を確認し、無理のない範囲で実施するようにしましょう。
使い勝手
エンゲージメントサーベイは、従業員を対象にした調査であるため、さまざまな人が回答します。そのため、誰でも回答しやすいような設計か、シンプルで簡単なつくりになっているかなどもチェックしておきましょう。
使い勝手が悪かったり、操作の説明などを行わなければならないと、さらに時間がかかってしまうため、できるだけ使いやすいものにしましょう。
サービス内容
エンゲージメントサーベイのサービスに含まれる内容が十分かどうかも確認しておきたいところです。特に調査実施後の回答分析やサポート対応がどれくらいの内容で用意されているのかは大切です。
また、プロの客観的な目線によるアドバイスなど、コンサルティングが必要な場合、その分費用が高くなるという点には注意しましょう。
エンゲージメントサーベイ実施の流れ
エンゲージメントサーベイは、以下のような手順で実施します。具体的な流れをイメージして、スムーズに行えるよう意識しましょう。
調査対象を決める
調査の目的や調査内容によって対象者を決めます。目的や内容によっては、女性を対象にしたり、管理職を対象にしたりすることもあります。特定の層に限定しない内容であれば、全従業員を対象にしましょう。
調査項目を決める
調査対象を定めたら、調査内容(項目)を決めましょう。
「調査対象を決める」ときと同様に、調査内容も目的を踏まえて決めます。調査内容を決める際の注意点は、以下の通りです。
| 質問数を適量にする |
|---|
| 問数が多いと従業員の負担になるとともに、分析に時間がかかります。また質問数が少なすぎても、正確な調査ができません。 |
| 質問内容を定期的に見なおす |
|---|
| 状況は常に変化するため、度重なる調査で「同じ質問」をしても、意味をなさない可能性があります。 |
| 不必要な質問をしない |
|---|
| 不必要な質問は、従業員の回答への負担につながります。 |
| 【不必要な質問の例】趣味、志望動機、特技など |
アンケート設計
調査内容について調査票に落とし込み、アンケート項目を作成します。
また昨今のアンケートは、インターネットやクラウドサービスで実施するのが一般的です。特にクラウドサービスを活用すると、以下のようなメリットがあります。
| 利便性が高い | ・パソコンをはじめ、タブレットやスマートフォンでも回答できる ・インターネット環境があれば場所を選ばず実施できる |
|---|---|
| 集計が簡単 | ・データをクラウド上で一括管理できる |
クラウドサービスは、アンケート結果の可視化もスムーズにできるため、メリットが多いでしょう。
エンゲージメントサーベイの周知
次に、アンケート対象者に対して周知を行います。周知すべき内容は、目的とサーベイの実施方法についてです。
| 目的と方法の例 | |
|---|---|
| 目的 | 新卒社員の定着率を高めたい |
| 方法 | 専用のクラウドサービスを使い、アンケートを実施する |
また、周知する方法にはメールやサイト掲示、説明会などがあります。質問などにすぐに対応できるため、説明会を実施できるとよいかもしれません。
| 周知の方法 |
|---|
| ・メールで報告する ・ポータルサイトに掲示する ・説明会を開催する |
アンケート実施
アンケートを実施します。専用のサービスを活用する場合は、回答用URLを対象者に共有します。自社が用意した調査の場合は、データ等を対象者にメールで共有するなどの方法があります。
アンケートの回収と結果共有
アンケートが終了したら、回答の回収と結果の報告を行います。
さらに分析などを行い、内容を適切にフィードバックできると、従業員のエンゲージメントサーベイに対する信頼感が増し、理解を深められるでしょう。
| スコアの高低をチェックする |
|---|
| スコアの高低をチェックすることで、従業員のエンゲージメントがわかります。 スコアが高いほど、エンゲージメントも高いといえます。 |
| スコアの軸をさまざまな角度から見る |
|---|
| スコアの軸を「部署ごと」や「年度ごと」などのさまざまな角度から見ると、数値の悪い項目がわかるため、対応すべき課題も見えやすくなります。 |
| クロス集計を実施する |
|---|
| エンゲージメントサーベイの結果とは異なるデータ(人事評価の結果など)とクロス集計をすることで、詳細な分析が可能です。 |
回答の結果を分析する場合も、専用のサービスを活用すると効率化でき、担当者の負担を減らせるでしょう。
改善策の検討と実施
エンゲージメントサーベイの結果から、課題に応じた施策を実行します。エンゲージメントサーベイを実施して終わりにならないように、調査と分析、改善策をセットとして捉えましょう。
『スマカン』でエンゲージメントサーベイの実施をサポート
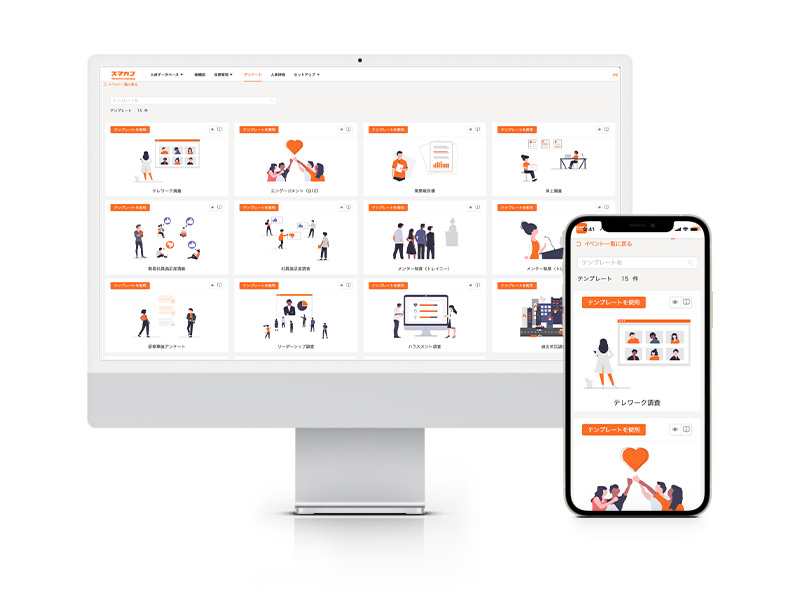
エンゲージメントサーベイを効率的に実施するには、クラウドシステムがおすすめです。
タレントマネジメントシステムの『スマカン』は、人材データをクラウドで一元管理するタレントマネジメントシステムとしてさまざまな人事施策に役立つ機能が搭載されていますが、アンケート機能も魅力の一つです。
『スマカン』のアンケート機能を活用すれば、従業員エンゲージメントやワークエンゲージメントの状況を調査できます。これらのデータを分析し適切な対応をすることで、個人のパフォーマンス向上や離職率低下につながるなど組織体制を強化できるでしょう。
『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!