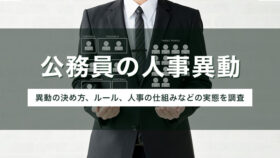- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事評価
評価制度とは|目的や作り方、求められるポイントも徹底解説!

関連資料を無料でご利用いただけます
評価制度は、従業員の処遇や配置、人材育成のため、多くの企業が導入している人事制度の一つです。
評価制度は、適切な運用を行うことで企業の生産性や業績の向上にもつながります。
しかし一方で「どのような評価手法を取り入れたらいいのかわからない」「どのように評価制度を構築すればいいのだろう」と悩んでいる人事担当者も少なくありません。
そこで本記事では、評価制度について総合的に解説しながら、目的や種類、事例なども含めてご紹介します。評価制度の運用を成功させたいと感じている人事担当者は、ぜひ参考にしてみてください。
目次(タップして開閉)
評価制度とは?
評価制度とは、従業員の業務遂行能力や成果などを評価・査定する制度です。半年に1回、1年に1回など定期的に行い、評価基準は各企業によって異なります。
評価制度は人事制度の一環として「等級制度」や「報酬制度」と連携しており、よい評価を得られると役職が上がったり給料が増えたりするのが一般的です。従業員のモチベーションが高まって目標達成や生産性の向上につながるため、評価制度は適切に実施する必要があるでしょう。
評価制度の目的
評価制度を導入する目的には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。一般的に企業で評価制度を導入する目的を3つご紹介します。
処遇の決定
評価制度を導入する目的の一つは、処遇への反映です。給与や賞与、昇進・昇格という処遇は、一人ひとりの能力や業績への貢献に見合ったものでなければなりません。
客観的な指標でさまざまな基準を用いながら評価制度を運用し、処遇に反映することで、納得感を得やすい評価につながります。評価制度は、処遇に納得してもらうために有効だといえるでしょう。
育成への活用
評価制度では、従業員の育成を目的とする場合もあります。評価結果によって従業員ごとの強みや弱みが把握できるため、それぞれに適した育成プログラムが提供しやすくなるためです。
若手社員であれば将来のキャリアや業務に関する悩みを相談できるメンターをつけること、中堅社員であればマネジメント研修への参加などが検討にあがるでしょう。
また、的確な評価を受けた従業員は承認欲求が満たされ、主体的な成長のきっかけになるかもしれません。本人の次の目標が明確になり、求められている行動や課題がフィードバックされる点もポイントでしょう。
配置への活用
適切な人材を適切な部署に配置することで全体の生産性が上がり、成果の最大化を目指せます。従業員の能力や適性を見極めるには、評価制度の活用が効果的といえるでしょう。
客観的な評価基準によって、把握できた従業員の適性に基づいて配置を最適化すると、よりパフォーマンスを発揮してもらえる可能性があります。
最適な人材配置ができると、生産性向上による業績アップだけでなく、従業員エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
評価制度における3つの基準や種類
評価制度では、以下の3つの基準を設け、それを基準として制度が運用されることが一般的です。3つの基準について確認してみましょう。
業績評価
成果評価は、日頃の業務への取り組みによって得られた成果や結果で評価を行うものです。従業員がみずから設定した、あるいは会社に設定された目標の達成度に応じて判断されることが一般的でしょう。
業績評価では、数値などを用いた定量的な成果を評価するので、客観的かつ公平性を保つ評価として納得感も得られやすいのが特徴です。
また、従業員みずから成長に向けて主体的に行動するきっかけとなり、モチベーションが高まりやすくなるでしょう。個人のパフォーマンスが向上すると、会社やチームとしての生産性も上がり、組織全体の成長につながる可能性があります。
能力評価
能力評価とは、スキルや経験に対して評価を行うものです。日頃の業務を通じて習得した能力や、能力を活かしてどれだけ企業やチームに貢献できたかを判断します。
能力評価は、本人の適性を見極める際にも役立ちます。従業員の能力やスキルに応じて、適材適所の人材配置が実現できれば、組織の生産性向上にも寄与するでしょう。
また、能力評価によって適切な配置ができれば、本人の適性と担当業務との乖離(かいり)が軽減し、最終的に離職の防止にも役立つでしょう。
情意評価
情意評価は、仕事に対する意欲や態度、姿勢を総合的に評価します。具体的には、勤務態度やルールの順守、協調性や積極性などが該当します。
情意評価では、数字にはあらわせない部分を評価できるため、数値による成果をあげられなかった従業員でも、高い評価が得ることができる場合もあるでしょう。
評価制度の運用で用いられる評価手法
評価制度を適切に運用するために用いられる評価手法にはどのようなものがあるのでしょうか。主要な評価手法だけでなく近年注目を集める評価手法なども含めてご紹介します。
目標管理(MBO)
目標管理(Management By Objectives)とは、設定した目標の達成度に応じて評価や、日々の業務管理に活用できる評価管理制度です。
MBOは、従業員みずからが目標設定を行い、自己管理を行います。個人目標を企業目標とリンクさせながら、目標達成に向けて上司が部下をサポートします。
MBOは、目標に対する達成度でスムーズな評価ができ、人事評価にも活用できるほか、従業員の成長やモチベーション向上にも効果がある点が魅力といえるでしょう。
| 関連記事 目標管理(MBO)とは? |
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、企業で成果を出している従業員や理想のモデル像を明確にして、人事評価に反映する仕組みです。
コンピテンシーモデルを確立することで、具体的な評価基準が明確になります。評価基準が明確になると、評価者による主観的な評価を防ぐことができ、公平で客観的な評価の実現につながるでしょう。その結果、従業員の満足度やモチベーションアップが期待できます。
また、成果を出すためには必要な要素や会社が求める人材像が明確にできることで、従業員の成長も促進できるでしょう。
| 関連記事 コンピテンシー評価とは? |
360度評価(多面評価)
360度評価とは、一人の従業員に対して、上司や部下、同僚や他職種のプロジェクトメンバーが、多角的に評価する手法です。
360度評価が適切に運用されると、より客観的かつ納得感のある評価につながりやすくなるでしょう。多角的に評価されることで、人材育成や従業員のモチベーション向上にも期待できます。
また、上司だけでなく周囲とコミュニケーションをとる機会が増えることで、チームや組織力の強化にもつながるでしょう。
| 関連記事 360度評価とは? |
OKR
OKRとは、1つの目標(Objectives)とともに複数の結果(KeyResults)が付随するような目標管理方法です。組織目標としてのOを達成するために必要な結果をKRとして設定し、その内容に従って、各部署や個人レベルに必要な業務や役割を割り振っていきます。
Oは定性的な目標を、KRはOを導くための具体的数値目標を設定するのが特徴です。
目標に対する進捗確認も随時行っていくため、最終的な評価自体も公平で納得感のあるものになりやすいといえるでしょう。
| 関連記事 OKRとは? |
リアルタイムフィードバック
1~2週間に1回、あるいは1か月に1回などの短期間でフィードバックを行う評価制度が「リアルタイムフィードバック」です。
1年や半期ごとに行う評価制度よりも、現状に合わせたタイムリーな目標設定がしやすく、次の課題も見つけやすいというメリットがあります。ただし、業務外の工数が増えて従業員に負担がかからないよう、実施前に頻度や内容をしっかり検討しておくことが重要です。
ノーレイティング
ノーレイティングとは、ABC評価や5段階評価のように、従業員にランクづけをしない新しい手法です。海外の先進的な企業で導入が進んでおり、日本でも注目され始めました。
ノーレイティングとは評価制度そのものを廃止するのではなく、従来の年次評価制度を廃止するという意味です。
代わりにリアルタイムで従業員の行動や成果にフィードバックすることになるため、より納得度の高い評価をするための仕組みといえるかもしれません。
ノーレイティングを導入する際は、年1回の査定面談の代わりに、1on1ミーティングを頻繁に実施します。頻繁に面談を重ねることにより、状況に応じて課題や目標を設定し直すことができます。
ノーレイティングによる評価を行うことで、従業員の納得度やモチベーションを高めやすくなるでしょう。
| 関連記事 ノーレイティングとは? |
バリュー評価
バリュー評価とは、企業の価値観や行動基準を「バリュー」として設定し、バリューを実践できているかを評価します。絶対的な基準を設けることが難しいため、ほかの従業員と比較する「相対評価」で行われることが多いのも特徴です。
バリュー評価では、従業員が会社のバリューを理解して業務に取り組めるため、企業の価値観が浸透しやすくなったり、会社と従業員の目線が一致しやすくなったりすることがメリットといえます。
働き方が多様化し、企業の社風に基づくバリューが重視されるようになったことで、評価制度として取り入れる企業も増えてきました。
| 関連記事 バリュー評価とは? |
パフォーマンス・デベロップメント(PD)
部下の成長に焦点を当てた評価制度のことを「パフォーマンス・デベロップメント(PD)」といいます。個人の業績よりも、キャリアの方向性を加味した成長度を評価の基準とするのが特徴です。
パフォーマンス・デベロップメントでは、評価者である上司が部下と頻繁に面談し、リアルタイムにフィードバックすることから、お互いのコミュニケーションが活発化します。
ただし、評価にバラつきが出やすくなる懸念があるため、具体的で測定しやすい目標を部下に設定してもらう必要があります。
関連記事:『【人事評価制度とは】種類・作り方・評価項目を詳しく解説します。』digireka!HR
評価制度の作り方・設計方法
評価制度の設定について、どのような流れで行うのがよいのでしょうか。評価制度の作り方についてその流れや手順をご紹介します。
現状を分析する
評価制度を策定するために、自社が求める人材像を踏まえたうえで、解決すべき課題を明確にします。たとえば、どの属性の従業員がどのような傾向にあり、どうしたら理想に近づけるのかを分析します。
評価目的を設定する
評価制度における目的を設定します。一般的には、人事評価の目的は「処遇」「配置」「育成」が中心となりやすいですが、企業の評価制度としてどこにどの程度の比重をかけるのかなども決めておきましょう。
評価制度の目的やルールは経営状況や業績などによっても変化します。そのため、状況に応じて定期的に目的を見直すようにすることも大切です。
評価基準を策定する
次に評価制度における評価基準を設定します。評価基準は、職種によっても異なるため、現場の声もヒアリングし、一緒に調整しながら設定するのがよいでしょう。
評価基準を設定する際は、会社が求める役割や行動などがわかりやすくなるよう意識することが大切です。
評価項目を作成する
評価項目の作成では「業績評価」「能力評価」「情意評価」の3要素を踏まえ、自社に合った項目を設置します。
業績評価では成果を評価するために、達成度や品質、効率性などの項目を設定します。能力評価では、仕事を行う能力について評価するために、企画力や実行力、理解度や提案力、リーダーシップなどの項目を設定します。情意評価では、仕事への姿勢や態度を評価するために、責任感や協調性、積極性などの項目を設定します。
さらに、評価項目のウエイトも定めておきましょう。一般的には、役職が高くなるにつれて「業績評価」へのウェイトが重くなるように設定されやすく、新人や若手社員などは情意評価のウェイトが重くなりやすいという点を理解しておきましょう。
評価方法を構築する
評価をどのように行うのかというルールを決めます。5段階評価だけでなく、あいまいな評価を避けるために3段階評価を導入する方法もあるでしょう。
さらに、評価方法によって点数化されたものを等級制度や報酬制度へどのようにリンクさせるかなども決めておきましょう。
評価制度に関する周知を行う
評価制度の具体的な運用方法や流れが決定したら、会社全体へ周知を行いましょう。
評価者だけでなく、被評価者である従業員にも評価制度について理解してもらうことで、従業員のモチベーションや評価制度のスムーズな運用につながります。
フィードバックを行う
評価を行ったら、本人だけでなく人事担当者にもフィードバックしましょう。
よい評価になった際は、評価理由とともに今後の課題も合わせて伝えることで、さらなる成長が見込めます。従業員のモチベーション向上にもつながるでしょう。
悪い評価になった際は、評価理由を説明したうえで、よかった点や今後の改善点を伝えるなどフォローすることが大切です。悪い結果となった場合、従業員のモチベーションが下がりやすくなるため、意欲が低下しないよう、励ましたり鼓舞したりすることが重要です。
評価制度における等級制度

評価制度における等級制度の代表例をご紹介します。等級を決めるにあたり、企業として重視するものが何かによって選ぶべき制度は異なるため、確認してみましょう。
職能等級制度(メンバーシップ型)
職能資格制度とは、従業員個人の職務遂行能力を評価し、給与などの待遇面に反映させる等級制度の一つです。
職能資格制度で個人の能力を待遇面に評価させると、モチベーション向上など人材育成にも効果があり、日本では多くの企業で取り入れられてきました。
また、職能資格制度をうまく運用できると、従業員は広い範囲の業務をこなせるようになるため、組織改編や人材不足への課題にも対応できるようになるでしょう。
職務等級制度(ジョブ型)
職務等級制度は、職務内容とその達成度合いによって評価が決まる等級制度です。年齢や勤続年数は評価の対象外であり、成果主義ともいえる点が特徴です。
職務内容の価値や業績によって評価されますが、職務記述書の内容によって等級づけが行われます。
また、専門的なスペシャリストを育成する側面があり、組織として分業を徹底し、生産性を向上したい場合にも有効です。
役割等級制度(ミッショングレード制)
役割等級制度とは、従業員が担っている役割によって等級を決める仕組みです。仕事に焦点を当てて評価する職務等級制度と、人に焦点を当てて評価する職能資格制度の間を取ったような仕組みともいえるでしょう。
役割等級制度では、職務記述書(ジョブディスクリプション)に基づく評価ほど厳格ではなく、ほどよい柔軟性のある評価を目指しています。そのため、各社によって考え方が異なったり、職務等級制度と職能資格制度のどちらかに近い運用がされていたりします。
評価制度のメリット
評価制度を運用するうえでのメリットを具体的にご紹介します。
モチベーションの向上
評価制度を運用することで、従業員のモチベーションが向上しやすくなります。評価とともにフィードバックを受けることで、従業員がみずからの強みや課題を改めて認識するためです。改善に取り組む中で成長や達成感を得られるでしょう。さらに、評価の結果として報酬アップや昇格の機会が得られるとさらなるモチベーションアップにつながるでしょう。
処遇決定がスムーズ
評価制度がうまく機能することで、処遇の決定もスムーズになります。あらかじめ明確にした評価基準と報酬制度などが上手に連携できれば、公平な評価に基づいた処遇となり、従業員の納得感も得られやすくなるでしょう。
効果的な人材育成
評価制度によって評価基準が明確になると、従業員の人材育成にも効果があるでしょう。従業員は、何をどうすれば成果を出せるのか、評価してもらえるのかという点を理解しやすくなります。また、明確な基準があると、さらなるスキルアップやキャリアアップをイメージして挑戦するきっかけにもなるため、人材の成長につながるでしょう。
適切な人材配置
評価制度によって、従業員の能力や取り組む姿勢などを正しく評価することによって、適材適所の人材配置にも効果があるでしょう。
適材適所の配置によって従業員がより活躍できるようになると、さらなる成長やモチベーションアップ、離職防止も期待できるかもしれません。
会社の方向性やビジョンの浸透
評価制度を運用する中で、会社のビジョンや方向性が浸透しやすくなります。自社が求める人材像を明確にし、評価項目に企業理念や経営方針に関する内容を盛り込むことで、企業への理解が深まりやすくなるでしょう。
ビジョンが浸透するほど、企業と従業員が同じ方向を向いて目標達成に向けて取り組めるようになり、成果や業績アップにもつながるはずです。
評価制度のデメリット
評価制度のデメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。具体的なデメリットにも注目してみましょう。
評価に影響しない業務がおろそかになる場合がある
評価制度によって、評価に影響しない業務への優先度が下がりやすくなるでしょう。評価基準や項目が明確になることで、何をすれば評価につながるのかを理解しやすくなるぶん、評価につながらないような業務を後回しにしたり、取り組まなくなったりする可能性があります。
評価に不満が発生する場合がある
評価制度を運用する中で、必ずしも全員が納得する評価にはならない場合があります。
特に主観的な評価が行われたり、評価プロセスが不透明だったりした場合、不満を抱く原因になってしまうでしょう。評価制度は、処遇とも連動するため、最悪の場合は離職やモチベーション低下の原因にもなりかねません。
設計に時間と労力がかかる
評価制度を運用する際は、設計の段階で時間と労力がかかります。設計に関するノウハウも必要になるでしょう。
また、適切な評価制度を運用するために評価者の教育を行う必要もあるなど、運用準備だけでもさまざまな点を調整しなければなりません。
| 関連記事 人事評価制度への不満要因と対処法 |
評価制度の企業事例
評価制度を導入して、効果をあげている企業の事例を2つご紹介します。
ソフトバンク株式会社
ソフトバンクで株式会社は「評価と報酬は頑張った人が次の挑戦へ向えるように。」をコンセプトとした評価制度を実施しています。担当するミッションや働き方に応じた「ミッショングレード制」を基本とし「貢献度評価」と「コア能力・バリュー評価」の2つの評価指標を取り入れているのが特徴です。
また、これらを連動させた報酬制度も整えています。特に賞与に関しては、従業員それぞれの貢献度評価に変動幅を持たせ、貢献度に応じて金額を決定しています。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは、さまざまなバックグラウンドを持った従業員が集まる多様な組織に対応するため、2021年1月から評価制度を刷新しています。新評価制度では、評価軸を「成果評価」と「行動評価」に分け、それぞれ5段階で評価しています。
昇給・昇級は「成果評価」と「行動評価」の両方を考慮し、賞与は「成果評価」と連動して決定する仕組みです。
メルカリは「ミッション(経営理念)に基づいたバリューの発揮」をもっとも重要視しています。数値化された成果だけでなく、中長期的なチャレンジや「行動評価」を通じて、いかにバリュー(経営方針)を体現できたかを評価しているのが特徴です。
参照:『メンバーの活躍を“大胆に”報いる──大幅アップデートされたメルカリ人事評価制度の内容と意図』mercan
評価制度に求められるポイント
評価制度の運用ではどのような点に注意しておく必要があるのでしょうか。成功に導くためのポイントをご紹介します。
評価基準が明確で公平性がある
評価制度を運用する際は、評価基準や項目、運用方法などが明確で公平性があることが大切です。
評価されるためにはどうしたらよいのかが明確になることで、意欲が向上したり、パフォーマンスが向上して会社としての業績にもよい影響がもたらされることが期待できます。
また、評価に対する情報を全社的に公開することで、会社への信頼感も増すでしょう。
評価と報酬の関係を明確にする
評価制度で重要なのは、評価と報酬の関係性を明確にすることです。
人事評価は給与などの処遇に影響するため、従業員も意識して見るポイントでもあります。同じ等級でも給与額に幅を持たせて設定するなど、評価によって給与の変動がどのように起こるかの仕組みをわかりやすくしたうえで全体に公開しておくとよいでしょう。
評価者の教育を行う
評価制度を効果的なものにするためには、評価者の教育も欠かせません。評価基準や項目を決めても、実際に評価を行う者が、主観的な評価をして適切な評価ができていないと意味がありません。
設定した基準に沿って適切な評価が実施できるよう、評価者への研修などを開催し、評価者の教育も行いましょう。
絶対評価である
評価制度を運用するうえで、基本的には絶対評価を採用するのがよいでしょう。ほかの従業員と比較して評価すると、自信をなくしてしまい、不満や不信感を抱く原因にもなりかねません。
評価に対する説得力や納得感という点においても、従業員一人ひとりと向き合うことを重視しましょう。
適切なフィードバックを行う
評価制度を成功させるためには、評価のあとのフィードバックも重要です。
評価そのものに対するフィードバックはもちろんですが、従業員のよかった点や今後の課題を伝えることで、自信やモチベーションにも影響するはずです。評価をして終わりにするのではなく、評価からさらなる成長につなげましょう。
トレンドにも注目する
評価制度は、時代によって求められる役割が異なります。
年功序列型から成果主義型へと変化したように、今後も重視される評価制度が状況や時代とともに変化するでしょう。
特に近年は、働き方改革によって多様な働き方や雇用形態が認められつつあり、働き方による格差を是正し、評価制度が公平公正であることが求められています。
このように、時代とともに求められている評価制度の内容も変わるということを意識して、必要であれば状況に合わせた運用やルール変更を柔軟に行っていくことが大切です。
クラウドシステムで管理する
評価制度をより効率的に管理するために、クラウドシステムによる管理を行うこともポイントです。
クラウドシステムを活用すれば、評価シートの作成、従業員への配布・回収・集計、さらにフィードバックなど、評価に関する一連の流れを効率化できます。
さらに管理を効率化することで、人的負担を軽減させ、適材適所の人材配置や従業員へのフィードバックなどに時間を割けるようになり、より効果的な運用にもつなげられるでしょう。
評価制度のサポートなら『スマカン』
『スマカン』は、人材データをクラウドで一元管理するタレントマネジメントシステムです。
「MBO」「コンピテンシー評価」「360度評価」など、さまざまな評価制度に沿った評価シートのテンプレートがあり、始めやすいのがポイントです。
評価シートは、自社の運用に合わせて自由にカスタマイズもできます。アンケート機能を活用して、評価制度への納得度やモチベーションも測定できるため、評価制度の見直しにもおすすめです。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
評価制度は、定期的に従業員の能力や成果などを評価し、その結果から従業員の処遇の決定や育成、配置に役立てることができます。
評価制度を適切に運用することで従業員の納得感を得られると、企業への信頼度やモチベーションがアップし、組織全体の業績向上にもつながるでしょう。
そのためにも、まずは評価制度の仕組みを理解したうえで、正しい手順で制度運用を行うことが大切です。
本記事でご紹介した評価制度を参考に、最適な評価制度の運用を目指してみてはいかがでしょうか。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!