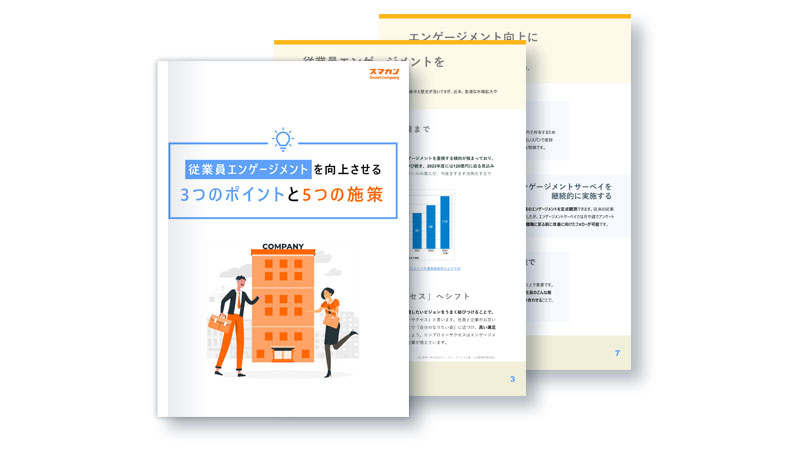- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材管理
モチベーションマネジメントとは|必要? メリットや生産性向上に欠かせない企業事例も解説

関連資料を無料でご利用いただけます
近年、企業における従業員の生産性やパフォーマンスの向上が切実なニーズとなっています。こうした背景から「モチベーションマネジメント」に注目が集まっています。
しかし、モチベーションは個人の環境や価値観に深く関連するため、正しい実施方法に迷う企業も少なくありません。
そこで本記事では、モチベーションマネジメントとは何か、なぜ必要なのか、メリットや生産性向上への寄与、具体的な企業事例について解説します。
目次(タップして開閉)
モチベーションマネジメントとは?
モチベーションマネジメントとは、個人やチームの動機づけ(モチベーション)を高め、生産性や業績を向上させるための管理手法です。具体的には、従業員の働く意欲や情熱を引き出し、それを維持・強化するための戦略と実践方法を指します。
適切な運用により、従業員が自分の業務に対して意義や達成感を感じられるようになります。さらに忠誠心と満足度が高まり、組織への帰属意識が強化されるため、離職率の低下も期待できるでしょう。
| 無料お役立ち資料をダウンロード 離職防止に効果的な5つの取り組み |
そもそもモチベーションとは?
モチベーションとは、人が特定の行動を起こすための動機づけや意欲のことです。モチベーションは主に「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の2つに分けられます。
外発的動機づけ
外発的動機づけは、外部からの報酬や刺激によって行動や意欲が促される状態を指します。
| 外発的動機づけの例 | 発生する要因(→外部要因) |
|---|---|
| 営業目標の達成にともなう報酬や昇進 | ・承認欲求 ・経済的利益への欲求 ・罰則を避ける意識 など |
外発的動機づけによるモチベーションは、向上させる方法がシンプルでわかりやすい反面、向上させたモチベーションを維持するのが難しいという難点があります。
内発的動機づけ
内発的動機づけは、個人の内部からの欲求や興味によって行動や意欲が促される状態を指します。何かに深く興味を持ち、そのために全力を注ぐ様子が伺えます。
| 外発的動機づけの例 | 発生する要因(→内的要素) |
|---|---|
| 何かに深い興味を持ち、全力を注げるほどの関心 | ・やりがいや達成感 ・自分自身への未来志向 など |
内発的動機づけによるモチベーションは、自己成長や充実感に焦点が当てられており、効果が長続きする傾向にあります。一方で、短期間でモチベーションを上げるのは難しく、特定の物事に対する強い関心がなければ動機は発生しません。
モチベーションマネジメントは必要?
さまざまな社会背景を踏まえて、モチベーションマネジメントは注目され、日本企業の課題として必要とされています。
現代は価値観が多様化しており、なかには仕事にやりがいを見出せない従業員もいるかもしれません。従業員のモチベーションが低下すると、企業全体の生産性も落ちてしまう可能性があります。
モチベーションマネジメントは、企業が従業員の外的・内的動機づけを促し、仕事への意欲と全体の生産性を向上させる戦略です。
個人に帰属するモチベーションを企業側で管理・支援することは難しいですが、本人が仕事に対して情熱と目的意識を持つように促すことで、離職率の低下やチームの協調性促進などの効果が期待できます。
企業が社員のモチベーションを適切に管理できると、個人の仕事への満足度と全体の業績、両者を向上できて、持続的な成長が見込めるでしょう。
モチベーションマネジメントのメリット・効果
モチベーションマネジメントを実施することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。モチベーションマネジメントがもたらす効果をご紹介します。
| ・生産性の向上に貢献する ・離職率の低下につながる ・従業員の成長を促せる ・企業ブランディングによい影響を与える |
生産性の向上に貢献する
モチベーションマネジメントを実施すると、従業員のやる気や仕事への取り組み意欲が高まります。
従業員が能動的に業務に取り組めると、組織・個人の目標に向かって、少ないリソースで高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。効率的に業務が遂行できるため、全体の生産性の向上に貢献します。
離職率の低下につながる
従業員が現在の仕事に対して満足感や達成感を感じていると、離職への意欲は減少するでしょう。モチベーションマネジメントでは、従業員に対して正当な評価や適切なフィードバックを実施します。
自分の働きが認められることで、少しずつ愛社精神も育まれ、離職率の低下も期待できるでしょう。
従業員の成長を促せる
モチベーション管理では、従業員のスキルやキャリアの成長も重視されます。
自己成長への支援や評価結果、行動に対するフィードバックが行われるため、従業員は自分の潜在能力を最大限に引き出し、成長を遂げる機会が増えるでしょう。
また、もともとモチベーションが高い従業員は、より高い目標の達成を目指し、自発的にスキルアップに取り組むようになります。
企業ブランディングによい影響を与える
企業が従業員のモチベーションを重視し、成長と満足度向上をサポートするマネジメントは、外部に対してもよいイメージを与えます。
モチベーションが高い従業員は、業務の質を高める働きをするでしょう。業務の質が高まると、自社のサービスや商品の品質にもよい影響を与えるはずです。
ステークホルダーに対して、企業が人々や世の中を大切にしているというメッセージを強く発信できるため、企業ブランドと信頼性を高める効果をもたらします。
モチベーション低下の主な原因5つ
モチベーションマネジメントに本格的に取り掛かる前に、まずは従業員のモチベーション低下の原因や理由を確認しておきましょう。
| ・評価や待遇の不公平感 ・人間関係 ・業務内容 ・キャリアパス ・労働時間 |
評価や待遇の不公平感
評価と待遇の不足や不公平感は、モチベーション低下の主要な原因の一つです。
自分の努力や成果が適切に評価されなかったり、待遇が期待したものと異なったりすると、結果が見合っていないと感じてしまいます。
制度運用に透明性がなく、何が評価されているのかわからないために、不信感や不満が高まった結果、仕事に対する興味や意欲を失い、生産性が低下してしまうのです。
人間関係
職場の人間関係はモチベーションに大きな影響を与えます。
同僚や上司との関係が険悪であったり、コミュニケーションが不足したりしていると、職場の雰囲気が悪化します。その結果、チームワークの低下や職場でのストレス増加が引き起こされ、従業員のモチベーションの低下につながってしまうでしょう。
当然、ハラスメントが横行しているような職場環境も、モチベーション低下の要因につながります。
業務内容
業務内容が単調だったり、自身の興味や能力と合っていないと、モチベーションの低下につながります。
新しい挑戦がなく、日々の業務がルーティン化していると、従業員は成長の機会がないと感じ、次第にやる気を失ってしまうためです。
また、過度なノルマを課したり、到底達成できない目標設定を強いたりするなど、上司からの圧力やプレッシャーもモチベーション低下の原因になります。
キャリアパス
社内キャリアパスが不明確であったり、自身の目標と会社の方向性が合致していなかったりすると、不安や失望感が生じやすくなるものです。
成長や進展の機会が見出せないと、長期的なモチベーションの維持は難しいでしょう。
また、組織目標が不明確な場合も同様です。自社の方向性がわからないと、従業員は不信感が募りモチベーションを高められなくなります。
| 関連記事 キャリアパスとは? |
労働時間
過重労働や長時間労働が続くと、身体的な疲労が蓄積します。
身体的疲労は心理的なモチベーションの低下につながることが多く、健康を害したり、仕事への情熱を失ったりする原因になります。
バランスの取れた働き方や十分な休息がないと、継続的な生産性の維持が困難になるでしょう。
モチベーションマネジメントの実践ステップ
実際にモチベーションマネジメントを導入する場合、どのように進めればよいか悩む人もいるでしょう。従業員のモチベーションを上げるためのマネジメント実践ステップをご紹介します。
| 1.信頼関係を構築する 2.課題を共有する 3.フィードバックとサポートを行う 4.評価と改善を繰り返す |
1.信頼関係を構築する
モチベーションマネジメントの基礎は、信頼と尊敬に基づく関係の構築です。まずは部下との開かれたコミュニケーションと相互理解を促進し、個々のニーズと期待を把握しましょう。
ただし、部下は上司になかなか意見することができないものです。そのため、できるだけ対等なコミュニケーションを心がける必要があります。
部下の意見を真摯に受け止め、適切なアドバイスを送るなど、お互いが尊敬し合えるような関係性を構築することが望ましいでしょう。
2.課題を共有する
上司と部下の間で課題を共有しましょう。
「本来どうありたいのか」や現状とのギャップ、ギャップが生じている理由などを具体的に探り、モチベーションが低下している原因を明らかにします。お互いで課題の共通認識ができていると、今後取るべき行動を模索しやすくなるでしょう。
課題解決に向けた行動については、部下自身が考えます。上司はあくまでもアドバイスの提供にとどめることが大切です。
本人が課題を理解し、解決の必要性に納得したうえで自発的に計画を立てられると、モチベーションマネジメントの成果があらわれやすくなるでしょう。
3.フィードバックとサポートを行う
モチベーションを維持するためには、定期的なフィードバックとサポートが欠かせません。部下との定期的な対話を通じて進捗をチェックし、必要に応じて支援しましょう。
部下の成功を称賛し、改善が必要な部分に対して建設的に指導するマネジメントを実践することで、成長とモチベーション向上への道筋を示せます。
4.評価と改善を繰り返す
最後に、モチベーションマネジメントのプロセス全体を定期的に評価し、必要に応じて改善しましょう。
方法やアプローチの効果を分析し、組織の文化と従業員のニーズに合わせて、取り組み方や進め方を調整します。継続的に改善していくことで、組織全体の生産性と従業員満足度を高められるはずです。
モチベーションマネジメントを成功させるコツ
モチベーションマネジメントをより効果的なものにするためには、コツを押さえた運用を意識しましょう。8つのポイントをご紹介します。
| ・従業員の声に耳を傾ける ・目的の明確化・方向性の提示をする ・定期的にモチベーション状態を確認する ・褒め合う風土をつくる ・個々のニーズに対応する ・失敗から学ぶ文化を醸成する ・適切な報酬と認識のシステムを構築する ・ワークライフバランスを促進する |
従業員の声に耳を傾ける
従業員の声に耳を傾けることは、信頼関係の構築が必要なモチベーションマネジメントの基本です。
それぞれの意見や要望、悩みを注意深く聞くことで、部下のニーズを理解したうえで対応できます。対話はモチベーション向上に直結し、最終的に全体の業績向上にもつながるでしょう。
目的の明確化・方向性の提示をする
働く目的を明確にし、従業員に方向性を提示することも大切です。
目的と実現のための具体的な指針を示すことで、今何をすべきかを理解してもらいやすくなるため、従業員は自主的に動きやすくなるでしょう。
指針通りに動いて成果があらわれると、やりがいを見出せたり、スキルアップへの意欲が芽生えたり、さらなる成長を促進できるかもしれません。
定期的にモチベーション状態を確認する
個人のモチベーションは一定ではなく、時とともに変化します。
定期的に従業員のモチベーションの高さをチェックし、必要なサポートや改善を行いましょう。定期的な実施によって、高い意欲を維持できるため、組織にも好影響があるはずです。
褒め合う風土をつくる
お互いに認め合って褒め合う会社の風土をつくりましょう。
ポジティブなコミュニケーションは、従業員同士の協力と連携を促し、チームの一体感を高められます。メンバーの多くが同じ方向を目指すようになるのを助けられるようにマネジメントを行います。
個々のニーズに対応する
従業員は一人ひとり異なるニーズや価値観を持っているため、一律のアプローチでは効果が限定されることがあります。個人の目標や動機づけの要因を理解し、適切なサポートを提供することが重要です。
失敗から学ぶ文化を醸成する
従業員が失敗を犯した際にペナルティを与えるのではなく、その失敗から学び、成長するプロセスを重視する文化がモチベーションマネジメントには重要です。
失敗を恐れず挑戦する精神が、新しいアイデアや業務の改善につながるでしょう。
適切な報酬と認識のシステムを構築する
従業員の努力と成果に適切に報酬を与え、その成果を可視化・共有できる仕組みは、モチベーションの維持に欠かせません。
金銭などの目に見える報酬だけでなく、感謝の言葉や認識していることを伝えるなど非金銭的報酬も大きな効果を発揮するといわれています。
ワークライフバランスを促進する
過剰な労働を続けると、燃え尽き症候群などによってモチベーションの低下を招きかねません。
働き方改革の一環としても、健康なワークライフバランスを保つための企業側の支援は、長期的な職務満足とモチベーションの維持につながります。
フレックスタイム制度やリモートワーク、健康診断、ストレスマネジメントワークショップなど福利厚生プログラムの導入も検討してみましょう。
モチベーションマネジメントにおける具体的な人事施策4選
従業員のモチベーションを向上させるために、人事部門ではどのような施策を検討すればよいでしょうか。代表的な4つの施策を紹介します。
| ・モチベーションを把握する定期的な場を設ける ・適材適所の人材配置を行う ・人事評価制度を見直す ・適切な目標設定を実施する |
モチベーションを把握する定期的な場を設ける
モチベーションマネジメントの一環として、従業員一人ひとりの現状を把握するために、定期的なミーティングや調査が不可欠です。
従業員が何に取り組み、どのように感じているか、どんな支援が必要かを随時確認しましょう。コミュニケーションを頻繁に取っておくと、問題が発生したときも早期に発見と対処ができます。
定期的に1on1ミーティングやモチベーションサーベイを実施し、従業員の意欲や職場に対する感情を測定しましょう。
| 無料お役立ち資料をダウンロード 1on1ミーティングの課題を踏まえた実践ポイント |
適材適所の人材配置を行う
従業員のスキルや興味、キャリア目標を理解したうえで、適切な役割を与えたりプロジェクトに配置したりすることは、重要なモチベーションマネジメント施策です。
適材適所の人材配置によって、従業員は自分の強みと興味を最大限に活かせる可能性が高まり、職務への満足度とエンゲージメントを高められるでしょう。
| 無料お役立ち資料をダウンロード 最適配置を実現! 今ある人材情報を最大限活用するには |
人事評価制度を見直す
公正で透明な人事評価制度は、従業員のモチベーションと信頼を築く基盤となります。評価基準や報酬体系が明確で公正であると、従業員は自分の努力と成果が適切に評価されていると感じるでしょう。
反対に不透明または不公平な評価制度を放置しているとモチベーションを下げるため、定期的な見直しと改善がモチベーションマネジメントでは重要です。
適切な目標設定を促す
モチベーションマネジメントでは、適切な目標設定を促しましょう。目標設定では、SMARTの法則やMBO(目標管理制度)、OKRというフレームワークを活用できます。
SMARTの法則とは、次の要素の頭文字をとった用語で、達成に向けて取り組みやすいとされています。
| S | Specific | 具体的な |
|---|---|---|
| M | Measurable | 測定可能な |
| A | Achievable | 達成可能な |
| R | Relevant | 関連性がある |
| T | Time-bound | 時限性 |
企業目標と個人目標を連動させるMBO(目標管理制度)や、より大胆な目標にチャレンジしやすいOKRもおすすめです。導入によって、個人やチームの成長を促進する強力な動機づけができるでしょう。
企業側から適切な目標設定を促すことによって、従業員が役割と業績の期待値を理解しやすくなり、達成に向けた行動をサポートできます。
モチベーションマネジメントに成功した企業事例
モチベーションマネジメントは、さまざまな企業で取り入れられています。従業員のモチベーションを向上させるのに成功した企業では、どのような取り組みが行われているのでしょうか。
モチベーションマネジメントに成功した4社の企業事例をご紹介します。
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社のモチベーションマネジメントでは、コミュニケーションを活性化して業務を効率化するソフトウェアである「グループウエア」を利用しています。
日頃から従業員が「できること」「やりたいこと」「やるべきこと」を共有し、企業が配属や部署異動を決める際も、この3つの希望に基づき適正に判断しています。
同社はグループウエアによって、従業員が自分の能力や願望に合わせて仕事を選び取ることをサポートし、自己実現と成長を促進しました。さらに、チーム内での仕事の拡充と信頼の構築が促された結果、全体のチームワークが向上したそうです。
同社のモチベーションマネジメントの制度設計と運用は、従業員一人ひとりの成長を支援するメソッドとして、企業全体のモチベーションと生産性の向上にも寄与しているといえます。
参考:『モチベーション創造メソッドとは?──「やる気」のセルフコントロール』サイボウズチームワーク総研
小林製薬株式会社
小林製薬株式会社では、従業員の実績を称える「ホメホメメール」制度を実施しています。
具体的な制度の内容は、同社の社長が賞賛に値する行動をとった従業員に、直接メールを送るというものです。会社のトップが個人を理解したうえで褒めるため、従業員の「承認欲求」を満たす効果があります。
メールの内容はグループ報で紹介されることもあり、主体性を持って挑戦する姿勢を全社に示す役割も果たしているといえるでしょう。
このようなマネジメントは、従業員一人ひとりのモチベーション向上につながり、経営陣と現場の従業員とのコミュニケーション強化にもつながっています。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは、感謝の気持ちを伝え合うために「mertip(メルチップ)制度」を導入しています。
具体的には、スタッフ同士が社内コミュニケーションツールを利用して、リアルタイムに感謝や賞賛をし合い、さらにインセンティブとして一定の金額を贈り合うピアボーナスの仕組みを採用しています。
同社にはもともと「Thanksカード」という制度があり、mertipによって拠点を超えて気軽に賞賛し合えるようになりました。
導入から1か月程の効果は上々で、社内アンケート調査では満足度が約87%に達し、mertipの消化率も期待以上の数値を記録したそうです。
このモチベーションマネジメントは、従業員同士の連帯感を高め、より健全な組織文化の醸成に寄与しているといえるでしょう。
参考:『贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。』mercan
株式会社フリークアウト
株式会社フリークアウトでは「人は頼りにされるとより一層努力する」という心理をもとに、従業員全員をある分野のスペシャリストに育てるマネジメントが行われています。
一人ひとりが自分の得意分野で専門家になると、他者と比較して劣等感を持つことも減り、モチベーションが向上しやすくなるでしょう。
自分の知識で周囲の問題を解決できるようになると、専門性がさらに磨かれ「もっと役立ちたい」という意欲が生まれる好循環が確立されました。
結果的に社内でのモチベーションの高い従業員が増加し、個人の成長も促進され、モチベーションマネジメントに成功しているようです。
参考:『「悪人の集団」から「誰もが頼られる組織」へ。フリークアウトのマネジメント体制とは』SELECK
いずれの企業のモチベーションマネジメントも、モチベーション向上を主な目的として導入した制度や施策ではありません。
コミュニケーションの強化やスキルアップなど、最終的な業績向上も視野に入れて導入した制度が、モチベーションの向上にも寄与したといえます。
モチベーションマネジメントを検討している人事部門の担当者は、現場の状況を把握し、何が従業員個々の動機づけになるのかを理解することが大切です。
努力や成果に対する評価方法なども含めて、現場のニーズに合わせて考えることが、社員のモチベーション向上を目指すうえで人事部の基本的な役割と理解しましょう。
モチベーションマネジメントに必要な資格・研修
モチベーションマネジメントは、組織の成長と個人の満足度を向上させる重要な取り組みです。マネジメントスキルを高めるために、関連する資格の取得や研修の受講を考える方もいるかもしれません。
モチベーションマネジメントに関連する資格として、モチベーションマネジメント協会が提供する「公認モチベーション・マネジャー資格」が挙げられます。モチベーションへの社会的関心と重要性を高め、個人に気づきときっかけを提供することを目的としたビジネス資格です。
そのほかにもプロジェクトマネジメントの資格やコーチングの資格なども、モチベーションマネジメントに役立つでしょう。
参考:『公認モチベーション・マネジャー資格とは?』モチベーションマネジメント協会
また、研修やセミナーも、さまざまな企業によって開催されています。人事部門の研修担当者は、管理職・マネージャー層に向けて、外部の講師を招いたり研修を企画したりしてもいいでしょう。
モチベーション管理に関する資格や研修は、チームの意欲を引き出し、目標達成へ導く能力を高めることに焦点を当てています。
継続的な学びと実践を通して、成果を実感できるマネジメントスキルを身につけられるでしょう。
モチベーションマネジメントの実践で生産性向上へ
モチベーションマネジメントは、組織の持続的な成長と従業員の能力向上に不可欠な戦略です。
企業が従業員の心身の状況を詳細に把握し、個々のモチベーションの源を見つけ、積極的に働きかけることが重要とされる施策といえるでしょう。
モチベーションサーベイや1on1などを通じて個別のニーズを理解し、それに基づいて支援を提供することで、従業員一人ひとりの意欲を高められます。
モチベーションマネジメントを適切に運用できると、良好な組織風土の形成だけでなく、組織全体の生産性向上にも貢献し、企業の長期的な成功に結びつくでしょう。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!