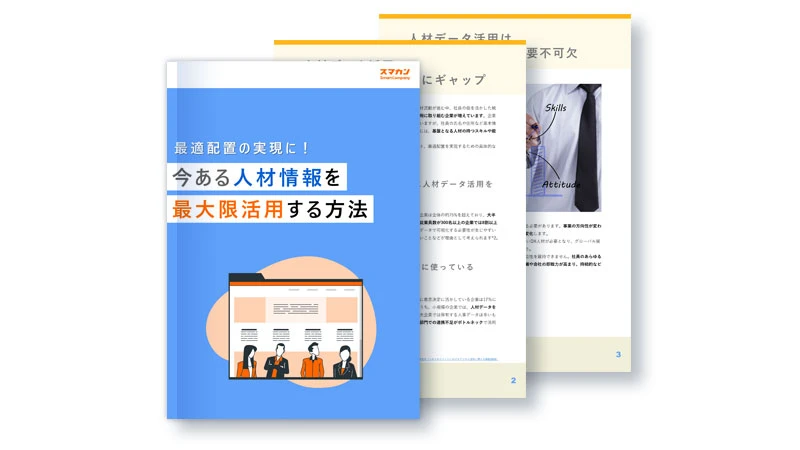- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事労務
後継者を育成する方法とは? 課題とポイント、計画の立て方を事例をもとに解説

関連資料を無料でご利用いただけます
後継者の育成は、特に中小企業にとって避けては通れない課題です。一方で、後継者の育成から目を背けている企業や、どうすれば後継者を計画的に育てていけるのか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、後継者を育成しないことによるリスクや育成に関する課題、後継者を育成する方法と意識すべきポイントなどを解説します。
後継者の育成に悩んでいる経営者や人事担当者の方は、ぜひお役立てください。
目次(タップして開閉)
後継者の育成とは?
組織における後継者の育成とは、経営者など現在重要なポジションにいる人物が退任や引退などをするときに、そのポジションを引き継ぐ人材を育成することを指します。
後継者の育成は、企業が継続的に成長し、競争力を維持するために必要不可欠なものといえるでしょう。
| 関連記事 抜擢人事のメリット・デメリット |
後継者を育成する目的
企業が後継者を育成する目的として、以下の4つが挙げられます。
| ・組織の継続性を確保するため ・長期的な企業の成長戦略を描くため ・従業員のモチベーションやキャリアアップの機会を提供するため ・コーポレートガバナンス・コードで規定されているため |
組織の継続性を確保するため
幹部の親族に適任者がいなかったり能力の高い人材がいなかったりして、重要なポジションを引き継ぐ人材がいないと、最終決裁者がいなくなり経営が立ちいかなくなる場合もあるため、企業は大きな危機に陥ることになりかねません。
そのため後継者を育成することで、企業の継続性を確保する必要があるのです。
長期的な企業の成長戦略を描くため
後継者が育成されることで、企業は将来的な成長戦略を継続的に推進できます。
候補者が企業のビジョンや戦略を理解し、実行するためのスキルや能力を身につけることで、企業は戦略通りに成長を続けられるでしょう。
従業員のモチベーションやキャリアアップの機会を提供するため
人材育成の一環で後継者候補を選出して将来的なポジションを用意することで、従業員のモチベーションを高めたり、企業へのエンゲージメントを強化できたりします。
キャリアアップやスキルアップの機会提供にもなるため、企業全体の能力を向上させることも期待できるでしょう。
『コーポレートガバナンス・コード』で規定されているため
上場企業であれば、『コーポレートガバナンス・コード』を遵守する目的で、後継者育成に注力する必要があるでしょう。『コーポレートガバナンス・コード』には、計画の策定や育成に十分な時間と資源をかけることが規定されています。
参照:『コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~』株式会社東京証券取引所(2011)
後継者が不在の場合の選択肢
社内で後継者を育成できない企業は、以下の3つの選択肢が考えられます。
| ・新しい人材の採用 ・企業の売却 ・廃業 |
新しい人材の採用
社内で後継者を育てる代わりに、外部から適任者を採用することで事業の継続性を確保できます。
ただし、経験豊富な人材の採用には費用や時間がかかり、組織文化やビジョンに合致する人材を見つけることが困難なこともあるでしょう。
企業の売却
後継者が不在で企業を存続できない場合は、売却することで資産を現金化し、事業を手放すという選択もあります。
ただし、企業を売却することは経営者にとって難しい決断であり、企業の評価や交渉などが必要なため多大な時間やコストがかかることが懸念点として挙げられるでしょう。
廃業
後継者が不在であり、外部からの採用や企業の売却も難しい場合は、事業を終了しなければならなくなるでしょう。
廃業する場合には、事業の売却とは違って資産の現金化が難しいため、処分や撤退にともなうコストが発生することがあります。廃業は、最終手段として慎重に決断することをおすすめします。
後継者を育成しないと起こるリスク
後継者を育成しない企業では、以下3つのリスクが発生する可能性があります。
事業承継の危機
後継者の育成に着手しないまま経営者の引退や急死などが発生した場合、事業承継の危機に直面する可能性があります。
候補者が不在のまま経営者がいなくなってしまうと、事業を引き継ぐ人材がいないため、企業の存続も危ぶまれるでしょう。
人材の流出とノウハウの喪失
後継者が育っていないと、企業に長年勤めるベテラン従業員が引退や転職などで退社した場合、その人が持っていた知識や技術が失われる可能性があります。
組織にとって重要なノウハウが失われてしまうと業務が滞り、いずれは業績が低下してしまうかもしれません。
社員のモチベーション低下
後継者を育成しない姿勢は、従業員のモチベーション低下にもつながります。
従業員が「長期的にこの企業にいても自分のキャリアアップにはつながらない」と感じると、転職などによって企業から離れていく可能性が高まるでしょう。
また外部からも将来性がないと感じられてしまうと、優秀な人材の採用が難しくなるかもしれません。
後継者育成において企業が抱える課題
後継者の育成は、企業にとって重要な課題です。しかし、その実現にはさまざまな課題が存在します。
経営者の意識が不足している
後継者問題に対する認識や取り組みが、不十分な企業も少なくありません。経営者が育成に熱心でなければ、従業員や関係者が思うように課題に取り組めないこともあるでしょう。
後継者を育成するには、経営者自身が課題意識を持って企業の長期的な発展につながることを理解し、積極的に具体的な施策を打ち出す必要があります。
従業員の意欲が不足している
後継者育成の課題として、従業員自身が後継者になることに興味がない、または後継者になるための必要なスキルや知識を習得するための時間や労力を割けないというケースも考えられます。
そのため企業は、従業員が後継者になることを積極的に考えるよう、研修やスキルアップの支援、キャリアプランのアドバイスなどを実施し、意欲を高めるように努めましょう。
後継者候補の選定と育成が難しい
そもそも後継者候補として従業員の適性やスキル、能力を把握できていないと、候補者の抜擢や育成はスムーズに進まないでしょう。企業は従業員のスキルや能力を公平に評価し、成長に応じて適切な教育プログラムを設計する必要があります。
| 無料お役立ち資料 【ガイドブック】効果的・効率的な「スキル管理」の手法 |
後継者候補が離職してしまう
後継者として育成していた従業員が、現在の業務に不満を抱いて退職したり、キャリアアップのためにほかの企業に転職したりしてしまうことも考えられます。
人材流出を防ぐためにも、従業員のキャリアプランを理解し、福利厚生や職場環境の整備に積極的に取り組むようにしましょう。また後継者育成を通じて、企業の将来性や経営理念に共感してもらう必要もあります。
| 無料お役立ち資料 【ガイドブック】自社で取り組める離職防止策 |
後継者を社内で育成する方法
後継者育成の課題を踏まえて、社内で後継者を育成するにはどのような取り組みがあるでしょうか。4つの方法をご紹介します。
| ・メンター制度の導入 ・教育プログラムの充実 ・キャリアプランの策定 ・幅広い経験を積むための環境整備 |
メンター制度の導入
後継者育成において、メンター制度の導入は効果的な手段の一つです。社長やマネージャーなどが、後継者候補のメンターとなり、直接的に指導や育成を行います。
後継者候補は経験豊富な先輩から指導を受けたり、少しずつ権限を譲り受けたりすることで、業務の専門知識や企業文化をより深く理解できるでしょう。
教育プログラムの充実
後継者の育成には、研修やセミナー、トレーニングなどの教育プログラムを充実させる方法も欠かせません。
専門の教育プログラムを通じて、候補者は企業経営に必要な知識を網羅的に学べるはずです。それによってスキルの土台が形成され、メンターによる直接的な指導の学習効率も高まるでしょう。
キャリアプランの策定
効率的に後継者育成を進めるためには、キャリアプランを策定することをおすすめします。
キャリアアップにつながるようなロードマップを用意することで、候補者は自身の強みを意識しながら、目標に沿って必要なスキルや知識を過不足なく習得できるでしょう。
キャリアプランを策定するとき、まずは後継者候補と面談を実施します。企業ビジョンや目標を共有し、将来像を具体的に描けるようにサポートしましょう。
幅広い経験を積むための環境整備
後継者候補には、新規事業や部門を横断するような業務を担当してもらい、成長を促しましょう。
候補者はさまざまな部署で幅広い経験を積むことで、業務ごとの関連性やビジネスモデルを多角的な視点で理解できるはずです。より広い視野や知識が身につき、経営者の考え方に近づけるでしょう。
後継者を社外で育成する方法
社内で後継者を育成するのが難しい場合、社外のサービスを利用して育成する方法もあります。3つの例をご紹介します。
| ・外部での教育 ・コンサルタントの活用 ・関連会社への出向 |
外部での教育
後継者を社外で育成する方法として、外部での教育を活用することが挙げられます。たとえば、セミナーやカンファレンス、研修会社、MBAプログラムなどの方法です。
外部での教育を受けてもらうことによって、従業員は社内だけでは身につけにくい知識やスキルを習得できるでしょう。特にMBAプログラムは、経営者候補としての知識やスキルを習得するために効果的といえます。
コンサルタントの活用
後継者を育成するために、コンサルタントの活用も検討するとよいでしょう。
コンサルタントは経験豊富な専門家であり、経営戦略やビジネスプロセスの改善、リーダーシップ開発などの分野で企業に助言してくれるものもあります。
コンサルタントが後継者のコーチングをすることで、リーダーシップなどのスキルを高められたり、社外の知識やトレンドを取り入れたりできるでしょう。
関連会社への出向
子会社やグループ会社がある場合は、後継者候補を出向させる方法もあります。
出向した候補者は別の企業で業務経験を積み、新たな知見やネットワークを得て、自社のビジネスと競合他社との関係性について深く理解できるでしょう。
将来的に本社の経営や重要ポジションを任せるための足がかりとして、子会社で経営を経験させることもあるようです。
後継者育成のポイント
企業が後継者の育成に取り組む際は、意識したい点があります。ポイントを4つ取り上げます。
| ・長期的な視点で取り組む ・透明性を確保する ・厳しい経験もさせる ・後継者の補佐も育成する |
長期的な視点で取り組む
後継者にふさわしい能力を身につけるには、長い時間が必要です。
後継者を育成する際には長期的な計画を立てて、候補者には最終的なゴールを伝えつつ、じっくり育てていけるような教育プログラムを設計しましょう。
また時間をかけて育成する中で、候補者が離職してしまっては本末転倒です。候補者の心身のサポートも忘れないようにしましょう。
透明性を確保する
後継者候補には、企業の経営理念や方針を明確に伝えて、育成プログラムや評価基準についても隠すことなく伝えるようにしましょう。
そうすることで候補者は将来像をイメージしやすくなるため、育成プログラムへの納得が得られモチベーションも高められるでしょう。
社内で育成に関する透明性を確保することで、後継者候補に該当しない従業員の理解も得られ、衝突も避けられるはずです。
厳しい経験もさせる
新規事業の立ち上げや海外事業の展開など、難しい仕事を乗り越える経験もさせることもポイントです。通常の業務では身につきづらい決断力や強いリーダーシップを磨けるでしょう。
周囲がサポートできる範囲であえて失敗を経験させることによって、問題解決能力やストレス耐性を高めることもできます。ただし後継者候補の性格や性質を考慮して、負荷を与えすぎないように注意しましょう。
後継者の補佐も育成する
後継者の補佐をする従業員がいることもポイントです。お互いに切磋琢磨し合って成長につながるだけでなく、候補者に補佐役のマネジメントや育成を担当してもらうと、経営者として重要な経験を積ませることができるでしょう。
経営者を継いだあとも、ともに成長してきた補佐役がいれば気軽に相談しやすく、後継者が孤独になることを防ぐ効果も期待できます。
後継者育成の準備と計画
後継者育成に必要な準備や進め方について、一般的な流れをご紹介します。企業の状況によって異なるため、参考までに理解しましょう。
| 1.自社の経営方針と経営戦略を再確認する 2.後継者の育成計画を立てる 3.後継者の要件を決めて候補者を選定する 4.後継者として必要な経験とスキルを身につけさせる 5.部分的に経営にかかわる業務を任せる 6.経営者から引き継ぐ |
1.自社の経営方針と経営戦略を再確認する
後継者を育成するためには、まずは自社の経営方針と経営戦略を再確認しましょう。後継者に求められる役割や能力を明確にして、育成計画の方向性を定めます。
2.後継者の育成計画を立てる
次に、後継者の育成計画を立てます。計画の中には、後継者に必要なスキルや知識、経験などを規定します。あわせて育成期間や評価方法、報酬体系なども考慮して含めましょう。
3.後継者の要件を決めて候補者を選定する
自社で後継者に求められる要件を明確にして、候補者を選定します。候補者の選定にあたっては、業務適性や人物評価、モチベーションなどを総合的に判断するとよいでしょう。
4.後継者として必要な経験とスキルを身につけさせる
選ばれた候補者に対して、将来のために必要な経験とスキルを身につけさせます。この段階での育成内容は、個人の能力や成長度合いに合わせて作成しましょう。
このときに段階を踏まずに従業員に合わない教育を行ってしまうと、従業員は必要以上に負担を感じ、モチベーションが低下してしまうかもしれません。
5.部分的に経営に関わる業務を任せる
後継者に対して、徐々に経営にかかわる業務を任せていきます。この段階での業務は、一般の従業員が担当する業務とは異なり、社長にふさわしい視点や判断力を養うためのものに移行します。
6.経営者から引き継ぎを行う
最後に、経営者から後継者への引き継ぎを行います。この段階で後継者がしっかりと経営者としての役割を果たせるように、アドバイスや指導を行うことが重要です。
また後継者の力量によっては引き継ぎをスムーズに行うために、段階的に権限を移行することも検討するとよいでしょう。
後継者育成の企業事例
実際に後継者育成を行っている企業ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。後継者育成に注力している3社の事例をご紹介します。
花王株式会社
花王株式会社では、後継者候補となる人材を以下の3つに段階分けしています。
| ReadyNow | 今すぐに後任となれる人財 |
|---|---|
| ReadySoon | 1~3年で後任として育成する人財 |
| MidTeam | 3~5年で後任として育成する人財 |
それぞれのレベルに合わせた評価や教育のプログラムを設計することで、より確実に後継者を育成できる仕組みとなっているようです。
ニデック株式会社(旧:日本電産株式会社)
ニデック株式会社は後継者を育成するための制度を豊富に用意しています。
| ・次世代グローバル経営人材育成 ・海外トレーニー制度 ・グローバル経営大学校 ・永守経営塾 |
また、2022年からは社内の優秀な人材から後継者候補を選んで会長みずから指導する取り組みに着手し、後継者の育成にさらに力を入れているようです。
参照:『人材の育成』ニデック株式会社
参照:『日本電産 後継者候補30代から教育 3代先まで約30人』産経新聞(2022)
株式会社小松製作所
株式会社小松製作所は、自社の価値観をまとめた「コマツウェイ」の中で、リーダーの行動指針の一つとして後継者の育成を掲げています。
計画的に後継者の育成を進めるため、幹部クラスの従業員には自分のあとを継ぐ適任者を報告するように義務づけています。毎年1回「自分の次」のみならず「次の次」まで指名する必要があるようです。
参照:『人と共に -人材育成の取り組み、グローバル人材育成』コマツ(2022)
参照:『後継者は次の次まで決めて育成』NIKKEIリスキリング(2016)
まとめ
後継者の育成は、企業が成長し続けるために必要不可欠なものです。もし後継者が不在であれば、事業が継続できなくなるリスクが考えられます。
しかし、多くの企業では経営者や従業員の意識不足などによって、後継者の育成に苦戦している現状を耳にすることがあります。
後継者の育成を円滑に進めるには、長期的な計画を立て、必要な経営の知識やスキルが得られるように、育成プログラムを設計することが重要といえるでしょう。
後継者育成にもタレントマネジメントシステム『スマカン』
後継者候補を選定したり、候補者に適した育成プログラムをつくるためには、あらかじめ従業員の経歴やスキルなどを把握しておかなければなりません。
全従業員のスキルの可視化には、タレントマネジメントシステムの導入をおすすめします。人材データを一元管理して可視化・分析することで、後継者候補の選定や育成に活かせるはずです。
外部から後継者候補を採用するときも、システムに集約された情報をもとに採用計画を立てたり、人材要件を整理したりできるでしょう。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!