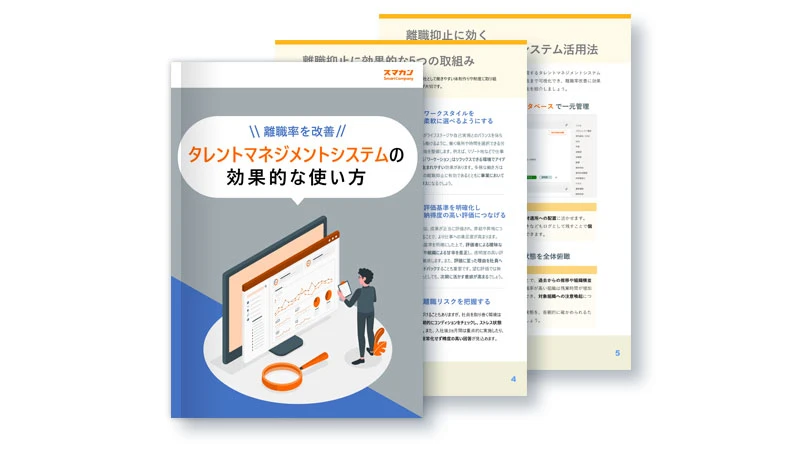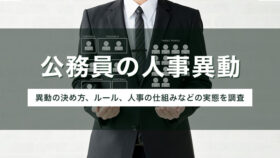- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人事戦略
離職率が低い業界とは|ランキングや特徴、メリット・デメリットも紹介

関連資料を無料でご利用いただけます
離職率の低下は、企業の安定的な経営にとって重要な課題です。離職率が低い業界にはどのような特徴があるのでしょうか。また、自社の離職率を低下させるには、どのような施策に取り組めばいいのでしょうか。
当記事では、離職率が低い業界のランキングや特徴、メリット・デメリット、離職率を下げる方法についてご紹介します。ぜひ今後の人材戦略の参考にしてみてください。
目次(タップして開閉)
そもそも離職率とは?
「離職率」とは、ある期間内に離職した従業員の割合を指します。離職率の算出期間は、期初から期末までの1年や入社から1〜3年など、算出する目的によって異なります。離職率は、企業の働きやすさなどの指標となるため、人事担当者にとって重要なKPIといえます。
離職率の計算方法
一般企業では、以下の計算式で離職率を算出することが多いです。
| 離職率 = 企業が定める一定期間内の離職者数 ÷ 起算日の在籍者数 × 100(%) |
たとえば、A社では2023年1月1日時点で300人(うち新入社員15人)の従業員がいるとします。そして1年後に、新入社員5人を含む10人が退職したとき、1月1日を起算日とした場合の離職率を計算してみましょう。
従業員数の変化
| 2023年1月1日 | 2024年1月1日 | 1年間の退職者数 | |
|---|---|---|---|
| 全従業員 | 300人 | 290人 | 10人 |
| 新入社員 | 15人 | 10人 | 5人 |
全従業員の1年間における離職率は
| 全従業員の離職率 = 退職者数 ÷ 全従業員数 × 100(%) |
と計算できるので、
| 10人÷300人×100 =0.03×100 =3.33(%) |
A社における全従業員の離職率は3.33%です。
新入社員に限った場合の1年間の離職率は
| 新入社員の離職率 = 新入社員の退職者 ÷ 全従業員数 × 100(%) |
と計算できるので
| 5人÷300人×100 =0.01×100 =1.66(%) |
A社における新入社員の離職率は1.66%です。
日本の平均離職率
日本の平均離職率は、厚生労働省が公表している資料から調べられます。
同省によると、2021年の国内企業全体の常用労働者の離職率は13.9%でした。また、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者35.9%、新規大卒就職者31.5%であると報告しています。
産業別で見た場合の2021年の離職率は「宿泊業、飲食サービス業」が 25.6%ともっとも高く「生活関連サービス業、娯楽業」が 22.3%と続いています。
参照:『令和3年雇用動向調査結果の概要「入職と離職の推移」』厚生労働省
参照:『新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)』厚生労働省
参照:『令和3年雇用動向調査結果の概要「産業別の入職と離職」』厚生労働省
離職率が低い業界ランキング
離職率が低い業界を、厚生労働省の資料に基づいてランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 業種 | 離職率 | 入職率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 複合サービス事業 | 8.1% | 6.6% |
| 2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8.7% | 8.2% |
| 3位 | 情報通信業 | 9.1% | 11.5% |
| 4位 | 建設業 | 9.3% | 9.7% |
| 4位 | 金融業・保険業 | 9.3% | 6.2% |
| 5位 | 製造業 | 9.7% | 8.2% |
※国内企業全体の常用労働者の離職率は13.9%
参照:『図3-1 産業別入職率・離職率(令和3年(2021))』厚生労働省
1位:複合サービス事業
「複合サービス事業」とは、複数の異なるサービスを提供する事業を指し、郵便局や農業協同組合などが該当します。当業種の2021年の離職率は8.1%でした。
離職率が低い理由には、労働時間が比較的短いのに対し、収入が高い傾向にあることが考えられます。ワークライフバランスを保ちやすいという点が、離職率の低さにつながっているといえるでしょう。
2位:電気・ガス・熱供給・水道業
電気、ガス、水道など生活インフラに関連する業界も離職率が低い傾向にあります。2021年の離職率は8.7%でした。
インフラ業界はいつの時代も景気に左右されにくいことや、新規参入の壁が高いため競合が少ないことから、業績が比較的安定しているのが特徴です。そのため、給与が大幅に下がるリスクも低く、離職者は少ない傾向にあります。
3位:情報通信業
情報通信業は入職率に対し、離職率が低い業界といえます。2021年の離職率は9.1%でした。
情報通信業界は、リモートワークやフレックスタイムなど働き方が比較的柔軟で、資格やスキルに応じて高い給与水準が保たれているのが特徴です。
そのため、長く勤めたい人やキャリアアップを目指す人にとって、魅力的な環境であることが、離職率の低さに影響していると考えられるでしょう。
4位:建設業
建設業は2021年の離職率が低い業界4位にランクインしています。離職率は9.3%でした。
建設業の中でも大手ゼネコンは、給与水準が高く福利厚生も充実しているため、離職率の低さの理由といえるかもしれません。一方で、中小企業の場合は労働環境が十分に整備されていないことも珍しくありません。
そのため建設業は、企業規模によって離職率に差が発生する可能性もあります。
4位:金融業・保険業
金融業・保険業の離職率は、建設業と同率の9.3%でした。代表的な金融業・保険業には、銀行や保険会社、証券会社などがあります。
金融業・保険業の離職率が低い理由は、数字主義の傾向が強く、目に見える成果にやりがいを感じる人が多いことが一因として考えられるでしょう。営業成績が高い人は、新卒でも大きな収入を得られる可能性があり、離職を考えにくいのかもしれません。
一方、数字のノルマが厳しいと、離職してしまう可能性もあります。入職率に対して離職率が高いのは「自分には向いていない」と考える人が一定数いるということかもしれません。
5位:製造業
製造業の離職率も全体平均に対して、低いといえるでしょう。2021年の離職率は9.7%でした。
製造業の離職率が低い理由は、いくつか考えられます。大手メーカーの場合、待遇のよさや、製品に対する需要の安定性などが挙げられるでしょう。中小企業でも、近年は人材を確保するために手厚い福利厚生を用意している企業が増えているようです。
また、製造業の中でも工場勤務では、融通がききやすいシフト制や残業の少なさも、離職率の低さにつながっているのかもしれません。
| 無料お役立ち資料 離職率を改善 〜タレントマネジメントシステムの効果的な使い方〜 |
離職率が低い企業の5つの特徴
離職率が低い企業には、共通の特徴があることが多いです。ここでは、5つの特徴をご紹介します。
1.給与水準の高さ
離職率の低い企業に共通しているのは「給与水準の高さ」です。どのような業界・職種でも、働きに見合った給与がもらえないと、退職を考える従業員は多くなるでしょう。
労働に見合った収入、または平均よりも高い給与額が得られると、心にゆとりを持ちながら働けるはずです。日々を充実した気持ちで過ごせる企業なら「ずっとこの会社で働きたい」と思う人も多くなるでしょう。
2.福利厚生の充実度
いくら高収入を得られるとしても、休暇がまったく取れない、手当が何もないなどの環境では、離職率は高いままでしょう。産休・育休や産後パパ育休、介護休暇が取得しやすいなど、福利厚生が充実しており、従業員個々のプライベートを尊重している企業は、離職率が低い傾向にあります。
3.業界の安定性
景気に左右されず、安定した業界は離職率が低い傾向にあります。たとえば、生活インフラに関連する業界は、時代を問わずサービス利用者がいるため、安定しているでしょう。
安定した業界の企業は、倒産のリスクや給与が大幅に下がる可能性が低く、従業員は安心して働けるでしょう。その結果、離職率も低くなりやすいといえます。
4.組織文化が浸透している
離職率が低い企業は、組織文化が浸透するように従業員を育成している傾向にあります。
組織文化は、従業員の行動指針となる場合が多く、価値観や目的、目標、振る舞い、規範などを含みます。組織文化が浸透していると、従業員は仕事に対する目的意識や誇りを持ちながら働けるため、帰属意識が芽生えて離職率は低くなると考えられるでしょう。
5.人事評価制度の公正性
離職率が低い企業は、公正な人事評価制度を行っているのも特徴です。上司の主観が入った評価ではなく、公平で透明性のある人事評価を実施し、評価結果をもとに適切な待遇を設けています。
そのため、従業員は評価に対して納得感を得られ、モチベーションを高めながら仕事と向き合うことができます。そのような企業では、従業員の離職率は低くなりやすいでしょう。
離職率と企業規模の関係
ここでは2022年に厚生労働省が発表した、就職後3年以内の事業所規模別離職率をもとに、離職率と企業規模の関係を見てみましょう。
| 企業規模 | 5人未満 | 1000人以上 |
|---|---|---|
| 3年以内の離職率 | 55.9% | 25.3% |
上記を見ると、企業規模が大きいほど離職率が低いと感じられますが、これだけで判断するのは難しいでしょう。
従業員数が少ない小規模企業では責任範囲が広いため、仕事にやりがいを感じられると長く働きたいと考える人が増えるかもしれません。また、企業文化や福利厚生などが魅力的なら、小さな企業でも離職率は低くなることもあるでしょう。
反対に企業規模が大きくても、組織内の人間関係が複雑だったり、個人の責任範囲が狭く、やりがいや自己実現の機会が少なかったりすると、転職による離職率の上昇が考えられます。
そのため、離職率と企業規模の関係は安易に結びつけないほうがよいかもしれません。
参照:『新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します』厚生労働省
離職率が低い業界で働くメリット
離職率の低い業界で働くメリットは、以下の5つが挙げられます。
安定した就業環境
離職率が低い業界では、職場環境が整備されていることが多く、長期的なキャリア形成に向いているといえます。残業も少ない傾向にあるため、健康的に働けるでしょう。
ワークライフバランスが取りやすい
離職率が低い業界は、勤務時間に対して業務量が適切であることが多いため、プライベートを確保しやすく、ワークライフバランスを取りやすいというメリットがあります。そのような企業では、サービス残業やハラスメントも少ない傾向にあるため、心身ともに充実した毎日を過ごせる可能性も高いといえます。
専門的なスキルアップが期待できる
離職率が低いということは、長く働いている従業員が多くいるということです。業界での経験が豊富でスキルが高い人と一緒に働けるため、より専門的な知識や技術を身につけられるでしょう。
収入アップにつながる
1つの企業で長く働くことで豊富な知識や技術が身につくと、スキルに見合った収入を得られる可能性が高まります。
また、離職率が低い企業では、適切な人事評価が実施されていることが多いため、努力した分だけ、納得のいく評価や報酬につながるでしょう。
良好な人間関係を構築できる
離職率が低い業界では、従業員同士が活発にコミュニケーションを取っている企業が多い傾向にあります。従業員同士の関係が良好であると、組織力も強化できるでしょう。
社内コミュケーションが活発な強い組織は、従業員エンゲージメントも高くなりやすいです。従業員が充実して働けると、将来的に企業全体の生産性や業績の向上も期待できるでしょう。
離職率が低い業界で働くデメリット
離職率が低い業界はメリットがある一方、実はデメリットもあります。離職率が低い業界で働く主なデメリットは、以下の3つが挙げられます。
成長が限定的になる
離職率が低い業界は安定している反面、業界全体の成長性が限定的になりがちです。そのため、新しい技術やビジネスモデルに対する変化や発展が遅れる可能性があります。
また、従業員個人においても1つの企業に長くとどまることで、企業文化や業界に慣れすぎてしまい、ほかの企業や業界に転職しにくくなるというデメリットも考えられます。
昇進が難しい
離職率が低い業界は、退職する従業員が少ないため、昇進が難しいケースもあります。仮に昇進ポストに空きが出ても、競争率が高く、ライバル同士で関係性が悪化する懸念もあるでしょう。
適当に仕事をする従業員もあらわれる
離職率が低くて働きやすい環境は、意欲的に仕事に向き合う従業員がいる一方で、その環境に甘えてしまう従業員を増やしてしまうかもしれません。働きやすいがために、やる気をなくして適当に仕事をする人があらわれるのです。そのような従業員ばかりになってしまうと、企業の成長は滞ってしまうでしょう。
離職率を低くする方法
ここまで、離職率の低い業界やその特徴などを紹介してきました。自社の離職率に悩んでいる場合「どうすれば離職率を低くできるのだろう」と考えるのではないでしょうか。
ここでは、離職率を下げる7つの主な取り組みをご紹介します。自社で着手できそうなものは参考にしてみてください。
従業員のやりがいを向上させる
従業員が仕事にやりがいを感じられると、離職率が低くなる可能性は高まります。
たとえば、
| ・プロジェクトに関する意見を聞く ・従業員が自由にアイデアを出せるような環境を整える ・キャリアアップの道を示す |
などの方法があるでしょう。
企業側が従業員の意見を取り入れる体制を整備することで、従業員は声をあげやすくなり、仕事に対してやりがいを感じられるようになるはずです。
給与・報酬制度を見直す
給与・報酬制度が公平であることは、従業員が離職しないための条件の一つです。企業は、従業員の仕事内容に応じた給与・報酬制度を整備することで、離職率の低下を促せるでしょう。
福利厚生を充実させる
従業員の生活面を支援する福利厚生制度を充実させることも大切です。
たとえば、
| ・資格取得の支援 ・社員旅行の補助 ・子育て支援制度の導入 ・健康診断の実施 ・休暇取得の推奨 |
などが挙げられます。
自社の福利厚生を見直し、不足しているものがあれば新たな制度を検討するといいでしょう。また、従業員に認知されていない福利厚生があれば、周知を徹底します。
ワークライフバランスの改善
従業員が仕事とプライベートのバランスを取れるようにすることも、離職率を低くするための重要な施策です。フレックスタイム制度や在宅勤務の導入など、柔軟な働き方を促進し、従業員のワークライフバランス改善を目指すといいでしょう。
人事評価制度の見直し
従業員の能力や成果を適切に評価することも、離職率の低下につながる重要な施策です。従業員の成長やキャリアアップを支援する評価制度を整備するとともに、納得度の高い評価を実施できるよう、評価者への教育も行いましょう。
| 関連記事 人事評価の見直しポイントまとめ |
キャリアアップの制度や環境の整備
離職率が低い企業は、従業員のキャリアアップを促進するための制度や環境を整備しています。従業員一人ひとりが能力を発揮し、長期的なキャリアアップを目指せるように、教育研修やキャリアカウンセリングを行うなどの支援も検討するとよいでしょう。
コミュニケーションの活性化
従業員同士のコミュニケーションを活性化する取り組みも、離職率低下につながります。全従業員を集めた決起大会を行ったり、懇親会を開催したり、部署の垣根を超えた交流の場を提供するなどもよいでしょう。
従業員が円滑なコミュニケーションをはかれる企業は、離職率を下げるだけでなく、企業全体の生産性向上にもつながります。
また、上司と部下が定期的に会話ができるよう、月に一度1on1ミーティングを実施するなども離職率を下げるのに効果的です。業務の進捗だけでなく、悩みなどを話せる場を設けましょう。
| 無料お役立ち資料 1on1ミーティングとは| 効果的な実践方法と運用時のポイント |
離職率低下にも役立つタレントマネジメントシステム
より効率的に離職率を低下させるには、タレントマネジメントシステムの活用も検討してみてはいかがでしょうか。
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、人材情報を集約して育成・管理・評価に活かすクラウドツールです。アンケートでエンゲージメントや従業員満足度を可視化し、離職率の低下につながる施策を考案できます。たとえば、スキルや能力に見合った適切な研修プログラムを提供したり、適材適所の配置転換を行うなどの方法が考えられるでしょう。
1on1の記録管理も活用しながら、従業員のコンディションを継続的にチェックし、離職の兆候を捉えるという使い方もあります。従業員の変化に早めに気づき、対策を打てるといいでしょう。
目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
離職率は、採用の指標として重視されることも少なくありません。低い離職率を維持するためには、給与や福利厚生の充実、ワークライフバランスの改善、キャリアアップの機会提供など、従業員が働きやすい環境を整備することが重要といえます。
離職率が低いからといって必ずしも会社全体のパフォーマンスが高いとは限りませんが、当記事で紹介した方法を参考に、従業員が能力を最大限に発揮できる組織を目指してみてはいかがでしょうか。

記事監修
スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎
一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。
SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!