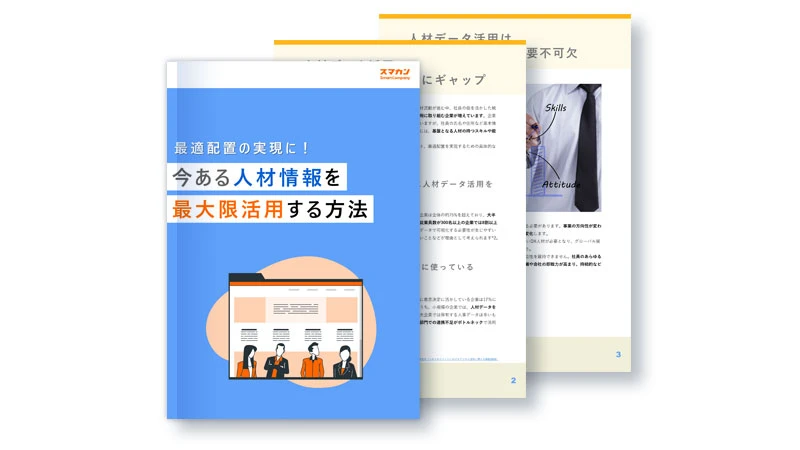- 最終更新日:
- タレントマネジメント
- 人材育成
日本の女性管理職が少ない理由とは? 増やすメリットや取り組み事例を紹介

関連資料を無料でご利用いただけます
近年の日本ではダイバーシティが尊重され、誰もが活躍できる社会の実現に向けて女性管理職を増やす取り組みをしている企業もあります。
しかし現状として、女性管理職を有する日本企業は多いとはいえません。女性管理職が少ない社会では、女性のキャリアアップの機会が限定され、組織や社会全体の成長を阻害する問題にもなります。
そこで本記事は、日本における女性管理職が少ない理由や、女性管理職を増やすメリット、実際の取り組み事例をご紹介します。
目次(タップして開閉)
女性管理職が少ない現状
日本において、女性が管理職のキャリアに就くことは依然として難しい状況が続いています。女性管理職が少ないといっても実際はどの程度の割合なのでしょうか。
女性管理職が少ない現状について、厚生労働省や内閣府男女共同参画局が公表している資料に基づき、詳しく説明します。
女性管理職がいる企業の割合
女性管理職が存在する企業は増えていますが、その割合はいまだに低いとされています。
2021年度の『雇用均等基本調査結果』によると、係長以上の女性管理職は6割を超えていますが、課長相当職以上になると5割にとどまっています。
女性管理職がいる企業の割合
| 課長相当職以上の女性管理職がいる企業 | 53.2% |
|---|---|
| 係長相当職以上の女性管理職がいる企業 | 61.1% |
役職別の女性管理職比率
さらに役職別に女性管理職の割合を見てみましょう。同調査によると、10人以上の企業規模において、役職ごとの女性管理職比率は10〜20%前後であることがわかります。
いずれも調査を開始した2009年に比べてやや上昇していますが、部長相当職以上についてはいまだに10%を切っています。
役職別の女性管理職比率(従業員数10人以上の企業)
| 2009年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|
| 役員 | 20.6% | 21.4% |
| 部長相当職 | 4.5% | 7.8% |
| 課長相当職 | 6.1% | 10.7% |
| 係長相当職 | 12.2% | 18.8% |
企業規模別の女性管理職比率
2021年度の『雇用均等基本調査結果』では企業規模が大きくなるほど、女性管理職が在籍する企業の割合が低くなっていることも示しています。
企業規模別の女性管理職比率
| 2009年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|
| 役員 | 20.6% | 21.4% |
| 部長相当職 | 4.5% | 7.8% |
| 課長相当職 | 6.1% | 10.7% |
| 係長相当職 | 12.2% | 18.8% |
産業別の女性管理職比率
続いて、課長相当職以上(役員含む)の女性管理職の割合を産業別に見てみましょう。
同調査によると、医療・福祉業界で女性管理職の比率が約5割でもっとも高く、続いて生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、飲食サービス業と続きます。また、2位以下の産業は、2.5割以下にとどまっています。
産業別の女性管理職比率(課長相当職以上(役員含む))
| 医療・福祉 | 48.2% |
|---|---|
| 生活関連・サービス業 | 24.3% |
| 娯楽業 | 24.3% |
| 宿泊業 | 22.3% |
| 飲食サービス業 | 22.3% |
| 教育・学習支援サービス | 19.8% |
世界と比べた日本の女性管理職比率
日本の女性管理職比率は、世界的に見ても低い水準にあります。
内閣府男女共同参画局が公表している『共同参画』によれば、2021年の諸外国の女性役員の割合は、フランスの45.3%がもっとも高く、そのほかの欧米諸国も30%前後で推移しています。
以下の主要7か国だけで見ると、日本は半数以上の差をあけて最下位に位置していることがわかります。
| フランス | 45.3% |
|---|---|
| イタリア | 38.8% |
| イギリス | 37.8% |
| ドイツ | 36.0% |
| カナダ | 32.9% |
| アメリカ | 29.7% |
| 日本 | 12.6% |
参照:『令和3年度雇用均等基本調査結果』厚生労働省
参照:『「共同参画』2022年12月号』内閣府男女共同参画局
日本の女性管理職が少ない本当の理由とは?
女性管理職が少ない日本の実情には、さまざまな要因が絡み合っているため、一概に説明することはできません。しかし、一般的にいわれている主な理由としては、以下の5つが挙げられます。
| ・管理職に対するイメージや認識の問題 ・管理職への意欲不足 ・社会全体での旧来的な性別役割へのこだわり ・女性の職場での働きやすさや環境整備の不足 ・育児休暇の取得による評価への影響 |
管理職に対するイメージや認識の問題
管理職は責任を求められるだけでなく、部下のマネジメントなど、さまざまな業務をこなさなければならないというイメージがあります。
給与は一般社員よりも高い水準にあっても心身への負担が大きいという印象から、管理職に就くことをためらう女性も少なくありません。実際、日本の企業においては管理職の業務量が多く、残業が常態化しているといわれています。
また、管理職は労働基準法が規定する管理監督者に該当し、労働時間などの規制が適用されません。このような事情も、女性管理職への昇格を難しくしている問題の一つといえるでしょう。
管理職への意欲不足
日本では、まだ男性よりも女性の方が家族や子育てに重きを置く傾向があります。
そのため女性は職場での昇進やキャリアアップよりも、家庭との両立や生活の安定を優先することが多く、管理職になることに対して十分なモチベーションを保ちにくいといえるでしょう。
近年では「出世よりも安定を求める」という意識を持つ人も一定数いることから、企業が女性管理職を増やすための施策を行っても、女性自身が希望しない限り管理職の割合は増えにくいと考えられます。
社会全体での旧来的な性別役割へのこだわり
一部の人々の中には、男女の役割分担について男性が家族を養う責任を持ち、女性が家事や育児を担当するという旧来的な考え方が根強く残っています。
そのため女性が管理職に就くことに対して、職場や社会の中で肯定的な評価が得られない可能性があることも、女性管理職の増加を阻んでいる要因の一つといえます。
女性の職場での働きやすさや環境整備の不足
女性が結婚や出産を経験すると、仕事と家庭の両立が難しくなる場合があります。
女性が働きやすい環境が整っていない企業では、キャリアアップや昇進に向けての取り組みをあきらめざるを得なくなってしまうでしょう。
また、働く環境が女性にとってストレスや負担が大きかったり、女性管理職のロールモデルがいなかったりすることは、管理職への昇格にためらいを持つ原因といえるかもしれません。
育児休暇の取得による評価への影響
女性が出産・育児のために長期休暇を取得すると、評価や昇進に影響を与えてしまうことも日本の女性管理職が少ない理由の一つです。
日本の企業では、これまで年功序列や勤続年数の長さなどで評価する傾向にありました。今もそのような評価方法を採用している企業では、産休や育児休暇を取得した女性従業員は評価・昇進の機会を失ってしまう可能性もあります。結果として、女性管理職へのキャリアアップが望めなくなってしまうのです。
女性は管理職になりたくない?
日本では、管理職に就くことに対して消極的な女性が多いといわれています。これは、出産や子育てにより、家庭と仕事の両立が難しい環境が、少なからず影響しているでしょう。
働く意欲のある女性に「結婚や出産をしても100%仕事に時間を使えるなら、管理職を希望するか」と質問をしたところ、64.4%の人が管理職を希望すると回答しています。
この調査から、家庭と仕事の両立が叶うなら管理職になりたいと考えている女性は多いと読み取れるでしょう。
| 結婚や出産をしても100%仕事に時間を使えるなら、管理職を希望するか | |
|---|---|
| 希望する | 15.4% |
| 条件によっては希望する | 49.0% |
| 希望しない | 26.8% |
| どちらでもよい | 8.7% |
参照:『しゅふJOB総研調査』株式会社ビースタイルホールディングス
企業が女性管理職を増やすメリット
女性管理職が増えると、企業にとってどのような影響があるのでしょうか。女性管理職を増やすことで得られる8つのメリットをご紹介します。
| ・優秀な女性人材が採用できる ・働き方が多様化し企業の生産性が高まる ・ダイバーシティの促進が実現する ・人事評価の公平性・透明性が向上する ・女性管理職のロールモデルが生まれる ・社会的評価が向上する ・部署内のコミュニケーションが円滑になる ・ESG投資家からの注目が集まる |
優秀な女性人材が採用できる
女性管理職が増えることで、企業はより優秀な女性人材を採用しやすくなるでしょう。向上心のある女性の中には、転職活動において「昇進の可能性」を重視する人も少なくありません。
自社に女性管理職が多ければ、入社を希望する女性も増える可能性があります。管理職を希望する女性が増えると、企業側も採用活動がスムーズになり、人材確保が容易になるでしょう。
働き方が多様化し企業の生産性が高まる
女性管理職が増えると、組織として女性が仕事と家庭の両立をしやすい環境が整備される可能性が高くなります。
たとえば、フレキシブルな勤務時間や在宅勤務、育児休暇制度の改善などが実現されると、女性が活躍しやすい環境が整います。これによって、働く女性たちが自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるようになり、業務効率化や生産性向上につながるでしょう。
また働き方に多様性が生まれると、男性にとっても働きやすい環境となります。従業員エンゲージメントが向上し、企業全体の活性化も促進されるでしょう。
| 関連記事 今更聞けない【働き方改革】とは? |
ダイバーシティの促進が実現する
女性管理職が増えることで、企業内において多様性が促進されます。
女性ならではの視点で多様な意見が集まれば、今までになかった斬新なアイデアや発想、新たなビジネスチャンスが生まれることが期待できるでしょう。
ダイバーシティが推進されると、他社との差別化や企業価値の向上にもつながっていくはずです。
人事評価の公平性・透明性が向上する
女性管理職を増やすためには、古くから根づく性別バイアスを排除する必要があります。
性別に基づいた偏った評価がなくなり、従業員の純粋な能力を評価する手法に移行できれば、人事評価の公平性や透明性が高まります。
また女性管理職が活躍すると、評価に対する新たな視点が生まれる可能性もあります。より公正かつ納得感のある人事評価になることが期待できるでしょう。
女性管理職のロールモデルが生まれる
女性管理職の増加によって、女性が経営層やリーダーのポジションになることが現実的な目標となります。若年層の女性たちのロールモデルとなる存在があらわれることで、将来的により多くの女性たちがキャリアアップを目指すようになるかもしれません。
またキャリアアップの可能性が明確になると、優秀な人材を自社に定着させることができ、企業活動の安定化にもつながります。
社会的評価が向上する
女性管理職を増やす取り組みは、顧客や求職者など、さまざまなステークホルダーに「女性の働きやすさを真剣に考える企業」「ワークライフバランスに注力する企業」というよい印象を与えます。
自社の社会的評価が向上すれば、競合との差別化がはかれたり、より優秀な人材の獲得にもつながるでしょう。
部署内のコミュニケーションが円滑になる
女性管理職が増えれば、ほかの女性従業員も組織内でより活躍しやすくなるでしょう。
女性管理職は女性従業員とのコミュニケーションを通じて、男性管理職には言いにくい職場環境や労働条件に関する問題点を把握できるかもしれません。
また、女性従業員がより自由に発言できるようになることで、男女問わず部署内のコミュニケーションが円滑になり、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
ESG投資家からの注目が集まる
女性が活躍できる職場環境の整備や、女性が経営層や取締役会に参加できるようなガバナンスの改善が評価されると、ESG(環境、社会、ガバナンス)投資家からの支持を得やすくなるでしょう。
また女性管理職の増加は、企業の長期的な成長や収益性の向上にもつながるとされています。女性管理職を増やそうとする企業は、ESG投資家にとっても魅力的な投資先となるかもしれません。
女性管理職を増やすための課題
「女性管理職を増やしたい」と考える企業は増えているとはいえ、実現にはまだまだ課題があるようです。厚生労働省が発表している調査資料によると「女性社員の管理職昇進意欲の向上」が課題と回答する企業がもっとも多いようです。
以降、上位5つの課題を抜粋してご紹介します。
| 女性の活躍推進における課題 |
|---|
| 1.女性社員の管理職昇進意欲の向上 |
| 2.両立支援制度利用者の代替要員確保やサポート体制作り |
| 3.女性活躍推進の体制整備や担当者の時間確保 |
| 4.部署による女性の能力発揮機会の差 |
| 5.女性応募者の少なさ |
1つめの課題だけを見ると女性が管理職にキャリアアップしたいというモチベーションが足りないと捉えられてしまうかもしれません。
しかし、2番目や3番目に多い課題から考えられるのは、そもそも女性管理職を増やす取り組みが不十分で、風土が整っていない実情がうかがえます。
また、企業が「なぜ女性管理職を増やしたいのか」という理由や目的が明確でないことから、女性がキャリアアップに積極的になれないという課題もあるようです。
参照:『「女性の活躍推進」にむけた取組施策集』平成27年度厚生労働省委託事業|三菱UFJリサーチ&コンサルティング
女性管理職を増やす取り組み
実際に女性管理職を増やしたいと考えたとき、企業としてどのようなことに取り組めばよいのでしょうか。企業が取り組んでおきたい施策をご紹介します。
| ・目的や目標を明確にする ・社内で適任者を探す ・制度を整える ・管理職のイメージアップをする ・セミナーや研修を実施する ・ジョブローテーション制度を導入する ・上層部の意識改革を実施する ・人事評価や給与制度を見直す |
目的や目標を明確にする
まずは女性のキャリアアップを支援するための、具体的な目的や目標を設定します。なぜ女性管理職を増やすべきなのか、という点を明らかにしましょう。
たとえば「自社に新しいイノベーションを起こしたい」という目的があるのなら、それを実現する具体的な数値目標などを設定することが大切です。
また、目的や目標は既存の女性従業員にも明確に伝えなければなりません。「収入が上がる」「裁量権限が広がる」などのメリットも提示し、キャリアアップ意欲を高めるなど、女性が管理職を目指しやすい風土をつくるようにしましょう。
| 関連記事 KPIとは|中間的な定量目標 |
社内で適任者を探す
まずは既存の従業員の中から女性管理職に向いている人材を探しましょう。
今いる従業員は、自社のビジネスモデルや文化に精通しており、組織内の信頼を得ている可能性が高いでしょう。そのため、新たに人材を採用するよりも早く女性管理職としての活躍が期待できます。
適性がある女性従業員がいた場合、キャリアアップや昇給の機会を与えるなど、組織としてバックアップするとよいでしょう。
| 関連記事 抜擢人事のメリット・デメリット |
制度を整える
女性が活躍しやすい制度を整備することで、管理職になりやすい職場環境をつくることも重要です。
たとえば育児休業や時短勤務、リモートワークなどの制度を導入すると、子育てと仕事が両立しやすくなるでしょう。
保育園が決まらないために職場復帰できない女性は多いといわれているため、場合によっては社内に託児所を設けるなども一案です。子育てをしながらでも昇進できる制度の導入も必要です。
管理職のイメージアップをする
「管理職=つらい仕事」というネガティブなイメージを払拭しましょう。
権限や待遇の見直しを実施するだけでなく、既存の従業員の中から女性管理職を登用したり、新たな人材を採用するのも効果的です。
また根本的な解決をするには、業務を洗い出して効率化できる方法はないか見直すことをおすすめします。既存の女性管理職が活躍しているのを見れば、管理職を目指したいと考える女性従業員が増えるかもしれません。
セミナーや研修を実施する
管理職に必要となるスキルや知識が身につく研修やセミナーを実施し、女性が能力を発揮しやすくすることも重要です。
女性従業員向けのセミナーや研修を実施し、スキルアップやキャリアアップを支援しましょう。入社歴別の研修や育児休業明けでブランクのある従業員向けの研修など、それぞれの状況に合わせた育成プログラムを用意するとよいでしょう。
ジョブローテーション制度を導入する
異なる業務経験を積むことができるジョブローテーション制度を導入するのも一案です。さまざまな部署で経験を広げることで、女性従業員が活躍の場を見つけやすくなります。
ただし、ジョブローテーション制度を導入する際は、従業員の特性を見極めて配属先を決めたり、本人の同意を得たりするのを忘れないようにしましょう。
上層部の意識改革を実施する
上層部に対して、女性活躍推進についての意識改革を実施することも必要です。現代においても、性別バイアスがかかった考えを持つ人は少なくありません。
これからの時代は、男女問わず同等に活躍する環境が必要であることや、女性管理職を増やすメリットなどを伝えます。女性が活躍することが当たり前となるよう、上層部の理解を促しましょう。
人事評価や給与制度を見直す
企業は、女性社員が働きやすい環境を整えるために、人事評価や給与制度を見直してみましょう。たとえば、育児休業中でも昇給や昇進が可能な制度や、男女同一賃金の実現などが挙げられます。
女性管理職を増やしている企業事例
実際に女性管理職を増やすことに成功している企業では、どのような取り組みを行っているのでしょうか。3つの企業事例を紹介します。
サイネオス・ヘルス・コマーシャル株式会社
医薬品販売の受託業務を展開するサイネオス・ヘルス・コマーシャル株式会社は、女性MRの多くが抱えている以下の課題に応えることこそが、女性活躍推進のキーワードだと見極めました。
| ・ライフイベント後も働き続けたいと考えていても、叶えられていないこと ・配偶者の転勤が離職する最大の理由であること ・家庭の事情を直近のリーダーや上司に共有しづらいこと |
そして、働き方や就業場所を制限せずに活躍できる「リモートMR」を育成し始めたのです。
また同社では、MR資格を持っているが出産や家族の転勤などで離職した女性の中途採用も積極的に行い、ワーキングマザーMRやブランクのある元MRなどにも支援環境を整備しています。
MR業界においては男性が優位である風土が根強いといわれています。そのため「育成環境の整備」や「ダイバーシティ・プロジェクト」施策によって女性のキャリアアップを支援し、女性の持続的成長をバックアップする環境を推進しています。
参照:『働き方改革で一番成長できるのはワーキングマザー。その理由とは――』d's JOURNAL
株式会社青森銀行
青森銀行は、10年以上前までは、せっかくスキルを身につけても結婚を機に退職する女性行員が多い傾向にありました。
そこで同社では、女性がさまざまな場面で活躍しやすい環境づくりや、退職した女性行員の再就職支援に注力し始めます。
若手や中堅などの女性行員に対してキャリアアップに必要な研修を充実させて、女性管理職が後輩の女性行員に積極的に声をかけるなどの取り組みを行ったのです。
結果的に2016年から2019年の3年間で女性管理職・監督者を14名増加させることに成功しました。
参照:『女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集』厚生労働省
イオン株式会社
イオン株式会社では、ダイバーシティ推進の取り組みの一つとして、積極的に女性活躍推進を行っています。既存の女性管理職を対象にした対話型マネジメント研修を実施し、女性管理職のロールモデルとして後進の育成を目指しています。
そのほか、管理職一歩手前の女性・初級管理職の女性を対象にした研修では、管理職になることの魅力を身近に感じ、上昇意欲を高める取り組みを行っているようです。
また、職歴5〜8年目の女性従業員を対象に、ワークライフバランスを保ちながら活躍し続けるためのライフプランについて考える研修を実施するなど、女性従業員のキャリアプランの幅を広げる環境を整えています。
| 関連記事 後継者育成の方法とは? |
女性管理職を増やす国の施策
日本政府は、女性の活躍推進を目的として、以下のような施策を実施しています。
政府が掲げる目標値
政府はかつて、2020年までに社会の指導的地位に占める女性の割合を30%程度にすることを目標としていました。
しかし、国家公務員や民間企業の女性管理職の割合がいまだ低い水準にあるため目標を立て直し、2023年6月に、女性管理職比率について新たな方針を公表しました。
1つは2025年を目安に女性役員を1名以上選任すること、もう1つは2030年までに、東証プライム市場に上場している企業の女性役員の割合を3割以上にすることです。
同時に、目標の達成に向けて行動計画をつくることをすすめています。
女性活躍推進法
女性活躍推進法は、日本において女性の活躍を促進し男女間の格差を解消することを目的として、2015年に制定された法律です。
この法律では、民間企業や国家公務員等の事業主に対して女性の活用・登用・昇進を進めるよう、目標数値の設定や透明性の確保、報告などを義務づけています。
また、女性の育児や介護などのライフイベントに対応した柔軟な働き方の実現や、男女が同じ職場で働くことによる職場環境の改善などの促進を目指しています。
| 関連記事 女性活躍推進法をわかりやすく解説 |
まとめ
管理職に対するネガティブなイメージや男性中心の労働環境、女性が活躍できる環境整備の不足など、さまざまな理由から日本の女性管理職の割合は低い傾向にあります。
しかしこれからの時代、企業がイノベーションを起こしたり、生産性を高めたりしていくためには、女性の活躍推進は避けて通れません。そのためには、企業は女性管理職を増やすための取り組みを進めていく必要があるでしょう。
本記事でご紹介した女性管理職を増やす取り組みや企業の成功事例を参考に、自社でできることから始めてみてはいかがでしょうか。
女性管理職の選出にも、タレントマネジメントの『スマカン』
タレントマネジメントシステム『スマカン』は、人材情報を一元化し、個々の能力や評価を可視化できます。埋もれていた従業員の経歴やスキル、適正などをひと目で把握できるため、女性管理職に適した人材を効率よく見つけられるでしょう。
また育成プランニングもシステム上で管理できるため、個々の保有スキルと人事評価を連携しながら、個人のスキルアップや管理職育成研修の立案などに役立てられます。
システムの導入も検討しつつ、女性管理職を増やす取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。
『スマカン』は目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE
関連資料を無料でご利用いただけます
コラム記事カテゴリ
こちらの記事もおすすめ
スマカンの導入をご検討の方へ
実際の画面が見られる
デモを実施中!